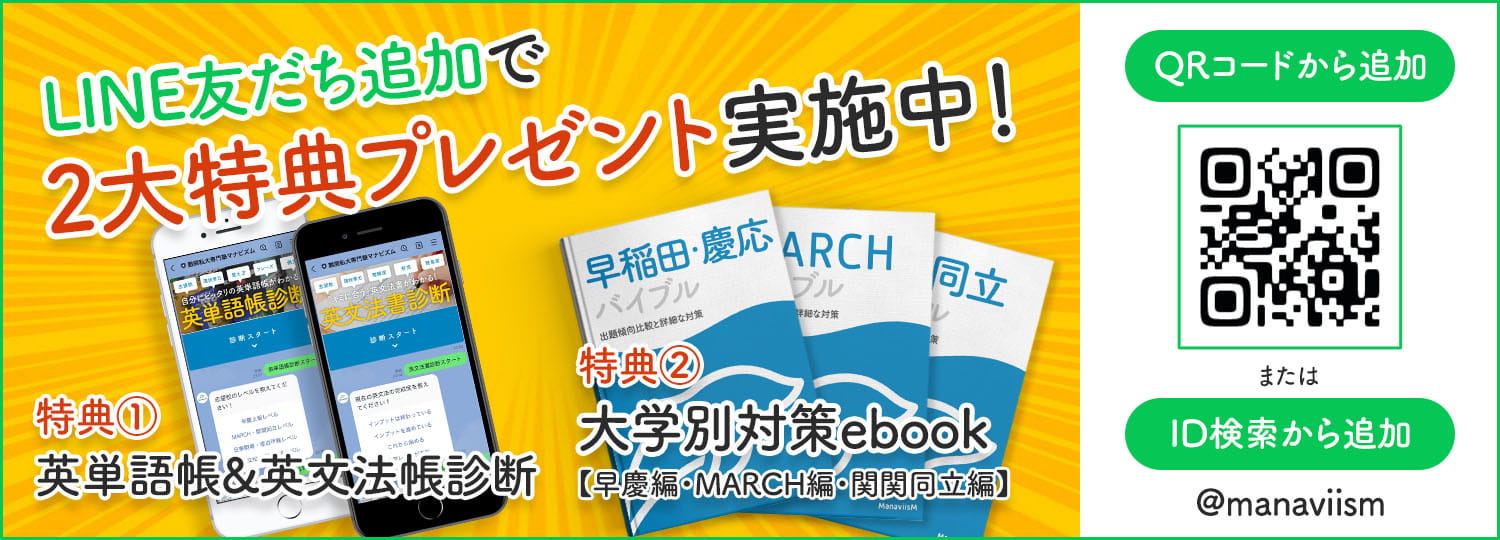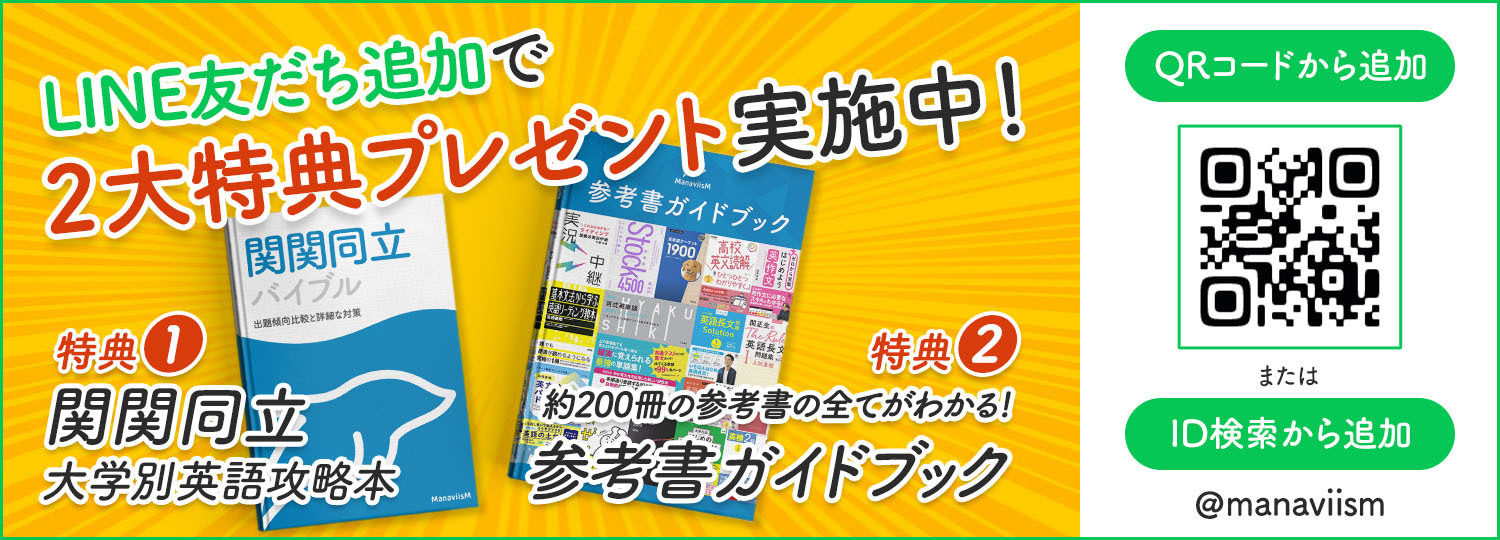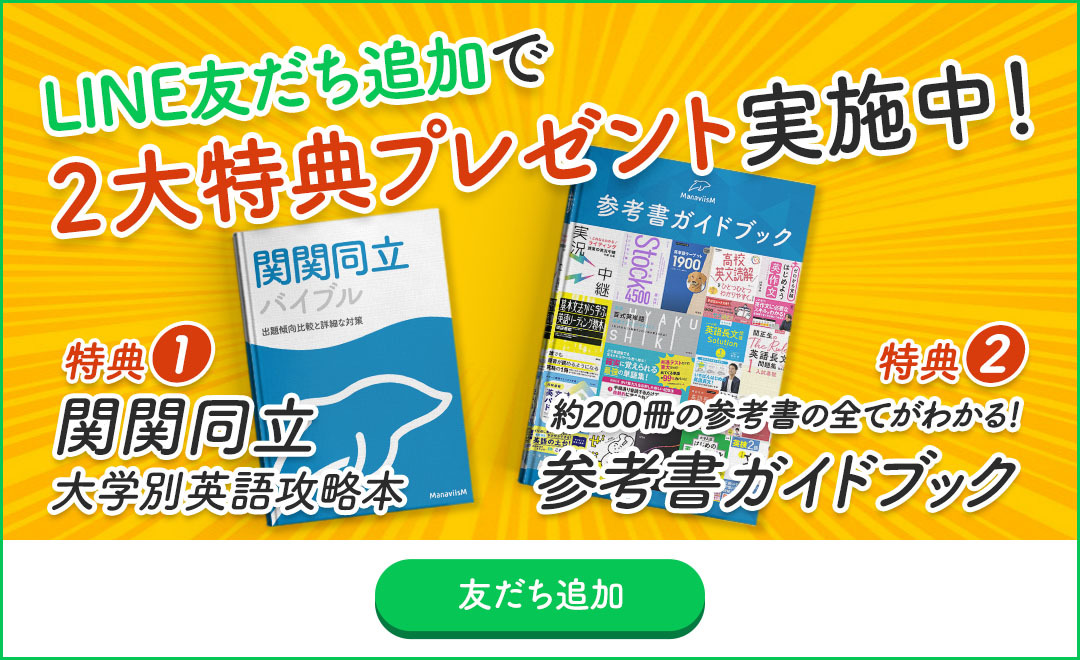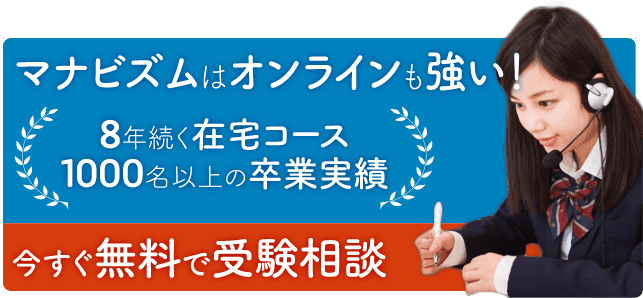【文系数学編】近畿大学の入試対策・オススメ参考書
更新日: (公開日: ) KINKI

このページでは近畿大学の文系数学の対策・勉強法について解説していきます。
問題構成
具体的な近畿大学の文系数学の問題構成は上図のように全3題構成になっています。
全問マークで空欄の数が約50個あります。
大問の配点は、ほぼ均等で小問の配点は3点から5点です。だいたい大問は35点、35点、30点という構成が多くなっています。大問が3つでそれを60分間で解いていかなければなりません。
目標点数
続いて目標点数に移っていきます。
近畿大学の文系数学は多くの学部で100点満点中80点以上を目標としたいです。
従って各大問8割以上が取れるように、これから話す勉強法を参考にして実力をつけていくようにしてください。注意点としてはすべてマーク式になっているので部分点がもらえません。ただ解けるようになるだけではなくて早く正確に解いていけるようにしていきましょう。
具体的な勉強法
それではここから具体的な勉強法についてお話していきます。近畿大学の文系数学の攻略のコツは問題を多角的に見ることです。毎年共通して見られる特徴として2点あります。
- 複数の単元が融合した問題が多い
- 一つの大問で複数の知識を問われる
この2点です。
1つ目については微分と積分であったり、図形とベクトルのようなよく出てくる複合問題が出題されるのはもちろん方程式と数列のような演習問題解いていても、なかなか見ないような複合問題も出題されます。
2つ目については例えば1つの大問の中で2つの図形の交点であったり二直線のなす角、平行移動、軌跡、面積、これが一個の大問で問われたこともあります。従って単元別の勉強にとどまらず総合的な数学力が問われている問題になっていることに注意しましょう。
近畿大学の入試問題では、総合的な力が求められます。
ただ勉強していく上では単元別に進めていくようにしましょう。
具体的には4段階で
- 教科書内容の理解
- 単元ごとの理解型暗記
- センター試験でのアウトプット
- 近畿大学の過去問に取り組む
4.までくれば自分の取りたい点数を時間内で取れるように訓練していきましょう。
それではここから一つずつ具体的にお話していきます。
教科書内容の理解
教科書で進められる人は教科書を使ってもらって問題ありませんただ教科書にちょっと苦手意識があるという人は「やさしい高校数学」
この参考書をお勧めしておきます。この参考書は先生と生徒が対話形式で進む形になっているので、すごく理解しやすいようになっています。だいたい1A2Bを合わせて2、3ヶ月ぐらいで1周するようにしてください。
続いて教科書内容が理解出来たらパターン問題の理解型暗記に進んでいきます。
➁パターン問題の理解型暗記
パターン問題というのはこういう出題に対してはこういう風に答えるという、その所作が決まっているような問題のことを指します。
数学には思考力が重要だという風に思われがちですが、そもそもこういう問題にはこう答えるというのを覚えておかないと話になりません。
なので、まずはパターン問題の理解型暗記をしっかりしていくようにしましょう。
近畿大学の過去問を見たらわかるのですが、ただ丸暗記になってしまうと、総合的な数学力を問われた場合全く歯が立ちません。なので、どの解法を用いるかだけじゃなく、なぜその解法を用いて解かなければならないのかというのをしっかりと理解した上でインプットしていくようにしてください。
このパターン問題の理解型暗記には「文系の数学重要事項完全習得編」
この参考書をお勧めしておきます。
この参考書を使うときには記号のABC をつけていくようにしてください
A:完璧に解けた
B:方針は合っていたもののミスしてしまった
C:解けなかった
この3つのチェックをしていくようにしてください
一周目をするときにABCの記号をつけていき、2周目以降はBCをAにできるように勉強していきます。Cを付けた問題に関しては2回連続でAが取れるように繰り返し演習していくようにしていってください。
この参考書は152題例題がついてますが、この152題が完璧になっているかどうかによって今後の数学力が決まってきます。この問題が来た時にこの解法を使えばいいんだだけでなく、なぜその解法を使うべきなのかというのをしっかりと理解した上で覚えていくようにしてください。
また、どれだけ遅くても10月にはセンター数学の演習に入りたいです。
なのでそこから逆算して自分で勉強計画を組むようにしていってください。いよいよパターン問題の理解型暗記が終わればその演習アウトプットに入っていきます。
センター試験でのアウトプット
演習の材料としては「センター数学」を使用していきましょう。
この段階で
①インプットに抜け漏れはないかということ
②問題の誘導にきちんとのる力を鍛える
というこの2点を意識してほしいです。
センター問題集は色々あるんですが、河合塾の黒本に関しては解説がすごく詳しくて自分がどの段階からできてないのかというのがすごくわかりやすくなってるのでこの河合塾の黒本をお勧めしておきます。
この段階でよくあるのが、この単元だけ全然出来ないなぁという風に苦手な単元が浮き彫りになることです。そうなった時に行ってほしいのは
➀教科書内容の理解に戻る
➁パターン問題の理解型暗記に戻る
この2つをまずやってほしいのですが、それでもできるようにならない。そういった場合は「数学の〇〇が面白いほどわかる本」のシリーズをお勧めしております。
特に坂田明先生が書いたものをおススメします。
数学が本当に苦手だという風に思っている人でも分かるように書かれているのでここでまず苦手分野をしっかりとおさえておくようにしましょう。「整数問題の面白いほどわかる本」のシリーズを買う場合は佐々木貴宏先生の本を買うようにしてください。
ここまできたら最後は近畿大学の過去問を解いていくようにしましょう。
過去問・赤本に関する合格者の使い方・何年分すべきか?などの詳細はコチラを御覧ください。
出題形式や時間配分に慣れていくのはもちろんですが、始めに言ったように問題を多角的に見るっていうのをしっかりと過去問を通して自分で体感するようにしてください。
近畿大学の問題は入試方式によって難易度が変わったりはしません。
なので一般前期のものを全て解くのはもちろん手に入る過去問は全て解くようにしてください。
この様に参考書の選び方1つをとっても大学との相性・オススメ度は異なります。
【合格者は知っている!】失敗しない参考書の選び方・使い方にの詳細はコチラ!
勉強法まとめ
始めは教科書かやさしい高校数学で基本的な考えを理解するようにしましょう。
その後に文系の数学重要事項完全習得編でパターン問題の理解型暗記をしていくようにしましょう。
パターン問題が全て解けるようになったらセンター数学で演習をしていきましょう。
おすすめは河合塾の黒本です。この時苦手な単元が見つかれば数学の〇〇が面白いほどわかる本シリーズで対策していくようにしましょう。
最後に過去問に取り組み、近大に合わせた対策をしていきましょう。
以上で文系数学の勉強法の紹介はおしまいです。近畿大学の文系数学では途方もなく難しいような問題は出題されません。ただ色々な見方で問題を解いていくようにしていかないといけないんでそれを念頭に置いた上で各単元の基礎からしっかりと勉強していくようにしましょう。
それでは、近畿大学の文系数学の勉強法の解説はここまでにしたいと思います!
近畿大学に最短で合格するより詳しい勉強法を知りたい方はぜひ無料体験コンサルをお申し込み下さい。
詳しい流れを知りたいという方は以下の動画を参照して下さい!