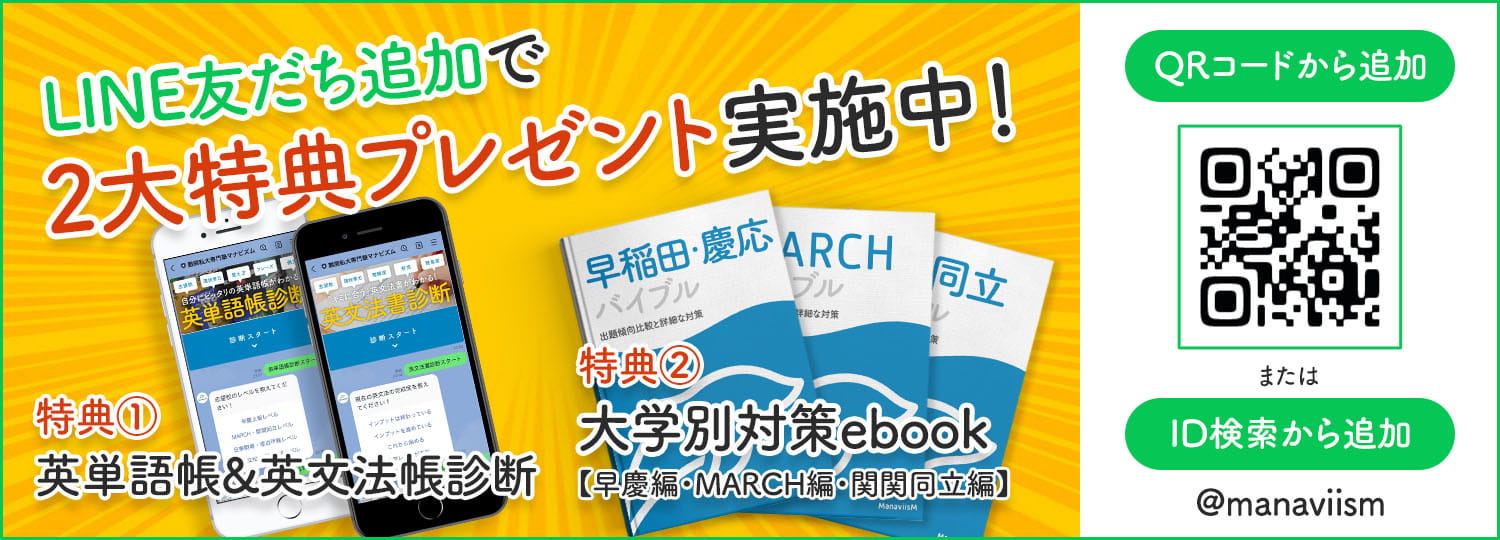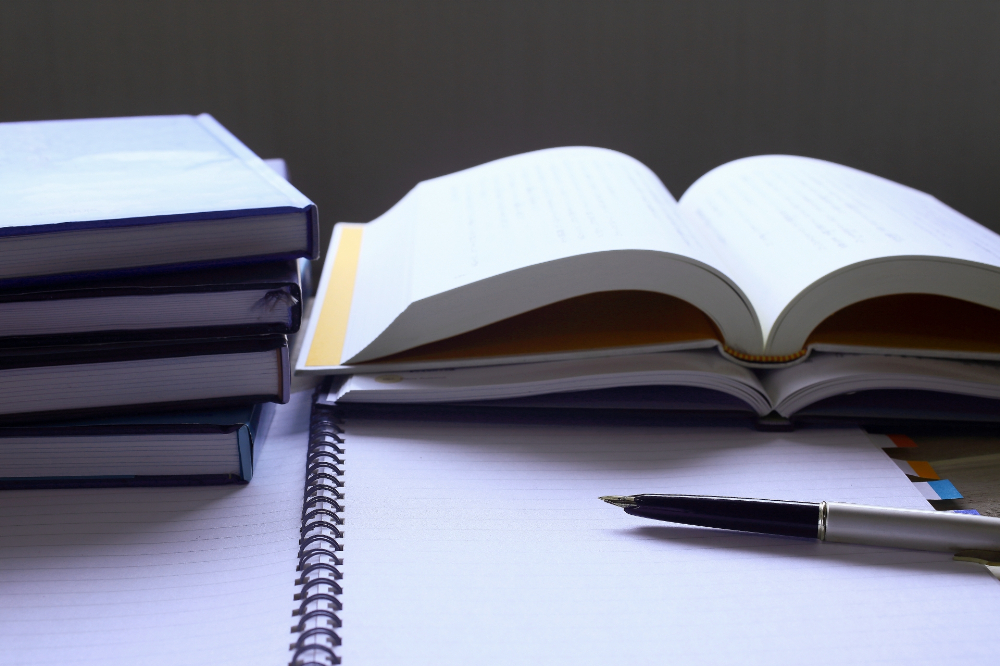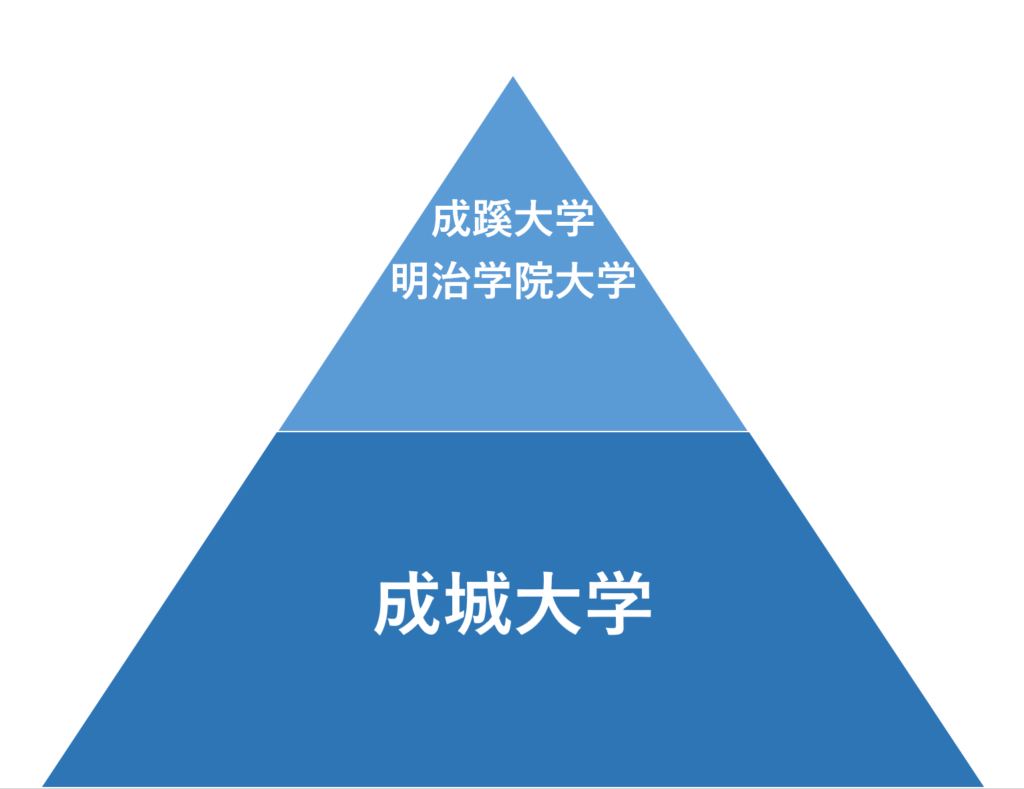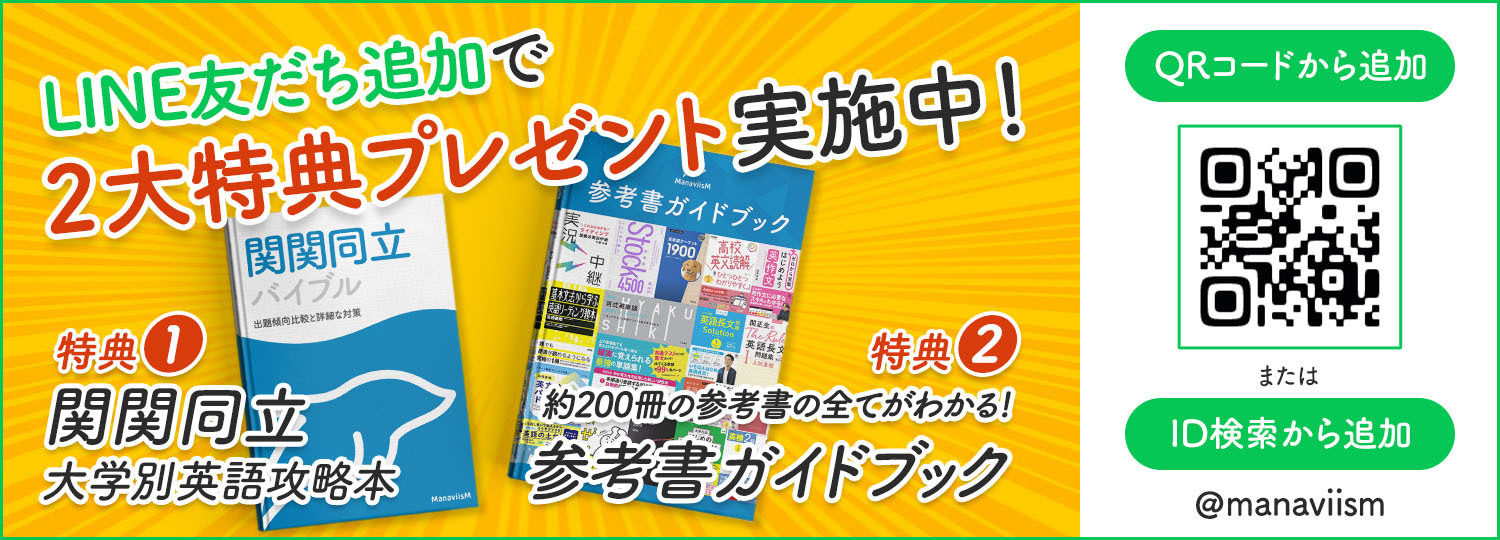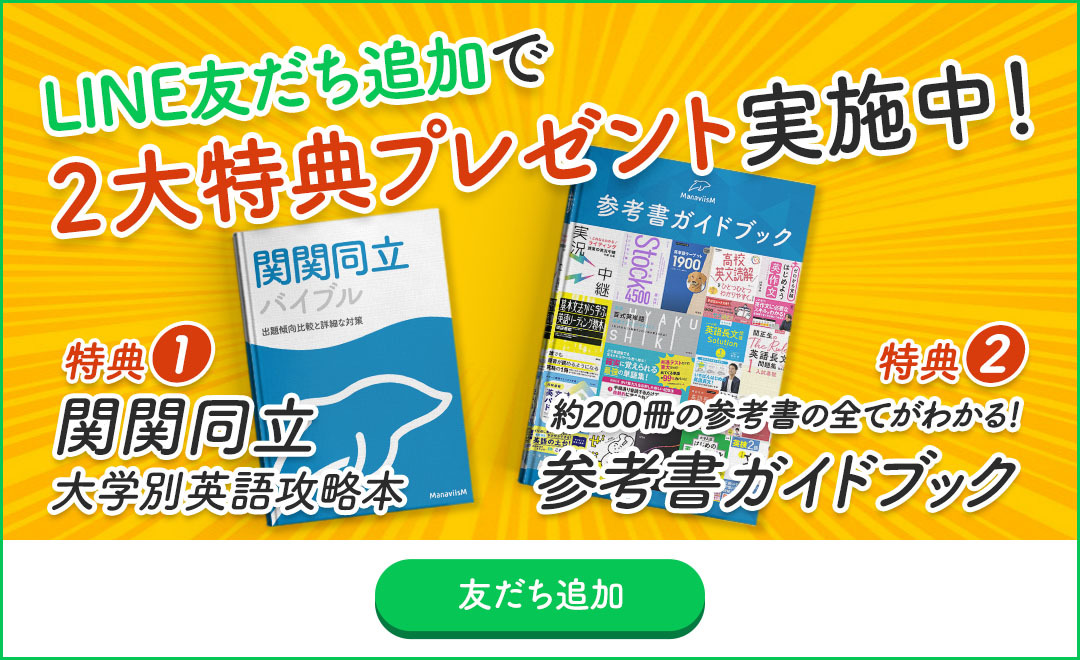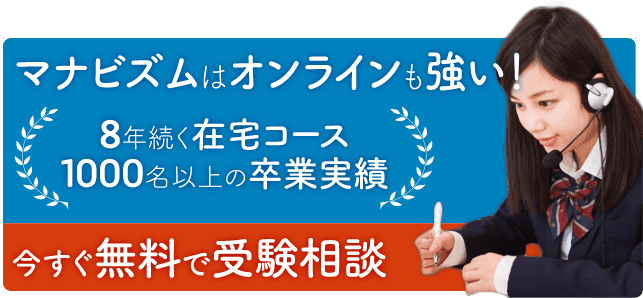【親御さん必見】大学受験で「ダメな塾」を見極めるには?失敗しない選び方のポイント
更新日: (公開日: ) COLUMN
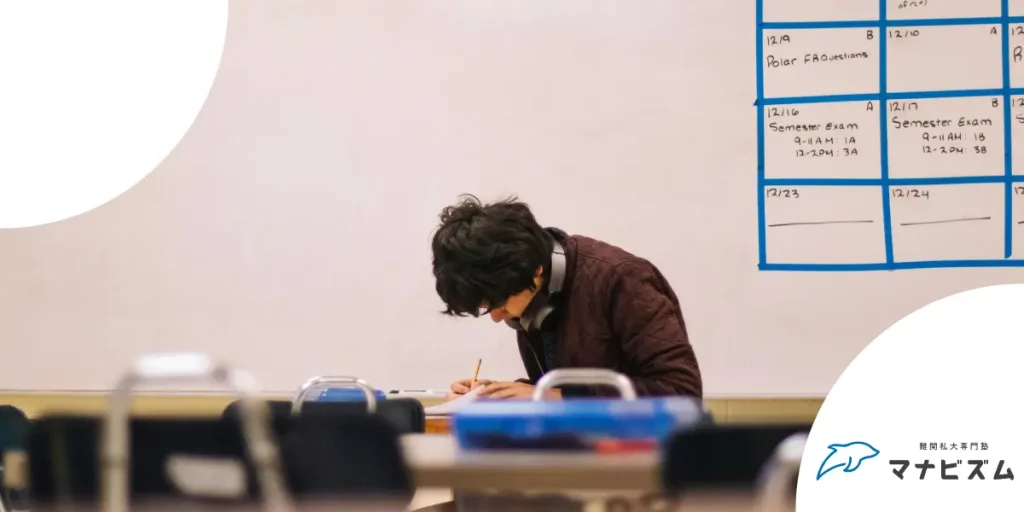
大学受験を控えたお子さんを持つ保護者の皆さん、塾選びに悩んでいませんか?
「高い授業料を払っても成績が上がらない」「本当にこの塾で大丈夫なのか」という不安は尽きません。実は、保護者が「良い塾」の基準を勘違いしており、それが受験失敗の原因になっていることもあります。
本記事では、大学受験における「ダメな塾」の特徴と見極め方を詳しく解説します。
【親御さん必見】大学受験で「ダメな塾」を見極めるには?
【動画でもご覧いただけます!】
授業のわかりやすさや講師の人気度だけで判断していませんか?
大学受験の成否を左右する「塾選び」。本当に重要なのは「授業の質」だけではなく、子どもが自ら学ぶ姿勢を講師が育てられるかがカギとなります。
授業を受けるだけでは成績は上がらない
保護者の方は、「塾に入れて授業を受ければ点数が上がる」と思っています。しかし、どれだけ素晴らしい授業を受けても、自習の質が悪ければ成績は上がりません。
私たちマナビズムの授業は日本一わかりやすいという自信がありますが、それだけでは不十分です。授業を受けたあと、例えば「ミニブックの復習をちゃんとやる」といった次のアクションを間違えれば意味がありません。
大学受験において、授業はあくまでも「インプット」の段階。本当に重要なのは、そのあとの「アウトプット」である自習の質です。ダメな塾は、この自習の部分をサポートせず、授業だけに焦点を当てています。
成績が上がるのは”授業中”ではなく”授業後”
実際、成績が上がるのは授業を受けている時間ではなく、自習している時間です。保護者様は授業ばかりに目を向けやすいですが、まず自習室に行く習慣を身につけること、ここに塾のサポートが必要です。
「成績が上がらない → 塾が合っていない → 転塾」となる方は少なくありません。ただ、転塾しても同じスタンスなら、また「ダメな塾か…」と同じ結果になってしまいます。
勉強のやり方・塾の使い方をまず見直しましょう。良い塾とは、授業の質だけでなく、授業後の自習をどれだけサポートしてくれるかという点が判断基準になります。
見るべきは講師?授業のわかりやすさ?
動画でもマナビズムの代表が触れていますが、「教えるのが仕事」だと思っている講師は、自分が気持ちよくなりたいだけだということです。本当に良い講師とは、「先生がいないときに頑張れる子を育てられる講師」です。
「来週までにこれやらないと恥ずかしいな…」と生徒に思わせる講師こそが名講師。であるからこそ、授業の質より重要なのは「目の色が変わったか」です。
通常、保護者様は授業の分かりやすさを気にするでしょう。ただ、これからは、「子どもが目の色を変えて勉強しはじめたか」を見てください。
現役生は受験の基準を知らないので、塾がその基準を示します。ダメな塾は、この「基準を示す」という役割を果たさず、ただ授業をこなすだけになってしまいます。
大学受験では入塾がダメなタイミングもある
マナビズムでは、保護者に連れられて来たものの、本人にはやる気がないというケースも少なくありません。このような状況で大切なのは、無理に塾に入れないことです。
むしろ、その子が自ら「やる」と決めるまでの『過程』こそ、塾選びよりも重要となります。このタイミングであれば、対話を通して、自らの優先順位・覚悟を見つめ直すことがポイントです。
覚悟が固まったタイミングで塾に入れることが、もっとも成果につながります。焦って先回りするのではなく、”光るタイミング”を信じて待つのも保護者の大切な役目です。
ダメな塾は、生徒のやる気に関係なく、とにかく入塾させようとします。しかし、本人の覚悟なしにはじめた受験勉強は長続きせず、結果も出にくいです。
マナビズムは”甘くない塾”です
私たちマナビズムは「合格が当たり前」と考えており、合格基準に合わせて指導します。甘やかして「今の状態で満足させる」指導はしません。
本当に目指す大学があるなら、そこに向かってやるべきことは決まっているはずです。だからこそ、合格基準の努力量に引き上げていくのが、私たちのやり方です。
今、保護者様の目から見て「努力が伴っていないな」と感じる場合は、ぜひ一度マナビズムをお子さんにご紹介ください。
保護者様が言いづらいことでも、私たちが生徒と面談して、やる気の根本原因を探って改善します。関関同立など難関私大を本気で目指すなら、ぜひマナビズムの門を叩いてください。
大学受験で選んではいけないダメな塾のよくある特徴

大学受験において避けるべき「ダメな塾」には、以下の共通した特徴があります。塾選びの際には、以下のような特徴を持つ塾には要注意です。
- 合格実績だけを誇り、その内訳を明かさない
- 講師の質が低く、教え方が一方的
- 指導方針が曖昧で一貫していない
- 費用体系が不透明で追加料金が多い
- 自習環境が整っておらず、集中できない
- フィードバックが不足し、改善点が見えない
- 生徒の個性や目標を無視した画一的な指導が行われている
いずれも単独ではなく、複数組み合わさって現れます。大学受験では「わかる」だけでなく「できる」ことが重要です。理解度を確認し、弱点を補強する仕組みがないダメな塾では成績向上は難しいでしょう。
脱ダメな塾!大学受験で失敗しない塾選びの5つのポイント
【動画でもご覧いただけます!】
大学受験でダメな塾を選ばないためには、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。
- 人として信頼できるか
- 不安や悩みを解決してくれるか
- お子様が「やる」といえるか
- 合格に基準を合わせてくれるか
- 同じ能力レベルの講師がいるか
人として信頼できるか
塾選びにおいて、授業内容や教材以上に重要なのが「人として任せられるか」という点です。保護者の方にとっても、生徒本人にとっても、もっとも見極めるべきポイントの1つです。
例えば、マナビズムでは体験説明会の際に「この先生、この塾に人生を預けていいのか」を必ず見てほしいと伝えています。
どれだけ授業が分かりやすくても、どれだけ有名な塾でも、結局は「この人のために頑張りたい」、「相談できる存在がいる」という信頼がなければ、長期間の受験を乗り切るのは難しいです。
保護者とのやり取りも含め、誠実かつ迅速に対応してくれる塾かは信頼の土台になります。サービスの良し悪しではなく、「人」に着目した塾選びが、結果的に合否をわけるのです。
不安や悩みを解決してくれるか
そして、塾に通う目的は「不安の解消」です。本人や保護者が抱える悩みに真摯に向き合い、解消するための仕組み・サービス・人材がそろっているかが、ダメな塾を避ける条件となります。
- 家で勉強できない
- 受験情報が分からない
- 自らの実力が見えない
など、生徒によって悩みは異なります。にもかかわらず、サービスが「オンライン映像授業のみ」であったり、自習環境を用意していなかったりすれば、その塾は根本的に合っていない可能性が高いです。
また保護者も「志望校の情報がない」「何を聞けばいいのか分からない」という不安を持ちます。そうした不安を言語化して受け止め、解決の道筋を明確に提示してくれる塾であるかが、重要です。
お子様が「やる」といえるか
どれだけ優れた指導、教材、カリキュラムがそろっていても、本人に「やる」という覚悟がなければ意味がありません。マナビズムでは、入塾を検討する生徒には必ず「本気でやる気があるのか」を面と向かって確認します。
その場で本気になれない生徒には「入塾はおすすめしない」とハッキリ伝えます。厳しさではなく、本気で合格させたいという本音からです。
保護者がどれだけ「うちの子に合ってる」と思っていても、本人が納得していなければ、努力は長続きしません。塾選びの前に、「本人の覚悟」があるかを確かめること。それが、塾の成果を最大化する前提条件です。
合格に基準を合わせてくれるか
「本人に合わせる」ダメな塾があるなかで、「合格に合わせる」塾を選ぶことも重要です。モチベーションが低いからといって、生徒の現状に基準を下げて寄り添うだけでは、受かるわけがありません。
マナビズムでは、生徒が持つ「物理的に可能な時間・環境・性格」を徹底的にヒアリングしながらも、合格ラインに到達するために必要な基準を見せ、引っ張り上げる指導方針を取っています。
無理をするのではなく、甘えを許さないそのスタンスが、「今までにない勉強の基準」となります。この設計があることで、あとから「間に合わなかった」「全然成績が伸びなかった」という悲劇を防げるのです。
同じ能力レベルの講師がいるか
ダメな塾でもよくある教える側が「なぜできないのかが分からない」状態では、生徒の悩みを永遠に解消できません。
例えば、偏差値70の進学校出身の講師が、偏差値50台の生徒に「A単語が覚えられない理由」を本当に理解できるでしょうか?理解できなければ、適切なアドバイスはできません。
マナビズムでは、同じような能力・偏差値層から逆転合格を勝ち取った講師陣を重視しています。
- 実際に苦労した経験があるから、寄り添える
- 同じ失敗を乗り越えたから、対策が分かる
- 成功体験が現実味を持って伝えられる
同じレベルの講師がいるかは、塾選びの”盲点”でありながらも、実は重要な判断基準の1つです。
難関私大、関関同立を本気で目指すなら、ぜひマナビズムの無料体験授業にお越しください。お子様の可能性を最大限に引き出す環境をご用意しています。
大学受験の塾選びで後悔しないためには?

大学受験でダメな塾にあたって後悔しないためには、以下の4つのステップを踏みましょう。
- 自らの学力と目標を明確にする
- 複数の塾を比較検討する
- 体験授業で相性を確かめる
- 先輩や口コミの評判を調べる
「なんとなく周囲に流されて選んだ」「必要な情報を十分に集めずに決めた」「月謝の安さだけで選んだ」「親が一方的に決めた」という選び方はもっとも避けるべきです。
なかでも親が一方的に決めるのは、生徒のモチベーションを下げる原因になりかねません。受験直前期になるほど、塾を変えるタイミングを逃すと取り返しがつかないこともあります。
関連記事:【大学受験】塾選びで失敗した!後悔しないためにできること
大学受験でダメな塾を変えるべき5つのサイン
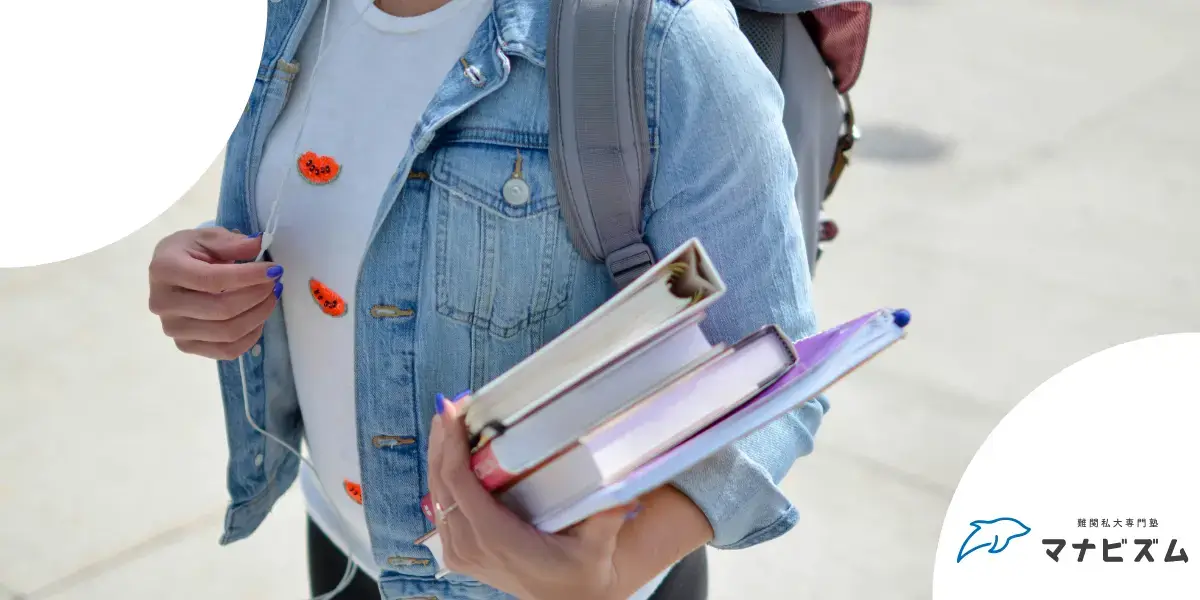
ダメな塾で失敗してしまった場合、早めに見切りをつけて変えるのも選択肢の1つです。以下の5つのサインが現れたら、塾を変えることを真剣に検討すべきでしょう。
- 成績が伸び悩んでいる
- 授業に行きたくないと感じる
- 質問しても満足な回答が得られない
- 学習計画が立てられていない
- モチベーションが下がり続けている
塾を変えることは、決して恥ずかしくありません。むしろ、自分に合わないダメな塾に留まり続けることのほうがリスクが大きいです。
塾を変える際は、単に「今の塾が嫌だから」という消極的な理由ではなく、「より自分に合った環境を求めて」という積極的な姿勢で臨むことが大切です。
関連記事:【例文】塾の体験授業後の断り方は?ポイントと注意点、しつこい勧誘の対処法も解説
まとめ
大学受験で「ダメな塾」の主な特徴は、合格実績だけを誇る、講師の質が低い、指導方針が曖昧、費用体系が不透明、自習環境が整っていない、フィードバックが不足している、生徒の個性や目標を無視するといった点です。
良い塾を選ぶためのポイントは、以下のとおりです。
- 人として信頼できるか
- 不安や悩みを解決してくれるか
- お子様自身が「やる」といえるか
- 合格に基準を合わせてくれるか
- 同じ能力レベルの講師がいるか
もし、子どもが難関私大、関関同立を本気で目指すならマナビズムへお越しください。私たちは「授業を受けるだけ」ではなく、「自習の質」にこだわり、1人ひとりに合わせた最適な学習環境を提供します!
よくある質問(FAQ)
大学受験で塾に行かない人の割合は?
一般的に大学受験で塾や予備校に通わない人の割合は、約30~40%程度といわれています。ただし、志望校のレベルや地域によって異なります。難関大学を目指す受験生の場合、塾や予備校に通う割合は高くなる傾向があります。
大学受験に塾は必要ですか?
大学受験に塾が「必要」かは、個人の状況によって異なります。塾は万人に必須というわけではありませんが、受験生にとって有益なサポートとなります。
独学で成績を上げられる自信がある場合は、必ずしも塾に通う必要はありません。しかし、難関私大などの高いレベルの大学を目指している場合は、塾の専門的な指導が役立つでしょう。
関連記事:高校生が塾に行くべきか迷ったら?判断基準と学年別・季節別のポイントを解説
大学受験対策で塾に通うならいつからが良いですか?
大学受験対策で塾に通うベストなタイミングは、志望校のレベルや現在の学力によって異なりますが、一般的には高校2年生の後半から高校3年生のはじめが適切です。高校2年生までの学習内容に少しでも不安がある生徒は、高校3年生の春期講習から塾に入るのがおすすめです。
関連記事:【受験生必見】大学受験で塾はいつから通うべき?おすすめの時期と塾選びのポイント
高3の夏から塾に通うのは遅いですか?
高3の夏から塾に通いはじめることは必ずしも遅すぎるわけではなく、現在の学力や志望校のレベル、学習習慣などによっては十分に効果を発揮できます。ただし、限られた時間を最大限に活用するために、学習計画と適切な塾選びが重要です。