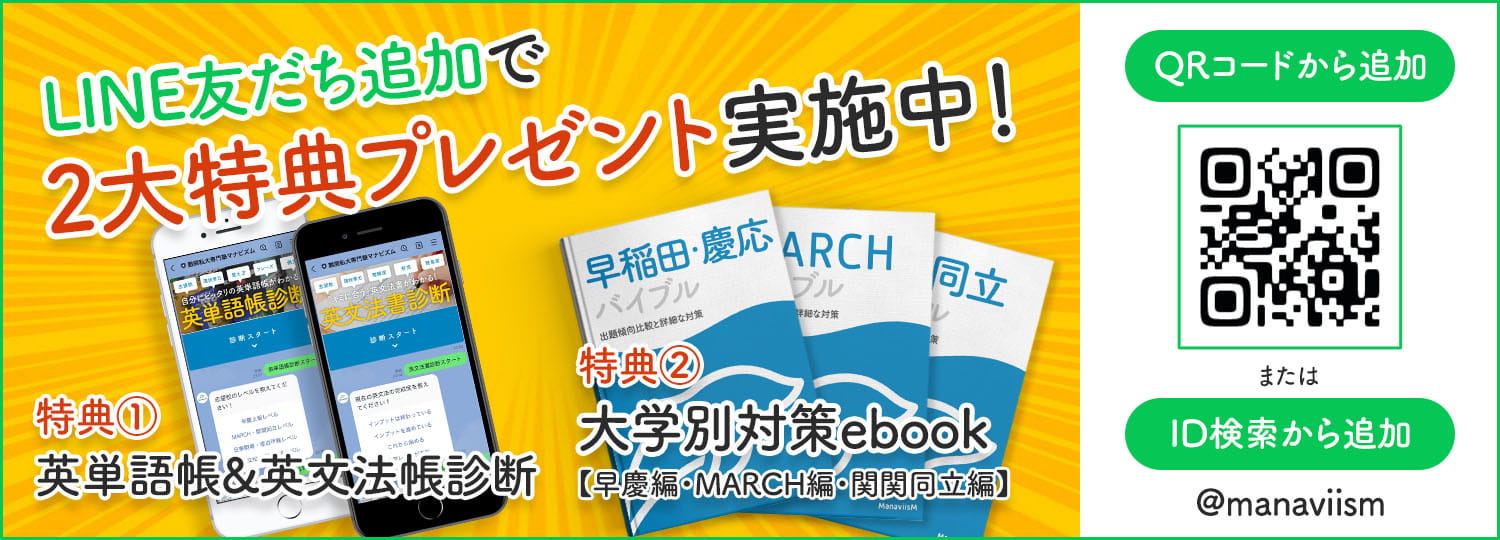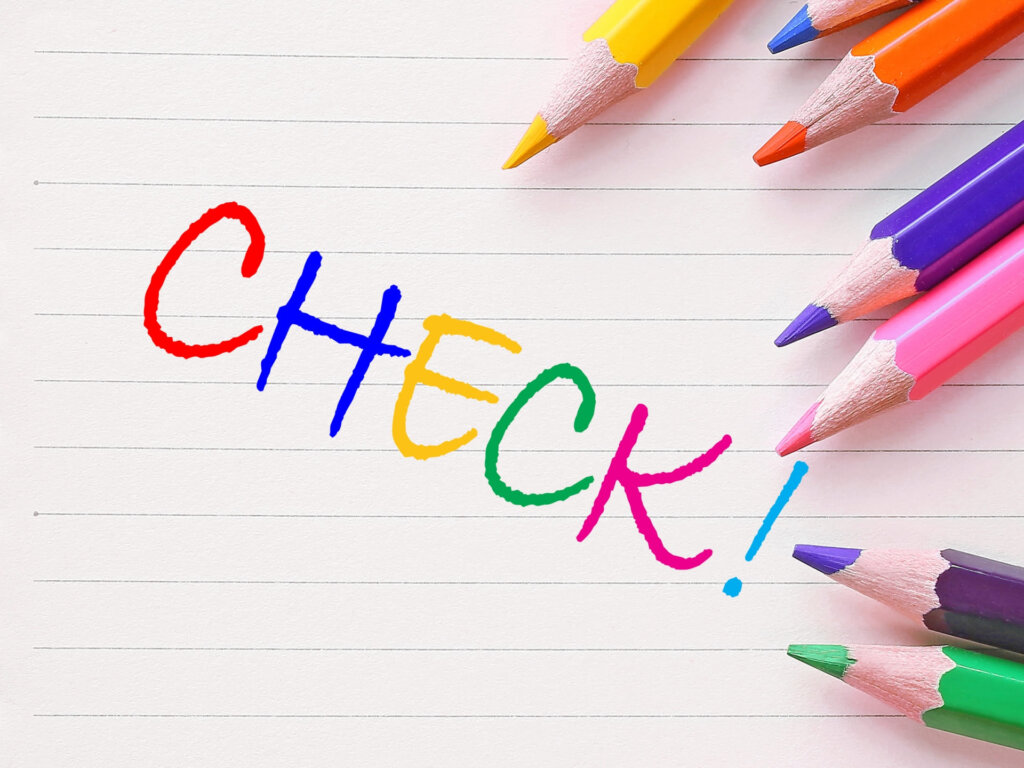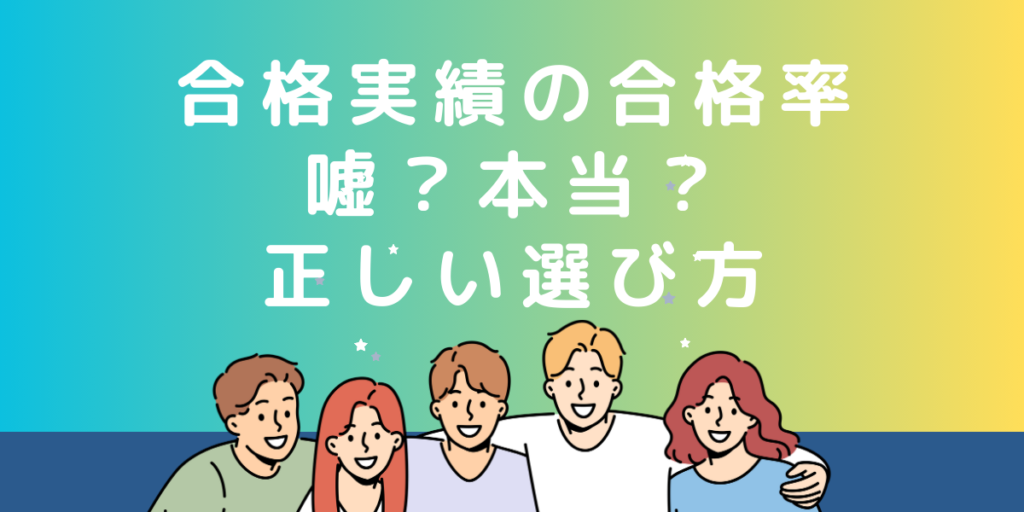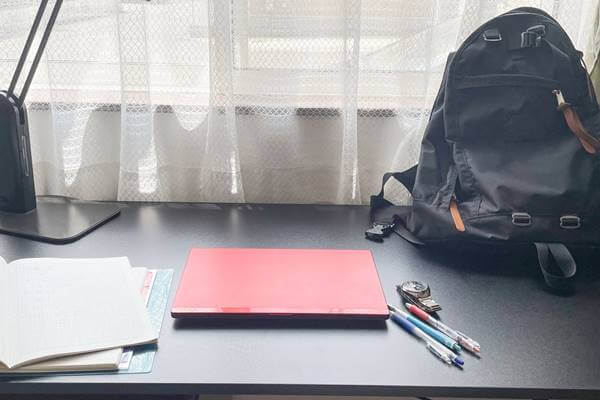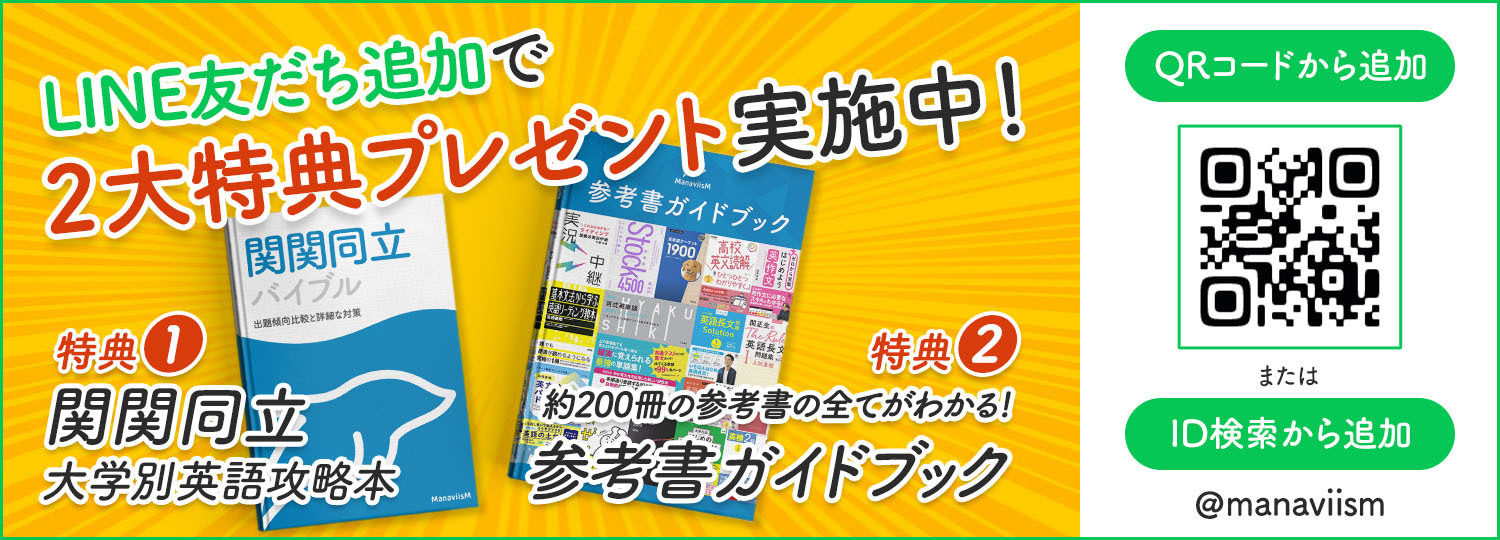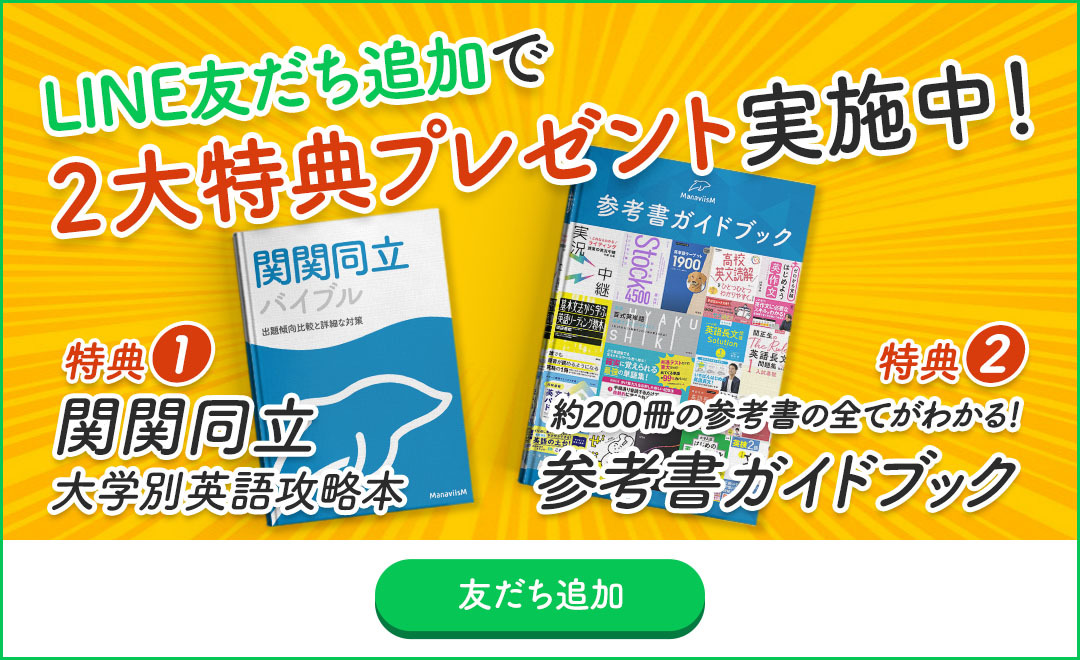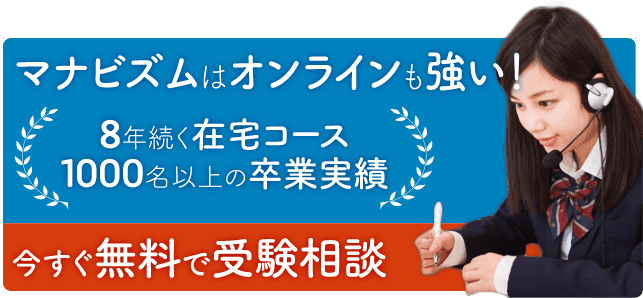【大学受験】過去問演習で点数が取れないのはなぜ?今すぐ君がやるべきこと
更新日: (公開日: ) COLUMN

受験生ならだれしも通る道。
- 「こんなに頑張っているのに、過去問の点数が全然伸びない…」
- 「周りは結果を出しているのに、自分だけ取り残されている気がする」
難関私大(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学などの関関同立)を目指すキミにとって、今は不安で胸が苦しい時期のはずです。
しかし、過去問で思うように点数が取れないのは、実は珍しい経験ではありません。
むしろ、この壁を乗り越えられるかが、合格と不合格の分かれ道になります。
今回は、過去問演習で点数が取れない理由を5つの視点から解説し、今すぐキミがやるべきことを具体的にお伝えします。
「なぜ点数が伸びないのか」が明確になり、「次にどう動けばいいのか」を解決する糸口にしてください。
YouTube動画でもご覧いただけます!
関関同立を目指す受験生は特に必見。過去問の点数が伸びず、焦りや落ち込みを感じている人へ。
本動画では、マナビズム講師が自身の経験をもとに、結果が出ないときに絶対にやってはいけない思考・やるべき行動を徹底解説しました。
感情と理屈の両面から、最後まで自分を信じて戦い抜く方法を語ります。
以下では、動画を見られない方に向けてテキストでも紹介します。
過去問演習の点数が取れないのはなぜ?

大学受験の過去問で思うように点数が取れない原因は、大別すると以下の5つです。
- ①「基礎の完成」が思っているより甘い
- ②「問題演習=過去問演習」と勘違いしている
- ③「分析」が浅い・曖昧になっている
- ④感情に流されて「戦略」がない
- ⑤過去問の「目的」がズレている
①「基礎の完成」が思っているより甘い
まず、圧倒的に多いのが「基礎の完成」が思っているより甘い状態です。
本人は「基礎は終わった」と思っていても、実は“使えるレベル”で定着していないのです。
- 英文法問題集は解けるけど、長文中では使えない
- 英単語は「見たらわかる」けど、文脈になると処理できない
- 数学の典型パターンはわかるけど、初見の形になると固まる
“インプット”は終わっているが、”運用力”が足りていないともいえます。
関関同立・MARCHレベルでは、英単語2000語を完璧にすれば6〜7割取れるのが一般的です。
しかし、受験生は実際には1200語程度しか身についていないケースがしばしばあります。
自分では「覚えた」と思っていても、実は復習不足で単語量が減っているわけです。
過去問は「知識を使いこなせるか」を問うステージ。
大学受験では基礎固めが完璧でないと、どれだけ演習を積んでも点数は取れません。
②「問題演習=過去問演習」と勘違いしている
大学受験の勉強で扱う過去問を「練習試合」だと勘違いしてはいませんか。
今日からは、どのような知識・技能を問われる大学なのかを”分析する場”だと考えてください。
「できなかった問題=次にやるべき課題」を抽出するために使えるからです。
解けたかより「なぜ間違えたか」を言語化しなければなりません。
受験生が「あ〜また60点だった…」で終わっていては、点数も取れないままです。
過去問の点数が取れない問題よりも、過去問から学ばない状態を改善しましょう。
分析で終える人だけが、着実に成績を伸ばしていけます。
関連記事: 大学受験の過去問は何年分解くべき?開始時期や使う目的、ポイント・注意点を解説
③「分析」が浅い・曖昧になっている
大学受験の過去問を分析しようとする姿勢は良いですが、”感想レベル”で止めてはなりません。
- 「単語が難しかった」
- 「時間が足りなかった」
- 「長文の内容が難解だった」
残念ながら、上記は分析ではなく感想です。
本来の過去問分析は、以下のように具体性を持たせます。
- 何の単語で詰まったのか(リスト化)
- どの設問形式で毎回落としているか(構造分析)
- 時間が足りない原因は文構造処理か、設問選択か(原因特定)
このレベルまで”言語化”できて、はじめて「過去問演習の価値」が出るからです。
解説を読んで満足しているだけでは意味がなく、次に解くときに意識する内容を言語化してメモしてください。
確かに分析には時間がかかりますが、その時間こそが点数アップへの投資になります。
④感情に流されて「戦略」がない
「過去問の点数が取れない」と落ち込むのは悪くありません。
ただし、その感情で手を止めるのはだめです。
- 点が悪い
- 焦る
- 同じ勉強を繰り返す
こうした「勉強量でカバーすればいい」と思い、方向を修正しないのは圧倒的に多い失敗パターンです。
結果、勉強はしているのに点数が上がらないという沼にハマります。
受験は「努力量」より「努力の方向」が重要です。
“頑張り方”を見直さないままの努力は、自己満足で終わります。
そして、具体的な単元・ページ数・学習時間を指定していないと、自分に言い訳しはじめるのは明白です。
曖昧な計画では、過去問で点数が取れない状態から抜け出せなくなるのです。
⑤過去問の「目的」がズレている
過去問を”点数の確認テスト”だと思っている人は、目的にズレが起きてしまっています。
でも本来の目的は、「合格点を取るために、今の自分に何が足りないかを把握する」という行動です。
合格点を超えるのが目的ではなく、合格点を超える準備を整えるための素材だと考えてください。
経験上、過去問で5割を切っている受験生は、大問ごとの時間配分や目標点を明確に決めていないケースがほとんどです。
過去問演習を通して「どう解けば点数が最大化できるのか」という解法を分析してください。
現役講師でも過去問演習で点数を取れなかった

マナビズムの講師である私でも、過去問の点数が取れない状態に陥った経験があります。
- 4月から勉強をはじめ、だれよりも量をこなした
- マナビズムの基準も満たし、勉強法も完璧に整っていた
それでも英語の過去問は、残念ながら200点中100点にも届きません。
周りには同じ高校で、もう合格点を超えてる子もいましたし、言い訳できる余地はありません。
そんな状況で、自らの能力を恨みました。
それでも、『救ってくれたのは”根拠のあるポジティブさ”』です。
「これだけやってるなら、いけるはずだ」という気持ちが折れなかったからこそ、最後まで走り抜けられたのです。
落ち込んでも点数は上がらない
繰り返しますが、「過去問の点数が取れない」と落ち込んでいても上がりません。
落ち込んでいる状態はまだ諦めきれていない、つまり心のなかにはまだ”火”があるはずです。
その火を絶やすか、燃やし直すかは自分次第。
落ち込むのは悪くありませんが、大切なのは、“そのあとどう動くか”です。
過去問演習で思うように点数が取れないときこそ、感情と理屈を切りわけてください。
少しでも不安を感じたなら、その気持ちをぜひマナビズムの講師に話してみませんか?
無料受験相談で、迷わず志望校への合格を目指せる計画を一緒に立てましょう。
過去問演習の点数を上げるためにやるべきこと
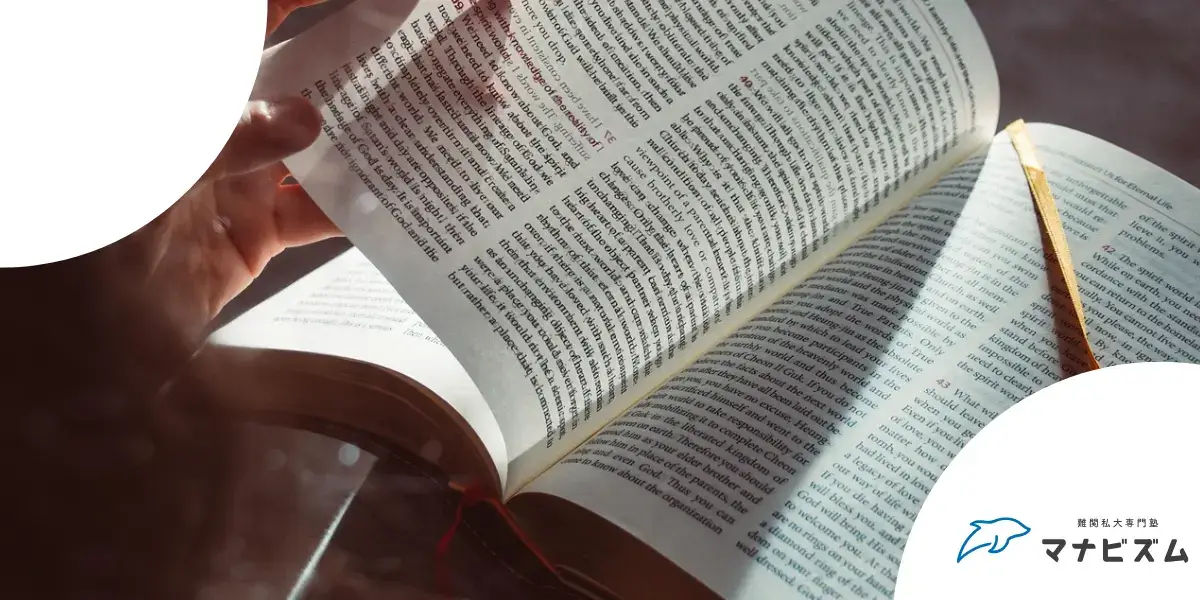
大学受験において、過去問の点数を上げたいなら、必要なのは「がむしゃらな努力」ではありません。
落ち込んだ気持ちを無理に打ち消すのでもなく、冷静に”原因を見抜く理性”を持つのが基本です。
具体的にやるべきことは、以下の5つです。
- 次は何をすべきかを考える
- 点が取れない原因を言語化する
- 分析ノートを作る
- 基礎に戻る勇気を持つ
- 長期の見通しを意識する
次は何をすべきかを考える
「過去問で点数が取れない」という気持ちを持ったあと、「次は何をすべきか」を必ず考えてください。
“感情で燃えて、理屈で動く”のが過去問の伸ばし方の第一歩です。
過去問で点が出なかったときに、落ち込むのは当然。それは「本気で挑んでいる証拠」です。
ただし大切なのは、その感情のままで終わらせないこと。
「夏までに●●大レベルで安定して点が取れるようになる」
こうした具体的な目標がなければ、進捗が遅れても「何がヤバいのか」すら分かりません。
目標から逆算して「次は何をすべきか」を明確にできれば、過去問演習の点数は着実に上がっていきます。
点が取れない原因を言語化する
過去問では、原因を具体的な言葉にすれば改善策も見えてきます。
点数が上がらない原因は、勉強量ではなく“分析不足”にあります。
受験生は「わからない」、「ミスった」で終わらせてしまうはずです。
しかし、そこを言語化できるかが勝負をわけるのです。
- 「単語はわかるのに文構造で詰まった」
- 「設問の主語との一致を見逃していた」
- 「時間配分が甘く、長文の最後を読めていない」
課題を説明できる人間は、すでに半分は突破しています。
分からない部分がピンポイントで定まっていれば、その分頭に入れる知識も少なくて済みます。
分析ノートを作る
点数が取れない原因を言語化するために、マナビズムでは「過去問分析ノート」を推奨しています。
目的は”ノートを作ること”ではありません。
「どれだけ自らの思考を言語化できているか」を調べるためのものです。
プリントでもデジタルでも構いませんので、解答根拠・弱点・改善策を自らの言葉で書いてください。
解説には結論しか書かれず、その解答に至るまでの流れが飛ばされやすいです。
この状況下では、過去問分析は時間がかかりますが、弱点がわかれば点数も着実に上がっていきます。
基礎に戻る勇気を持つ
過去問の点数が伸びないとき、「演習不足」だと思い込む受験生も少なからずいます。
このケースの場合、本当の原因は“基礎の抜け”です。
- 英語 → 文法・構文・語彙
- 数学 → 典型問題の解法プロセス
- 物理 → 公式の意味と条件
焦って応用に逃げず、こうした基礎に立ち返る勇気を持てる人が、最後に伸びます。
基礎固めは夏ごろを目安に終わらせ、秋以降に実践的な問題演習をして志望校・共通テスト対策の過去問に取り組んでください。
過去問で点数が取れないなら、まずは基礎の定着度を確認しましょう。
基礎に戻るのは「遅れ」ではなく、合格への最短ルートでもあるのです。
関連記事:浪人生も基礎からやり直すのが大切!科目別の勉強法やスケジュールを解説
長期の見通しを意識する
過去問演習では「今週で何を克服するのか」、「来月には何割取るのか」を明確にしてください。
部活に例えてみましょう。
- “とりあえず走っとけ”
- “グラウンド3周”
どちらが頑張りやすいでしょうか。
おそらく、ほとんどの受験生がラスト1周で頑張れる後者のはずです。
あまり経験はないかもしれませんが、人は”見通し”が見えると頑張れる生き物です。
逆に、先が見えないと不安と焦りで崩れるのはいうまでもありません。
このゴールを明確にして走り切る姿勢が、点数アップへの最短ルートです。
大学受験の年間計画では、目標を時期ごとに区切って設定し、受験当日から逆算して立てていくのが理想です。
過去問演習でも同様に、「いつまでに何点取るか」を設定し、そこから逆算して今やるべき内容を決めましょう。
関連記事:【脱失敗】大学受験の計画の立て方は?受験生に求められる修正力とは
過去問演習の点数から合格を掴む分析と戦略が重要
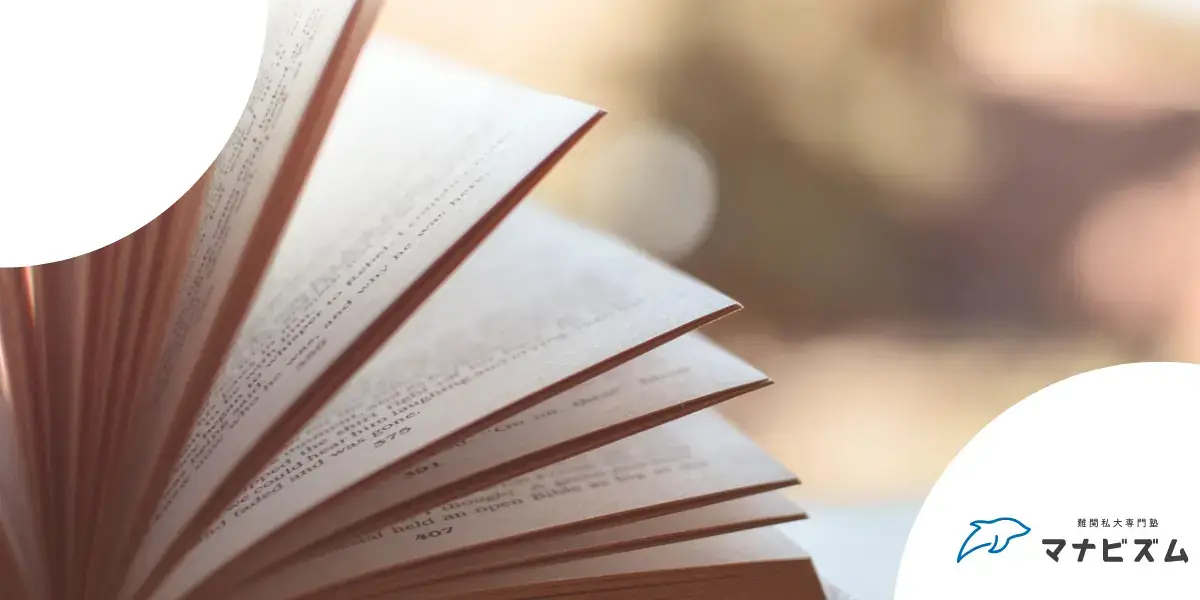
過去問の点数が取れないとき、”頑張ろう”という気持ちだけでは点数は上がりません。
点数が上がらないなら、合格できないというのは事実です。
もちろん、「感情」は努力の燃料になりますが、「戦略」がなければ前に進めません。
- どの勉強・どの手を打つのが最短距離なのか
- どの範囲を重点的に復習するか
- どの設問形式で点を落としているか
- どの順番で解けば時間配分が安定するか
それぞれを分析し、最適化しましょう。
「分析・修正・再挑戦」のサイクルを1周回すたびに、着実に合格に近づきます。
マナビズムでは、1人ひとりに専属の「自習コンサルタント」がつきます。
過去問の分析から次にやるべき勉強計画まで、オーダーメイドで設計するからです。
「何をどう勉強すればいいか」一切悩みませんので、志望校への合格に歩みを進められる環境です。
過去問演習で点数が取れないと悩んでいるなら、ぜひマナビズムの無料受験相談をご利用ください!
まとめ:今の点数で未来を不合格に書き換えないこと
大学受験の過去問で点数が取れないとき、落ち込んだとしても手を止めないでください。
合格の鍵は、才能ではなく”合格を信じ続け、努力する継続力”です。
感情に振り回されず、理屈で前を見て丁寧に積み重ねていけば、結果は必ずついてきます。
そしてその過程こそが、合格以上の価値を持ちます。
落ち込んでる暇はありません。泣いても笑っても、試験の日はいずれ来ます。
今の点数で未来を”不合格”に書き換えず、今からでも合格に向けて歩みを進めましょう!
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————