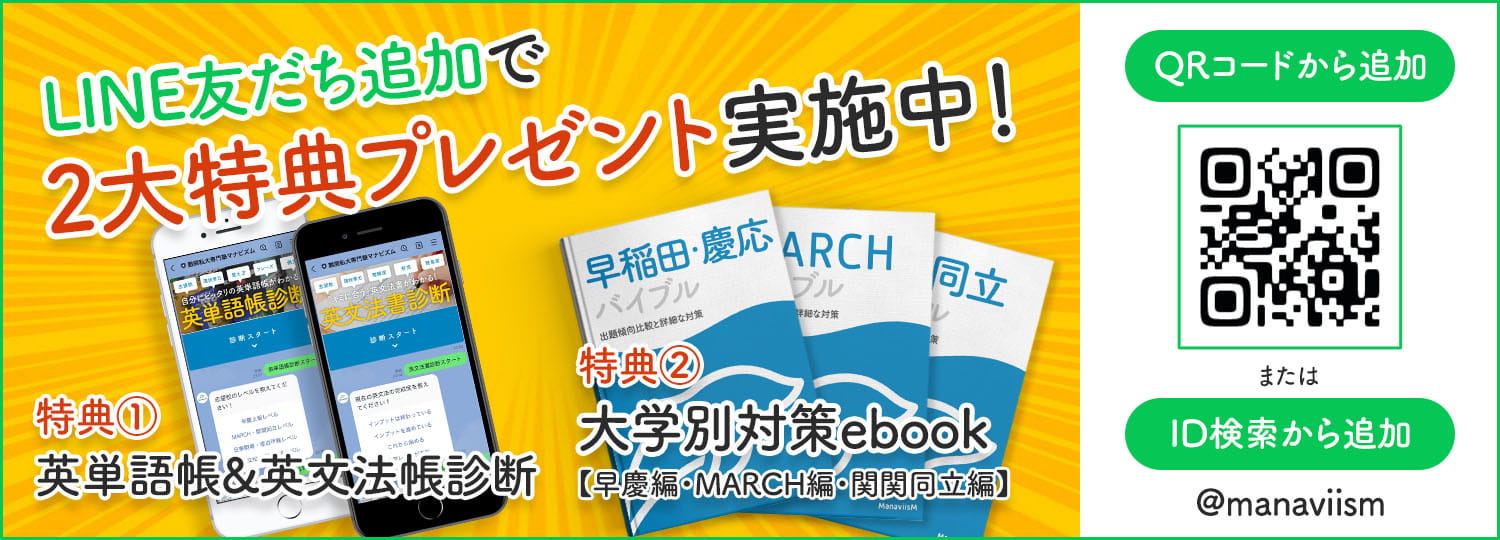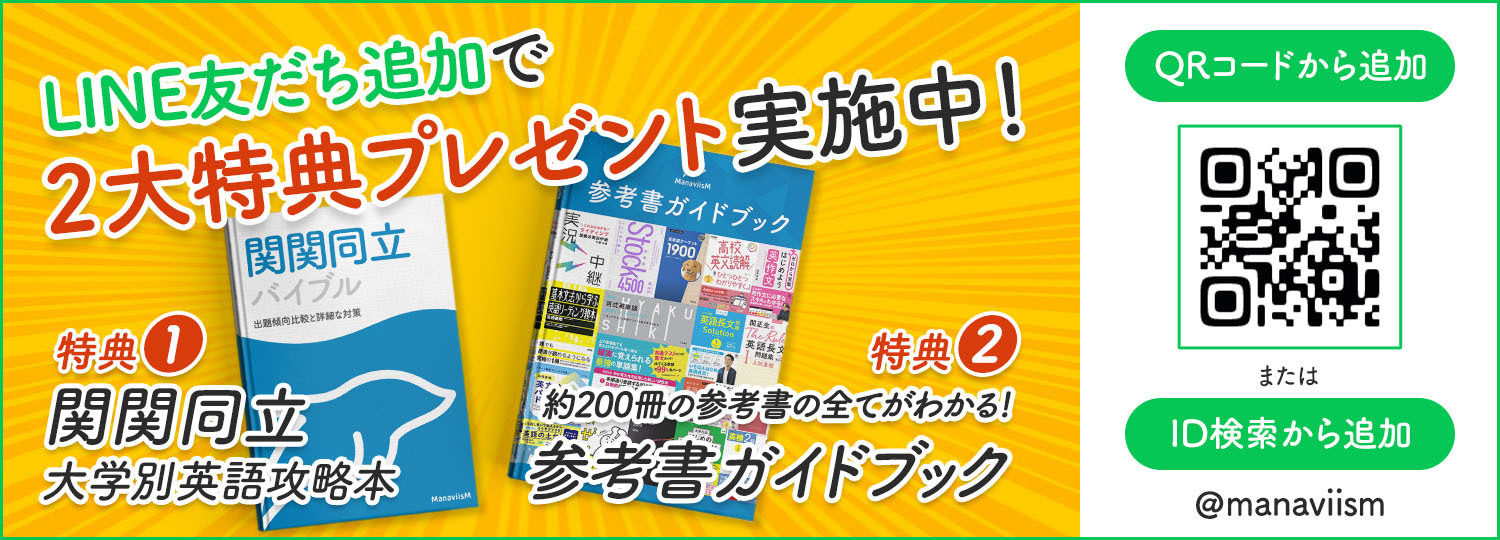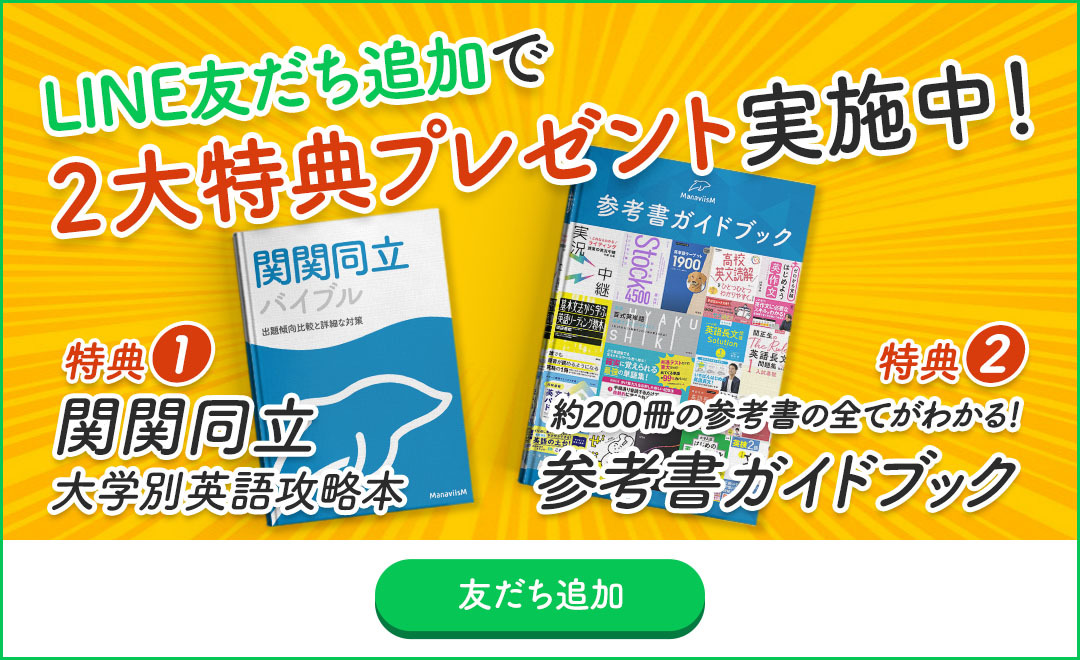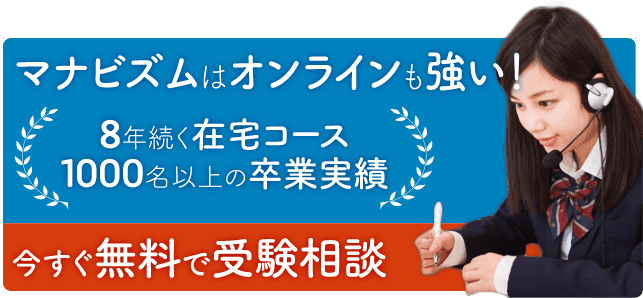【大学受験】成績が伸びない・結果が出ないのはなぜ?点数が伸びる勉強方法
更新日: (公開日: ) COLUMN
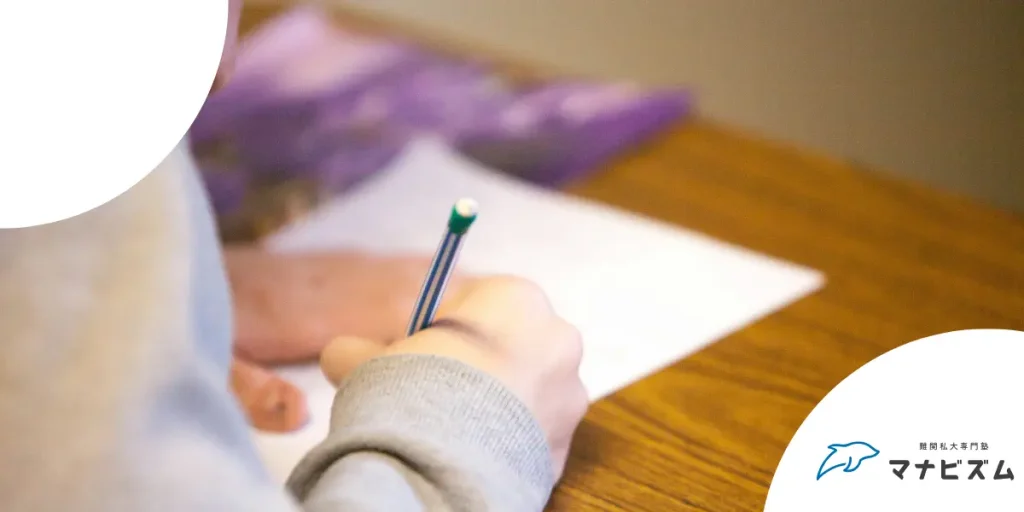
この時期、「勉強してるのに点数が伸びない」と思ってる受験生、多いと思います。
過去問や演習をこなしてるのに、成績が止まったまま……という状況ですね。
今回は、そんな受験生に向けて、「今やるべきこと」を具体的に話します。
テーマはズバリ、「点数が伸びる勉強法」です。
頑張っているのに結果が出ない原因を見つけて、今日から正しい勉強に切り替えていきましょう。
YouTubeでもご覧いただけます!
秋の受験後半、点数が伸び悩む受験生へ。
英語や古文の演習後に何をすべきか?
今井先生と川本先生が、復習分析・守りの勉強・単語運用・演習の質を徹底解説します。
やってるのに伸びない人ほど必見の、本質的な勉強法の講義です。
以下では動画を閲覧できない方に向けて、テキストでも紹介します。
成績が伸びない・結果が出ないのはなぜ?
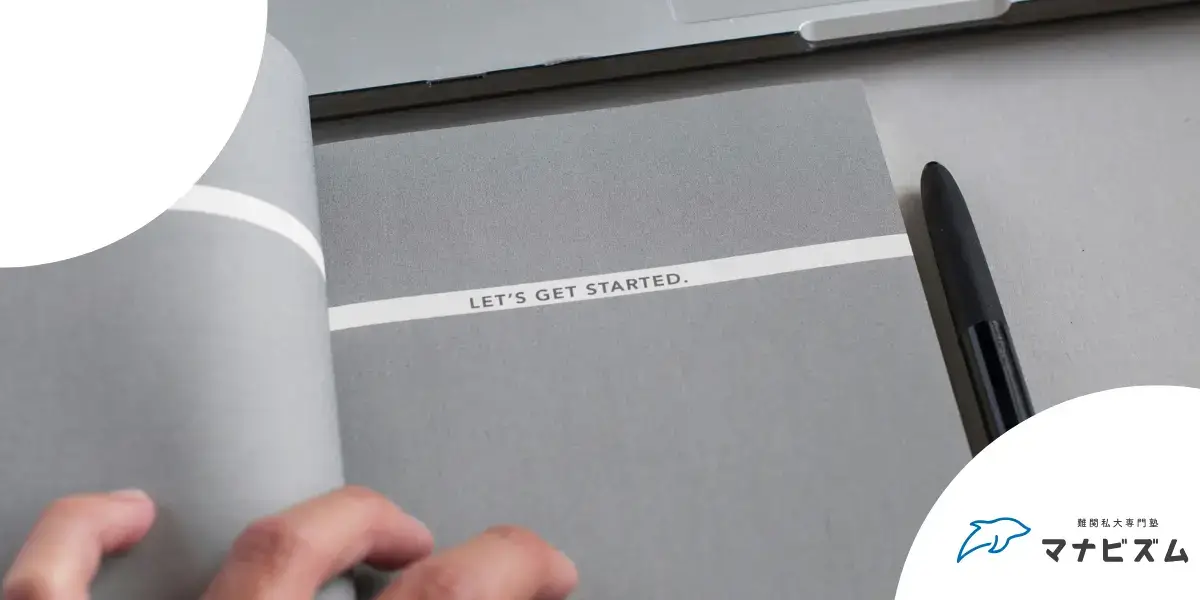
主に、成績が伸びない・結果が出ない理由は以下の3つに集約されます。
- 過去問分析の質が甘い
- 目的意識のない勉強になっている
- 勉強量が減少している
ほかにも理由はありますが、ここに当てはまるなら現状の見直しが必要です。
過去問演習をする際にもっとも大切なのは、「なぜその問題ができなかったのか」を明確に分析することです。
しかし、受験生がこの分析を甘くしてしまっています。
例えば、英語の問題で間違えたときに、文法・単語のどっちが原因なのかをはっきりさせずに進んでしまう。
そうすると、同じミスを繰り返してしまいます。
関連記事:【高校生向け】勉強してるのに成績・学力が上がらないのはなぜ?
成績が伸びる子の特徴は?
主に、大学受験で成績が伸びる子の特徴としては、以下があります。
- 教科書を読むだけで満足しない
- 基礎レベルの問題が完璧に解ける
- 間違えた問題をそのまま放置しない
- 自らのレベルに合う参考書を使っている
- 年間の学習計画が立てられる
- スマホが目に入らない環境で勉強している
- どの分野が弱点なのか把握できている
ただ、実際にこの状態になろうと思えば、相応の「努力」が必要です。
例えばスマホを手放せないなら、難関私大レベルの合格は本当に難しいと考えてください。
時間が無作為に奪われていくだけになってしまいます。
では、何をすれば良いのか。次は、実際の勉強法を紹介します。
今この時期に点数を伸ばすために必要な2つのこと
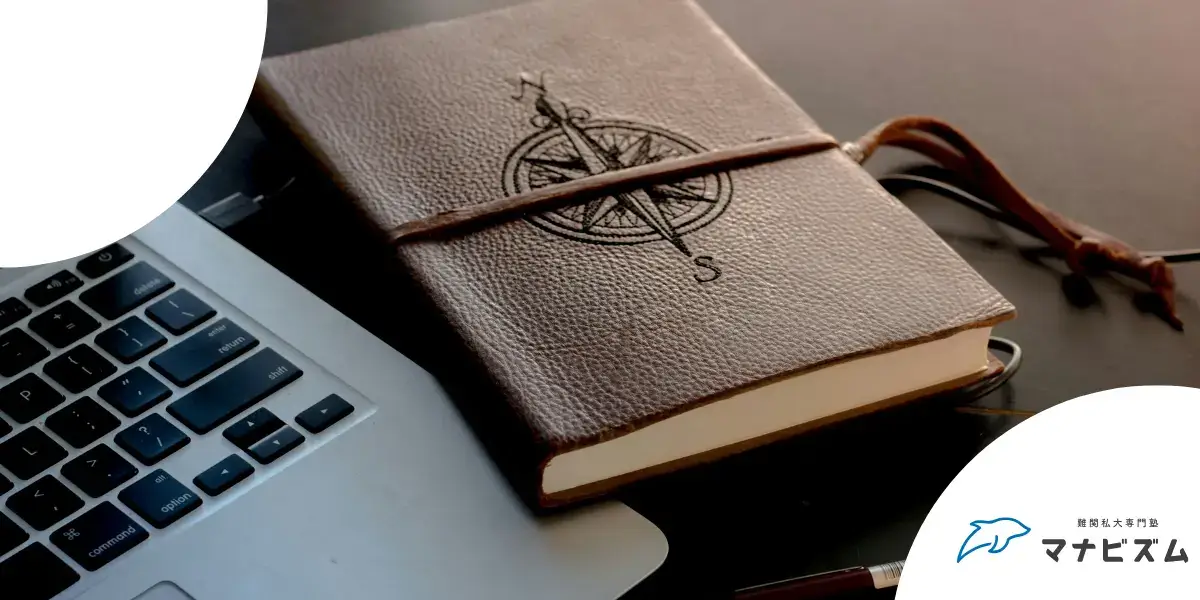
大学受験で成績が伸びないなら、やるべきことは以下の2つです。
- 演習後の分析を手抜かない
- 守りの勉強をしっかりやる
どちらも必須で、意外とみんなサボりやすい部分です。
ただ、この2つを徹底するだけで点数は着実に変わってきます。
演習後の分析を手抜かない
大学受験の勉強で自らの弱点を見つけるためには、「初期にやってきた丁寧な復習」が肝要です。
例えば私の場合、分析してて気づいたのが、「代名詞や指示語が何を指してるか」を意識してなかったことでした。
これをきちんと明確にしていかないと、文章全体がごちゃごちゃになります。
時間が経つほど、さらにいい加減な状態になります。
今、もう一度やってください。
過去問を解いた後に、なぜその答えになるのかを説明できるまで復習するのです。
守りの勉強をしっかりやる
大学受験において守りの勉強は、アウトプット(演習)→インプット(復習)の繰り返しです。
「基礎はもう大丈夫」と思った瞬間から崩れていきます。
人は1日経つと学んだ内容の半分を忘れてしまうため、守りの勉強は”やって当然”の領域です。
間違えた箇所を放置せず、その日のうちに回収する。これが守りの本質です。
やらない人に限って、「合格点取れてるしまあいいか」と油断します。
最終的に、足をすくわれる原因になります。
単語や文法など、基礎的な知識は短い周期(例えば1週間に1回など)で何度も見直してください。
すぐ実践!大学受験生の点数が伸びる勉強方法

ここからは、”今こうすれば点数が伸びる”というテーマで、具体的な勉強法・問題の解き方・分析・復習の仕方まで、がっつり話します。
今回の勉強方法のポイントは、以下の5つです。
- 初期の勉強法に立ち返る
- 演習後の復習で精度を高める
- 復習では根本を深く考える
- 見直しを段落単位ではなく”一文単位”にする
初期の勉強法に立ち返る
大学受験の受験勉強で成績が伸びないキミは、初期に立ち戻ってください。
最初に伝えたように、「自らの弱点を探す習慣」が消えていくからです。
思い出してほしいのが、受験初期に演習したあとに丁寧に復習してた経験です。
私も英語なら、SVOC(主語・動詞・目的語・補語の)を全部振って、だれが何をしてるかをチェックしてました。
数学なら、わからない問題をすぐチャートとか基礎精講に戻って確認していたほどです。
最初のころは、演習=インプットの延長だったのが、解説や全訳を”見るだけ”で終わってしまう。
この基礎知識の定着が不十分だと、どれだけ応用問題に取り組んでも成果が出にくくなります。
今一度、初心に戻って丁寧な復習を心がけてください。
演習後の復習で精度を高める
演習後の分析は、”復習の精度”をどこまで上げられるかにかかっています。
例えば古文の復習では、全文・原文と訳を見比べるのが絶対条件です。
本文の横に全訳を置いて、自らの訳と照らし合わせるといった丁寧さを持ってください。
ポイントは、一文単位で構造を意識して見てみることです。
文を読む動作に必死になって、“単語”とか”文法”のレベルを軽視してしまう人が多いです。
しかし、文章って結局その小さい要素の積み上げです。
単に問題を解き直すだけでなく、深い分析と具体的な改善策の立案を行います。
そうすると、同じ間違いを繰り返さず、着実に実力を伸ばせます。
ミクロなレベルまで見直すのは、成績が伸びないときこそ必須です。
関連記事:【高校生必見】塾で成績が上がらないたった3つの原因と対策
復習では根本を深く考える
“表面的に復習してるけど、深く考えられてない”のが、成績、そして点が伸びない原因です。
大学受験の勉強で演習を重ねると、人ってだんだん雑に復習します。
「もうわかってるからいいや」とか「解説見たら理解した気になる」とか。
手は動かしてても、考えが浅くなってるのです。
私たちも受験生の頃、構造振ってなんとなく訳してたけど、”なぜその構造でその訳になるのか”までは全然考えきれてませんでした。
解答の根拠を明確にし、人に説明できるようにしてください。いつまでたっても6割止まりになります。
例えば四択問題で正解したとしても、「なぜほかの選択肢が間違いなのか」まで説明できるようになってはじめて、本当の理解といえます。
見直しを段落単位ではなく”一文単位”にする
成績が伸びないなら、受験勉強の見直しをとにかく細かくするのが大切です。
英語の長文・古文のどちらでも、段落でざっくり振り返るだけじゃ意味がないからです。
一文ごとに、どこで訳せなかったかを確認してください。
単語1つの意味を深掘りするだけでも、理解は圧倒的に変わります。
例えば古文の「よ」は、「世の中」、「男女の仲」、「世間」など色んな意味があります。
なぜその文脈では”男女の仲”になるの?というレベルまで考えてはじめて実力になるのです。
細かく見れば見るほど、自らの弱点が見えてきます。
実際の大学受験で、次に同じ問題が出たときに着実に解ける実力へ変わるわけです。
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————
成績が伸びないときは勉強量×精度で差をつける
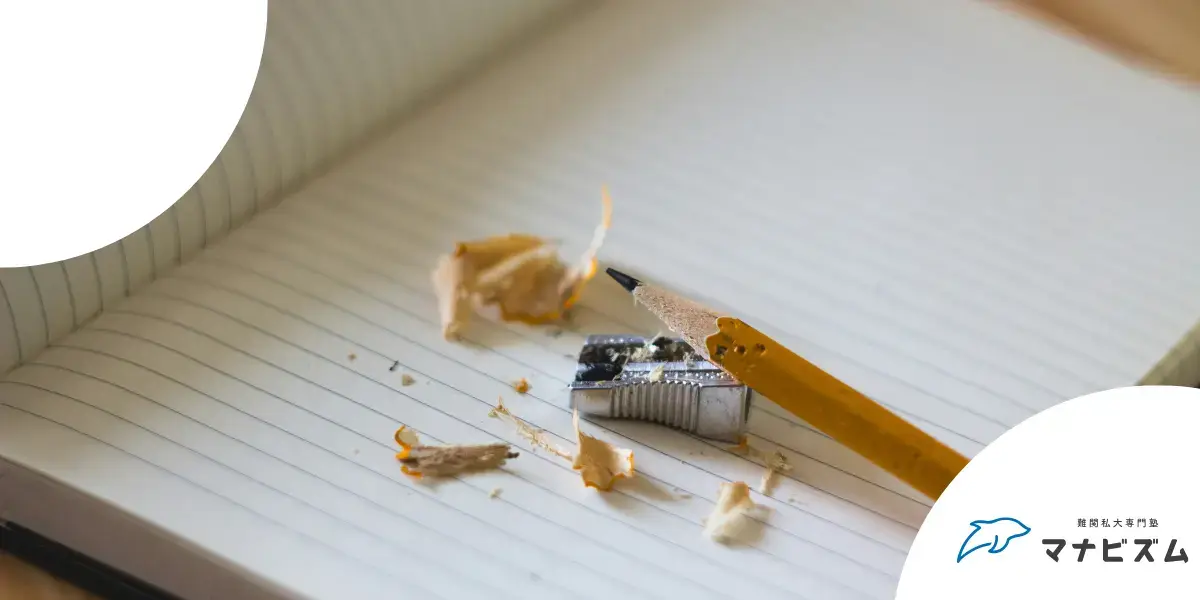
成績が伸びない・結果が出ないのであれば、”勉強してください”。
「頭いい人はあんま勉強しなくていいんでしょ?」と思ってる人、間違いです。
処理能力に差はあるけど、どのような人でも勉強しないとできません。
頭がいい人でも、大学受験に向けて勉強しなければ落ちます。
「能力が違うから」ではなく、”勉強量と精度”の差で結果が変わると考えてください。
テクニックは、全部”土台”の上にあります。
根本的に勉強量が足りてない人は、まずそこからです。
質を高めれば量は自然に増える
受験勉強で1問1問をしっかり分析しはじめると、1日6時間じゃ足りなくなります。
質を高めれば量は勝手に増えるわけです。目安をいうと、以下のとおりです。
- 6〜8時間
- 10時間
- 約70時間
これが”普通”です。「やることがない」は存在しません。
復習を深くすれば、さらに時間が足りなくなるはず。
もし時間が余っているなら、それは復習の質が浅い証拠です。
「志望校を下げようかな…」と考えているかもしれません。
しかし、ギリギリまで学力は伸びるので、志望校を下げないほうが良い結果につながりやすいです。
最後まで諦めずに勉強量と質の両方を追求してください。
関連記事:決定時期はいつ?大学志望校の決め方は5つのポイントで判断
まとめ:結果を出すなら辛いと感じた今から見直す
今日の話をまとめると、点数が伸びない理由は、「演習後の分析不足」と「守りの勉強不足」です。
復習をミクロレベルまで掘り下げて、基礎を落とさない。
それを続けるだけで、点数は必ず上がります。
逃げずに、細かく、やり切る。それだけで周りと差がつきます。
気持ちは分かりますが、焦る前に”復習の質”を見直してください。
分析して、守って、積み重ねる。これが、点数を伸ばす一番確実な方法です。
- 「自分一人では不安」
- 「正しい勉強法がわからない」
と感じたら、マナビズムの無料受験相談を利用してください。
プロの自習コンサルタントが状況を分析して、志望校合格までの最短ルートを示します。
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————
よくある質問(FAQ)
大学受験生が1番伸びる時期はいつですか?
大学受験生はギリギリまで伸びるので、チャレンジ校に受かる可能性は大いにあります。一般的に、受験生がもっとも成績が伸びる時期は、高3の夏休み以降から入試直前までです。特に入試直前の冬休みは、追い込みの時期で集中して大量のアウトプットをこなせるため、成績の伸びがもっとも速くなります。
勉強しても成績が上がらないのは病気ですか?
勉強しても成績が上がらないのは、ほとんどの場合、病気ではありません。分析が甘い、目的意識の欠如、勉強量の減少などの勉強方法に原因があることが大半です。まずは復習の質を高める、基礎を徹底するなど、この記事で紹介した方法を試してください。
大学受験生は1日何時間勉強していますか?
高校1〜3年生までの平均勉強時間は、平日約1.5時間・休日2.0時間というデータがありますが、これは全体の平均です。難関私大を目指す受験生は、もっと時間を勉強に費やしています。マナビズムでは、合格を目指す受験生の目安として、平日6〜8時間、土日10時間以上、週合計約70時間を推奨しています。