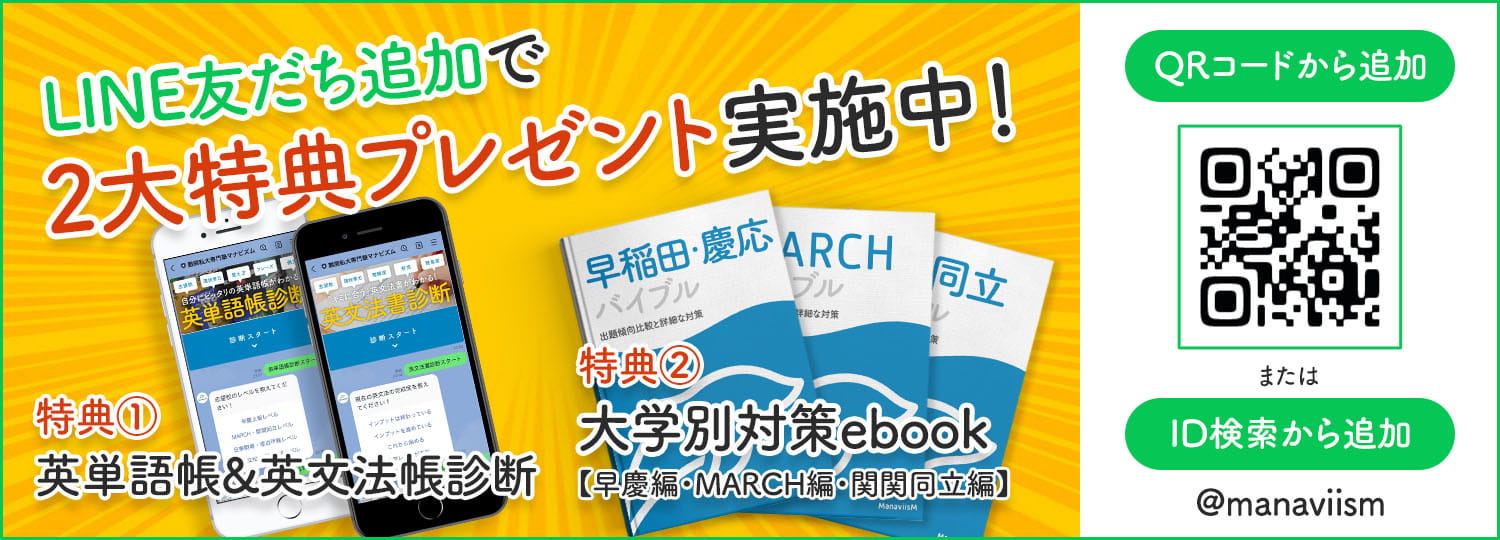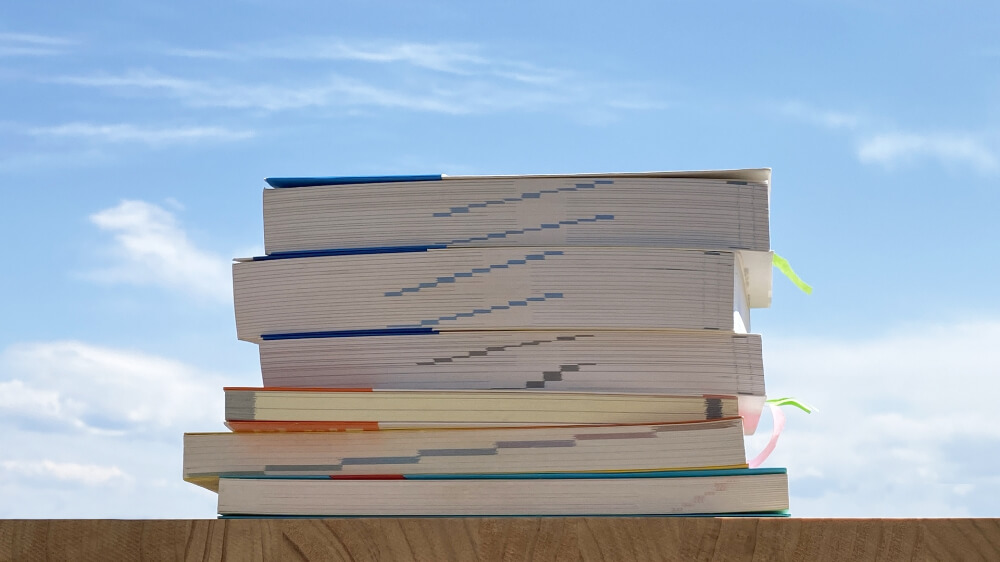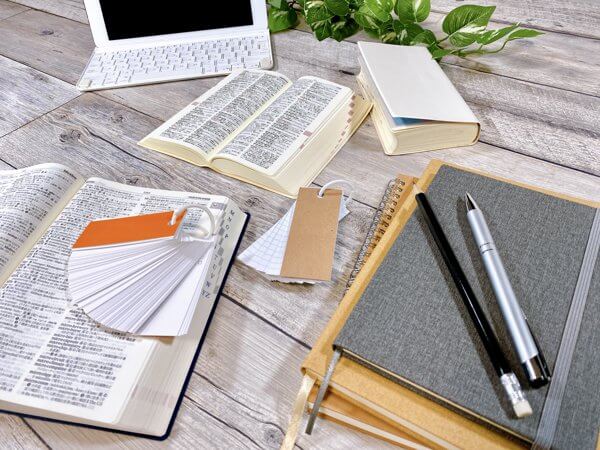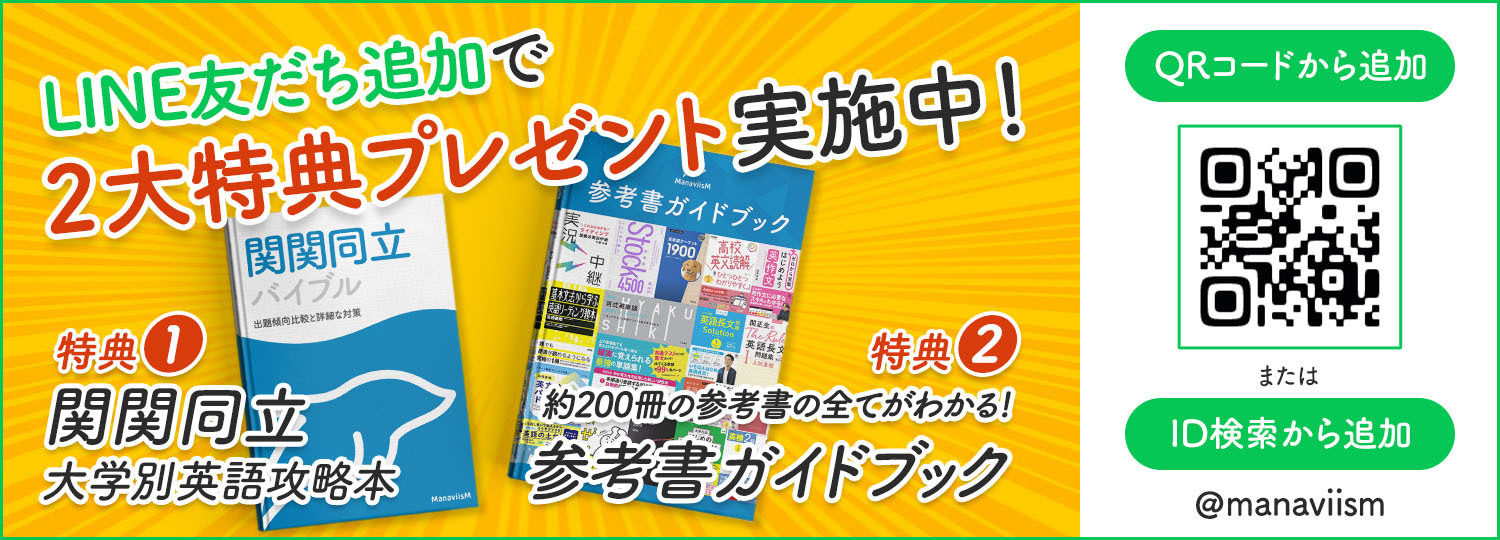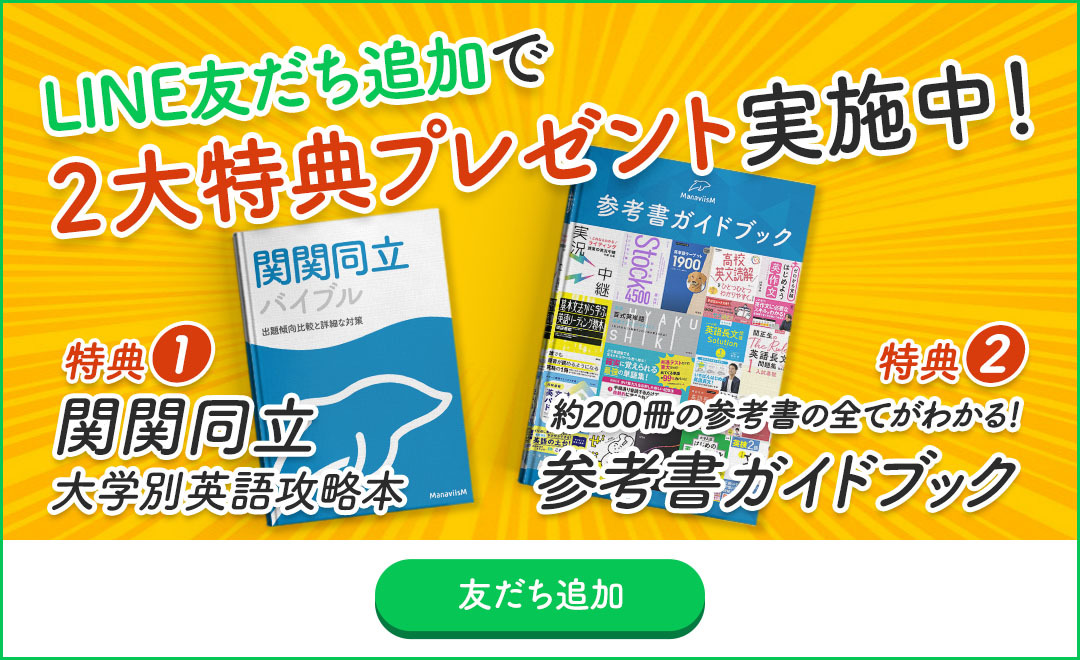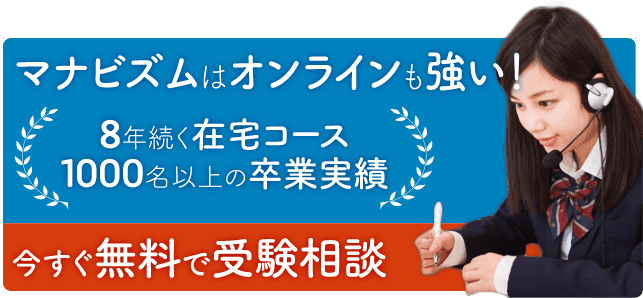【脱失敗】大学受験の計画の立て方は?受験生に求められる修正力とは
更新日: (公開日: ) COLUMN

キミは”勉強してるつもり”になっていませんか?
部活が忙しい、文化祭がある、勉強する時間がない──。それは、落ちる人のセリフです。
ここで大切なのは、「うまくやるか」じゃなく、「受かる」と決めることです。「時間がないなかで、どうすれば最大効率を出せるか?」考え出した瞬間、キミは”落ちる人”から”受かる人”に変わります。
そのためにも、本記事では大学受験の計画の立て方と、成功するための修正力について解説します。
この記事は、現役生向けの内容です。浪人生の方は以下の記事もご覧ください。
関連記事:浪人生にも大切な学習計画|手順やスケジュール例・成功するコツを解説
大学受験の計画が失敗する7つの理由
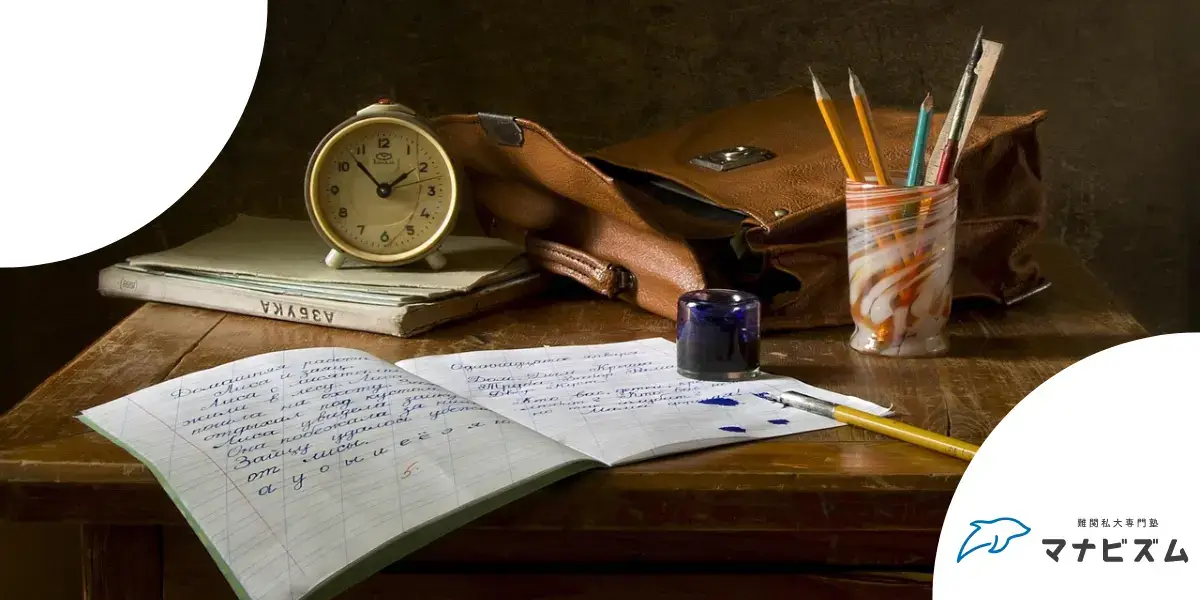
大学受験の勉強計画を立てても、うまくいかないのは主に以下の理由があります。
- 目標設定が曖昧だから
- 計画が具体的でないから
- 無理な計画を立ててしまうから
- 生活リズムを無視しているから
- 計画を修正する習慣がないから
- 科目間のバランスが悪いから
- 復習の時間を確保していないから
目標設定が曖昧だから
まず、「志望校に合格する」という目標だけでは、何をどこまでやればいいのかわからず、計画も立てにくくなります。
ここでの目標設定は、「英語の成績を上げる」「数学ができるようになる」といった漠然としたものではありません。例えば「12月までに英語で8割以上を取る」など、具体的な目標設定が大切です。
計画が具体的でないから
「今週は数学に力を入れよう」「この参考書を終わらせよう」といった曖昧な計画では失敗する確率が高いです。具体的な単元・ページ数・学習時間を指定していないと、自分に言い訳しはじめるのは明白です。
例えば、「英語を頑張る」「数学の問題集を進める」であれば、1文字覚えてもゴールになってしまいます。これでは計画として機能しません。
無理な計画を立ててしまうから
「毎日10時間勉強する」「4時間しか睡眠をとらない」といった計画は、本当に達成できるでしょうか?
計画が達成できないと、やる気が出なくなるのは大人でも同じです。睡眠時間を削る、休憩時間がない、毎日同じ時間勉強するという前提には、無理があります。無理な計画が短期間だけ続いても、長期的には必ずスランプが来ます。
生活リズムを無視しているから
朝型・夜型など自らの生活リズムを無視した計画では、集中力が発揮できません。自らの生体リズムに逆らった計画は、無駄な努力を強いることになります。
- 朝型の人は早朝に難しい科目を学ぶ
- 夜型の人は夕方以降に集中的に勉強する
- 集中力が続かない人は科目をこまめに切り替える
など、自らの特性に合わせた計画が必要です。これができないと、計画は続きません。
計画を修正する習慣がないから
ほかにも、最初に立てた計画をそのまま続けようとして挫折するケースも代表例です。「計画は随時修正するもの」という意識が不足していると、ストレスがたまり挫折しやすくなります。
- 模試の結果が出たとき
- 体調を崩したとき
- 学校が忙しくなったとき
- 苦手分野が見つかったとき
こうしたタイミングで計画修正の習慣がないと、計画と現実のギャップが広がり、やる気の低下につながります。
科目間のバランスが悪いから
得意科目ばかりを勉強したり、苦手科目に時間をかけすぎたりすると、全体のバランスが崩れます。英語だけに集中してほかの科目を疎かにする、苦手科目に全時間を費やして得意科目が伸び悩むといった状況はNGです。
一科目だけ極めて他は中途半端になると、結果として総合力を重視するような大学への合格が難しくなります。
復習の時間を確保していないから
受験生は、新しい内容の学習ばかりに時間を使ってしまっているはずです。ただ、本当に重要なのは復習の時間です。エビングハウスの忘却曲線が示すように、だれでも学習した内容は24時間後に約70%が忘れます。
復習をしないまま新しい内容を学び続けると、知識は「穴のあいたバケツの水」のように流れ落ちてしまいます。
キミの勉強計画は本当に大丈夫ですか?マナビズムでは1人ひとりに合わせた最適な勉強計画をご提案しています。無料相談も実施中ですので、講師にすぐ相談してください!
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————
大学受験の計画は『羅列』で立てないこと
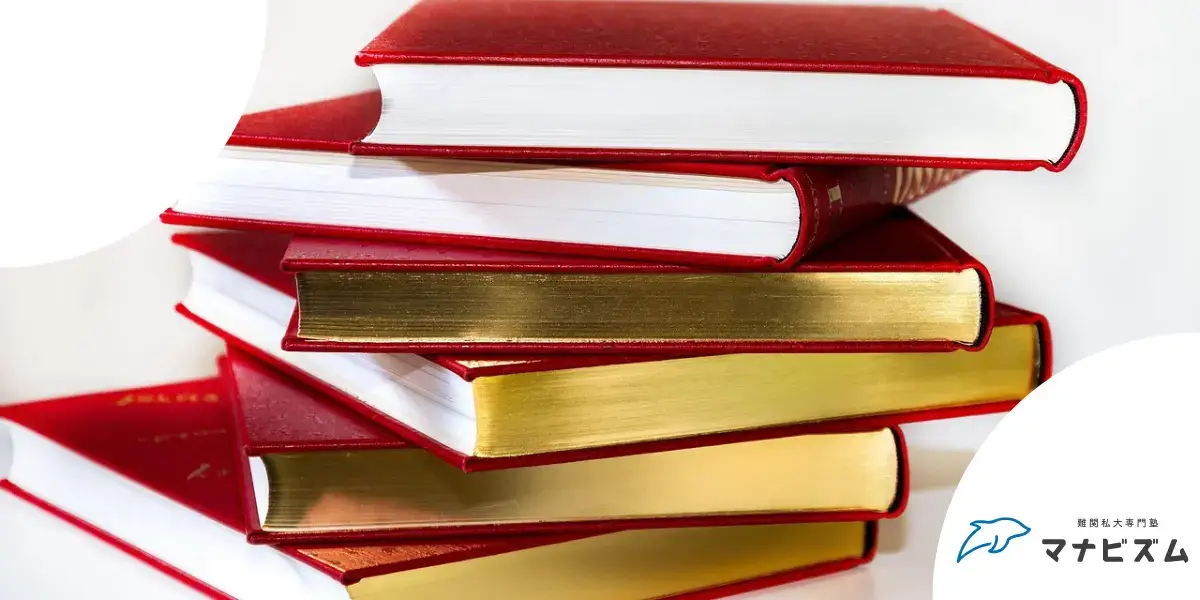
大学受験で設計する勉強計画というのは、単なる羅列ではありません。「この参考書から順番にやっていけば、いつか合格できるだろう」──。そう思っているはずです。
しかし、それは計画ではなく、”並べただけのリスト”を上からやっているだけです。
真の計画とは、
“今の自らの学力” “目指す大学の合格最低点”
というギャップを、『どう埋めていくか』です。数字と期間で逆算して、必要な力を定義してはじめて”計画”と呼べるものになります。
- 今の英語の偏差値が45で、志望校の合格者平均が60だとしたら、その差の15をどのように埋めていくのか。
- 単語力なのか、文法力なのか、読解力なのか。
- それぞれをいつまでに、どのレベルまで引き上げるのか。
こうした具体的な道筋を描くことが、計画立案の本質です。
参考書を羅列するだけでは、自らの弱点を克服できているのか、志望校の要求レベルに近づいているのかが見えません。目標から逆算した具体的な計画を立てることが大切ですので、次の立て方をぜひチェックしてください。
大学受験に受かるための勉強計画の立て方
【動画でもご覧いただけます!】
大学受験に合格するための勉強計画は、以下のステップで立てていきます。
- ゴールを決める
- 年間計画を立てる
- 週単位・月単位でタスクを設定する
なお以下では、勉強効率を上げる計画を作成する方法に触れているので、ここで紹介する内容とあわせて参考にしてください。
ゴールを決める
まず、目標大学にいつ、どの科目で、何点取るのかを先に決めてください。合格最低点を基準に、いつまでにどのレベルに到達すべきかを明確にしましょう。
- 「夏までに●●大レベルで安定して点が取れるようになる」
- 「12月末までにマーチで合格最低点が出せるようにする」
このような具体的な目標がなければ、進捗が遅れても「何がヤバいのか」すら分かりません。ただ漠然と焦るだけです。
志望校の過去問や模試の結果を分析し、各科目で必要な得点率を把握しましょう。例えば「英語は7割以上、数学は6割以上」といった具体的な数値目標を設定できれば、計画の指針が明確になります。
年間計画を立てる
次に、大学受験の年間計画では、目標を時期ごとに区切って設定します。例えば、夏には「日駒・産近甲龍」レベル、年内には「マーチ・関関同立」で合格最低点が取れる状態を目指すといった具合です。
各時期の目標点数を明確にし、”理想の点数推移”をもとに、「逆算」で参考書や演習を当てはめていきます。受験当日から逆算し、立てていくことができるのが理想です。
計画作成は「次にこれをやろう、次にこれをやろう」といった順番で決めていくのは本当にNGです。絶対に計画作成は、うしろからするようにしましょう。
【関連記事】
週単位・月単位でタスクを設定する
先ほど決めた大学受験の年間計画をベースに、週単位・月単位でタスクを設定します。
まず「週に何時間勉強できるか」を割り出しましょう。そのうえで、各科目に何時間かけるかを配分し、それに沿った学習内容を当てはめていきます。
例えば、平日は部活があるとしても1日2時間、土日は各8時間勉強できるとして、週40時間の勉強時間が確保できます。もし、英語に40%の時間を割り当てれば、16時間も使えます。
「単語を1時間やったらほかのことができない」というのではなく、「やっていないだけ」です。各科目内での細分化(例:英語16時間中、単語1時間/日など)で計画を立ててください。
以下では、文系と理系にわけて計画の例を紹介します。
文系
例えば、文系なら『英語:数学:現代文:国語=4:4:1:1』の比率で時間配分します。文系の勉強計画例(週40時間)では、以下のとおりです。
| 科目 |
時間(週) |
主な学習内容例(目安時間) |
|---|---|---|
| 英語 | 16時間 | – 単語帳:1時間×5日 = 5時間 – 長文読解:1.5時間×4日 = 6時間 – 英文法:1時間×3日 = 3時間 – リスニング:30分×4日 = 2時間 |
| 数学 | 16時間 | – 基礎問題演習:1.5時間×4日 = 6時間 – 標準問題演習:2時間×3日 = 6時間 – 苦手分野の復習:1時間×4日 = 4時間 |
| 現代文 | 4時間 | – 評論読解:1.5時間×2日 = 3時間 – 漢字/語彙:30分×2日 = 1時間 |
| 古文 | 4時間 | – 単語:30分×4日 = 2時間 – 文法:30分×2日 = 1時間 – 読解:1時間×1日 = 1時間 |
理系
次に、理系なら『英語:数学:理科=4:4:2』の比率で時間配分します。理系の勉強計画例(週40時間)では、以下のとおりです。
| 科目 |
時間(週) |
主な学習内容例(目安時間) |
|---|---|---|
| 英語 | 16時間 | – 単語帳:1時間×5日 = 5時間 – 長文読解:1.5時間×4日 = 6時間 – 英文法:1時間×3日 = 3時間 – リスニング:30分×4日 = 2時間 |
| 数学 | 16時間 | – 基礎問題演習:1.5時間×4日 = 6時間 – 標準問題演習:2時間×3日 = 6時間 – 応用問題・過去問:1時間×4日 = 4時間 |
| 理科 | 8時間 | ※物理・化学を想定(各4時間) 物理: – 教科書・基礎理解:1時間×2日 = 2時間 – 問題演習:1時間×2日 = 2時間 化学: – 教科書・暗記:1時間×2日 = 2時間 – 演習:1時間×2日 = 2時間 |
【学年別】大学受験に受かるための勉強計画の立て方
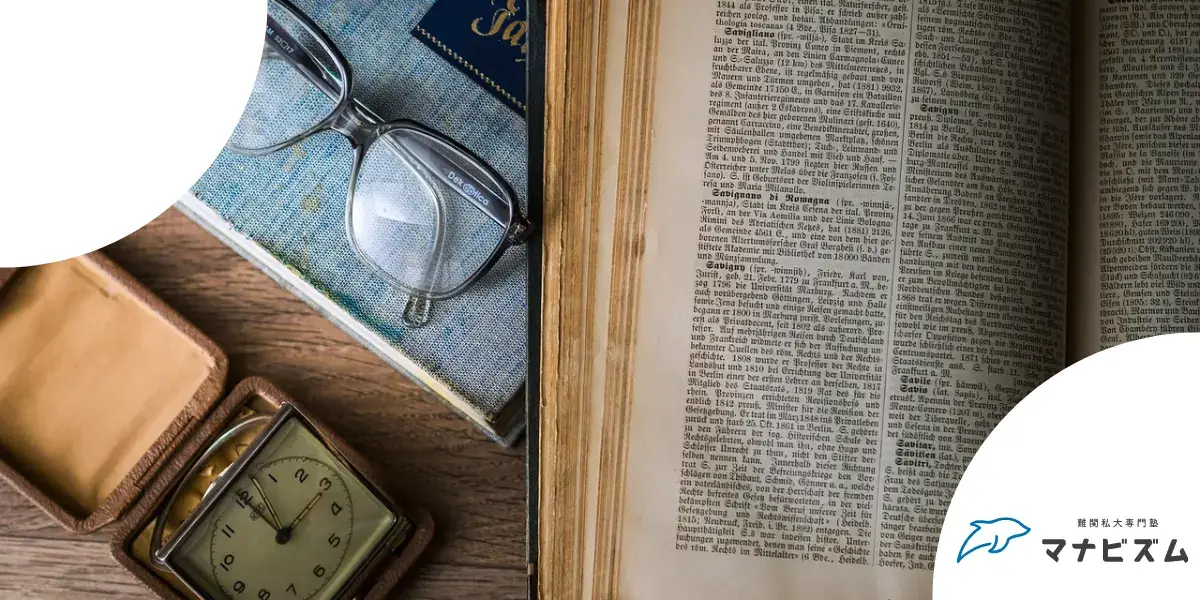
学年によっても、大学受験の計画の立て方は異なります。
- 「高1は”基礎+習慣”を武器に、英数を先取り」
- 「高2は”基礎の完成”と”志望校決定”が勝負をわける」
- 「高3春に基礎固め、夏に実戦、秋から過去問」
ロードマップとしても使えますが、キミが本気で志望校への合格を目指すなら、詳しくは以下の記事をご覧ください。スケジュールをどうしたら良いのかが見えてくるはずです!
【関連記事】
- 高1なら:難関大学の合格には高1からの勉強が大切!スケジュール管理術や勉強法を解説
- 高2なら:高2の受験勉強スケジュール|時期別に大切なポイントや年間・1日の計画について解説
- 高3なら:高3から大学受験勉強は遅い?合格に間に合うためのスケジュールや勉強法を解説
大学受験で計画に盛り込む参考書選びのポイント
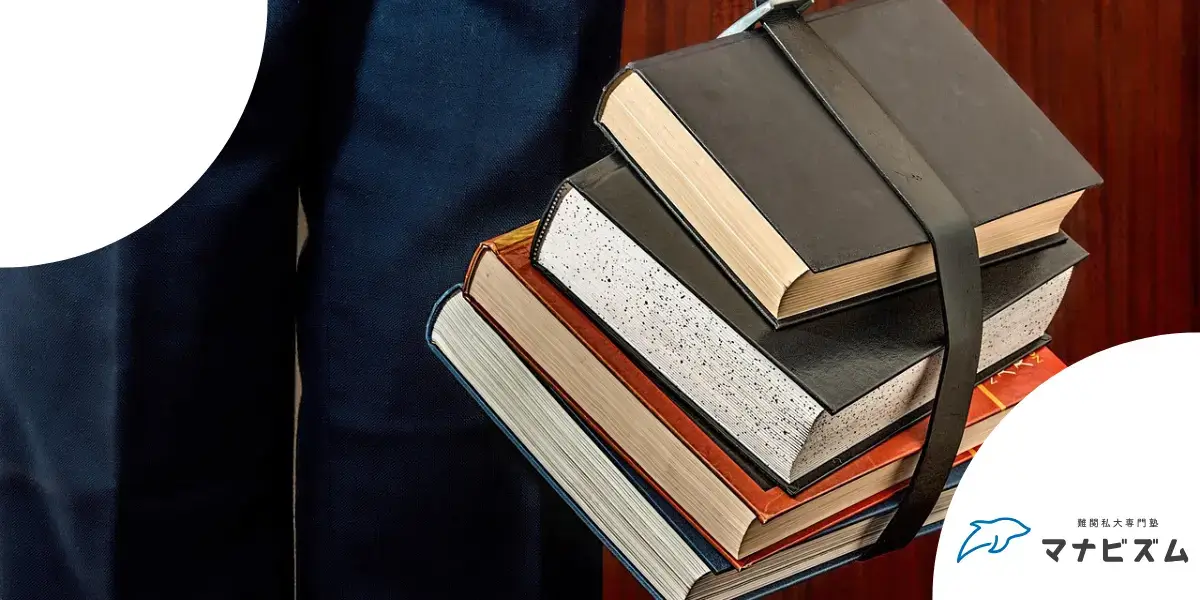
単に「良い参考書」を順番に並べるだけでは、大学受験の計画は精密になりません。年間で”いつ何を達成するか”にもとづいて参考書を選定してください。
参考書はあくまでも力を得るための手段で、目的から逆算して選ぶのがベターです。例えば、英語なら「正確に1文1文訳せるか」「論理的に読み進められるか」などの力を意識して参考書を選びましょう。
- 完璧にしたい人:8割は必ず達成できる量で計画する
- 適当にしてしまいがちな人:いつまでに終わらせるかを明確に決める
などのように、「いつまでに・どの程度」終わらせるかを設定できれば、無理なく進められるはずです。
大学受験の勉強計画では『修正力』がもっとも重要
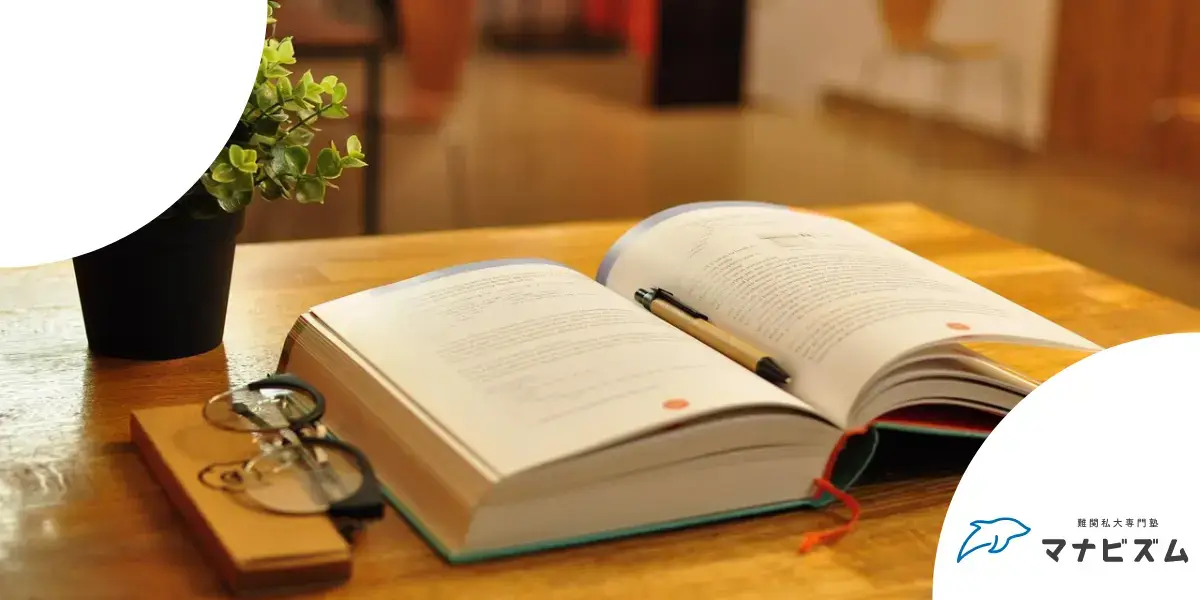
大学受験の勉強計画の立て方で、もっとも重要なのは『修正力』です。週単位で「今、自分はどこにいて」「どこに向かっているのか」を確認する工程を設けてください。
『長期計画は、ふとした拍子に、そして簡単に崩れる』からです。
風邪をひく、部活で疲れる、模試で凹む──。人生は大人も含めてそんなに完璧に進みません。でも大丈夫です、崩れてもいいのです。
大事なのは「崩れたとき、どう戻すか」という修正力です。
「頑張っているのに報われない」──。その原因は、だいたい修正力のなさにあります。例えば、「英語長文が読めない」という問題でも、以下のような違いがあります。
- 単語が分からない?→基礎不足
- 文は読めている?→解釈の練習不足
- 読めても解けない?→設問のアプローチが雑
ここを間違えるから、「頑張っているのに成績が上がらない」という悪循環に陥ってしまうのです。自らの弱点を正確に把握し、適切な対策を講じる修正力を意識しましょう。
わからない・難しいときには
ここまでお伝えしましたが、大学受験の勉強計画は、「立てたら勝ち」ではありません。「動いて、崩して、直して、積み上げて」、ようやくモノになるのです。
参考書でも、映像授業でも、自習でも──「修正力」がなければ成績は伸びません。今の時代、情報は山ほどあります。参考書ルートも、合格者の勉強法も、全部ネットに転がっているでしょう。
ただし、「君に合ったやり方」であるかは別問題です。だれかのやり方を真似るだけでは、修正ができません。
だからこそ、マナビズムでは、キミに合った最適な勉強計画の立て方から、つまずいたときの修正方法まで、プロの講師が徹底サポートしています。
“キミ自身の勉強計画”を作って、”プロの軌道修正の力”で迷わずに学べるようになります。無料相談も実施中ですので、ぜひお気軽に講師へ相談してくださいね!
まとめ
大学受験の勉強計画を立てる際には、志望校と自らの現状を正確に把握し、そのギャップを埋めるための具体的な道筋を描きましょう。目標から逆算して計画を立て、定期的に振り返り、必要に応じて修正することが成功の鍵となります。
なかでも模試の結果や学習の進捗に応じて、柔軟に計画を調整する「修正力」がもっとも重要です。志望校合格に向けて、勉強計画を立て、着実に実行していきましょう。
計画が崩れても諦めず、修正しながら前に進むことで、必ず志望校合格への道が開けます。
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————
よくある質問(FAQ)
大学受験生は1日何時間勉強する?
大学受験生の1日の勉強時間は、個人差が大きいですが、一般的には平日で3〜5時間、休日で6〜8時間程度が目安となります。ただし、単純な時間の長さよりも、集中力を保ちながら質の高い勉強をすることが重要です。
関連記事:大学受験生の平均勉強時間は1日何時間?合格を目指すスケジュールを組もう
基礎固めは何月までやるべき?
基礎固めの期間は、志望校のレベルや自らの学力によって異なりますが、一般的には受験年の夏頃までに終わらせることが理想的です。高3の夏までに基礎を固め、秋からは応用問題や過去問演習、冬からは志望校対策に集中するといった流れをくみましょう。