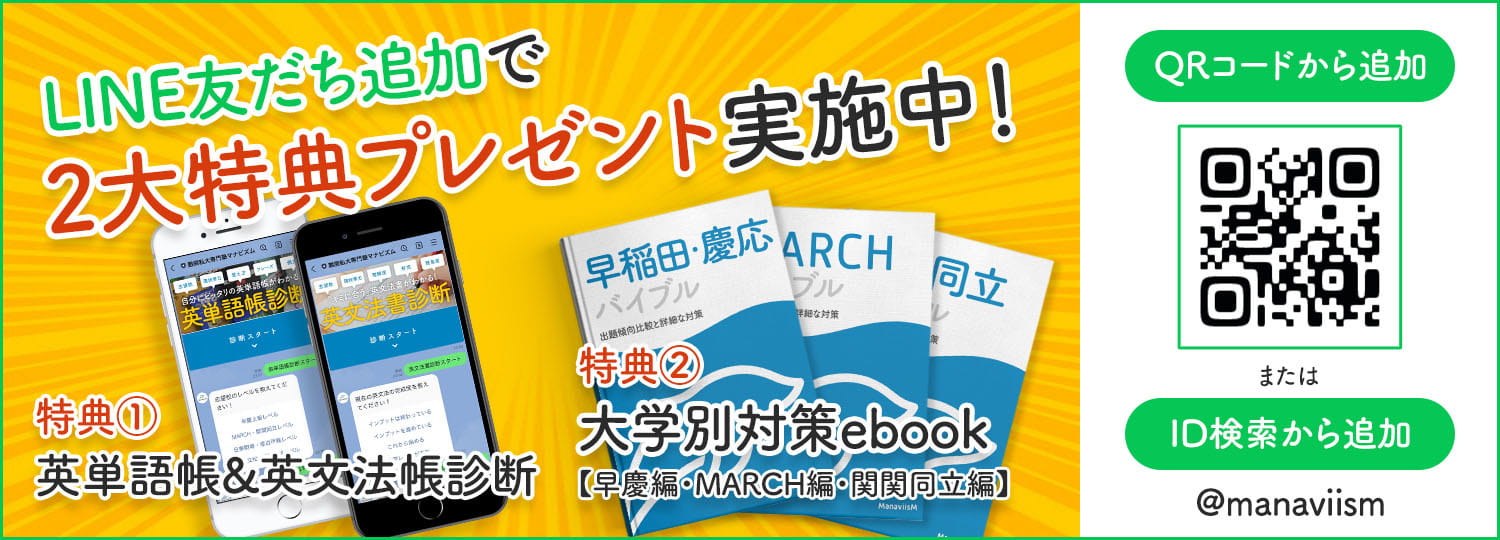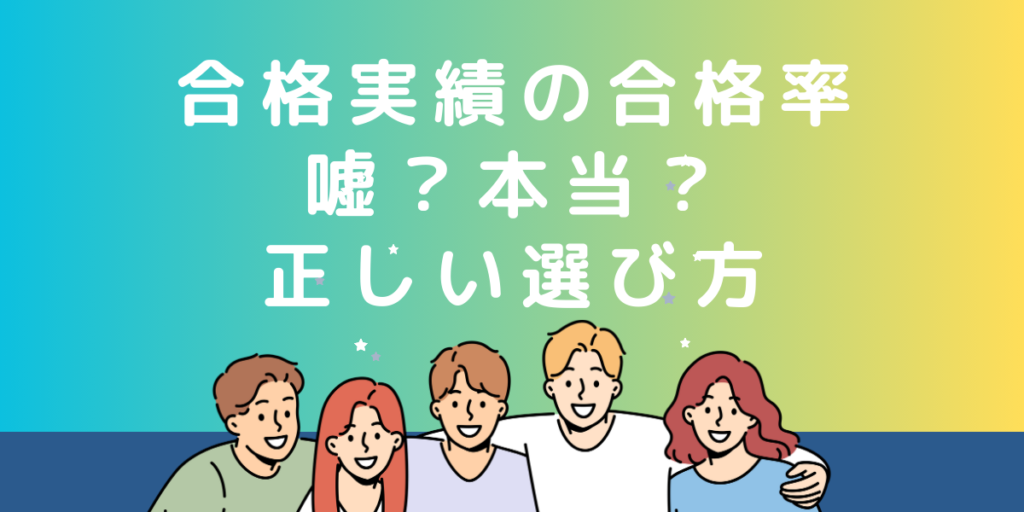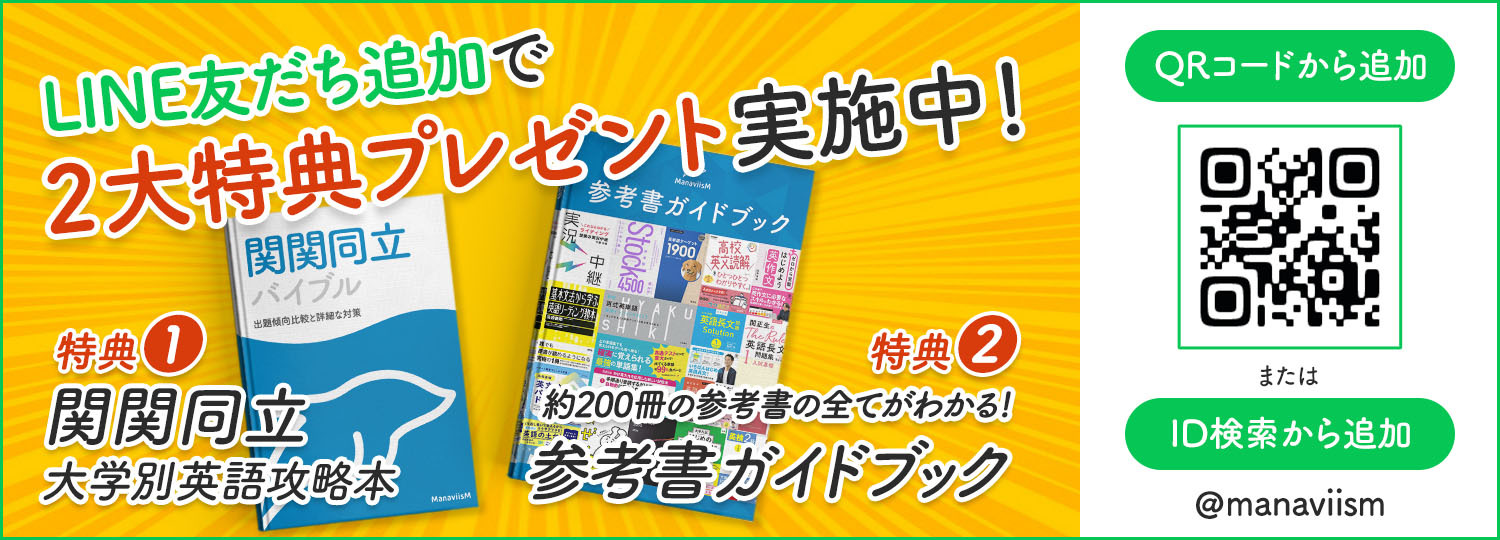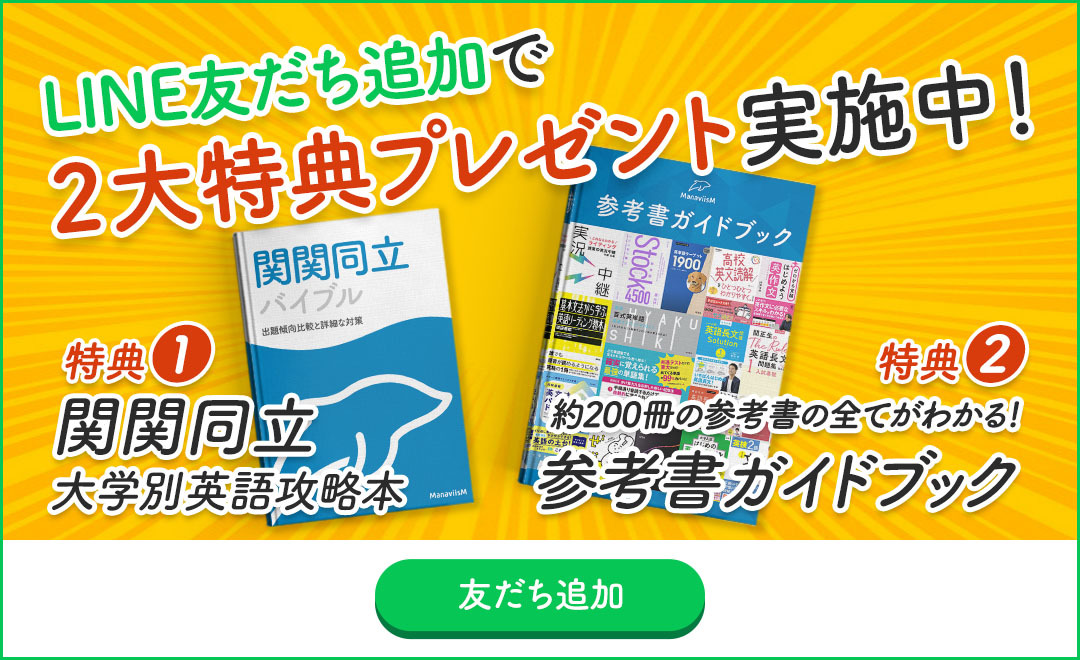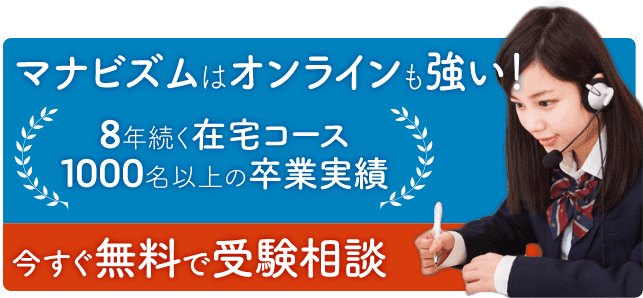関関同立の共通テスト利用ボーダーはいくつ?利用方法まとめ
更新日: (公開日: ) COLUMN

関関同立の共通テスト利用におけるボーダーが気になりますね。ボーダーとは、合格か不合格かの可能性が50%に分かれるラインのことです。関関同立の共通テスト利用ボーダーは、73~88%と予想されています。
この記事では、関関同立の共通テスト利用の方法やボーダーラインについて解説します。ボーダーを知っておくことで、どのくらい勉強が必要なのかの目安になるでしょう。関関同立受験で共通テスト利用を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:【決定版】関関同立(KKDR)とは?意味や偏差値・序列などを専門塾が解説
関関同立の共通テスト利用のボーダーは?
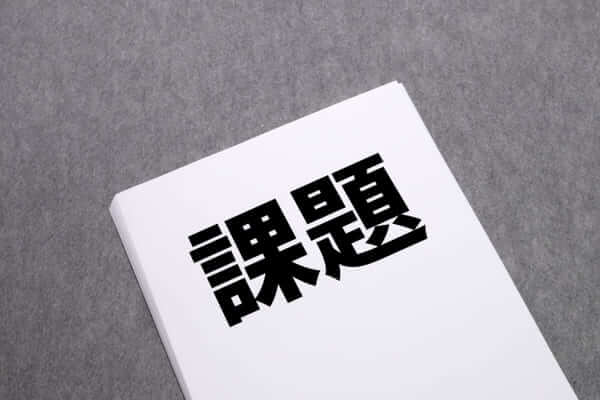
関関同立の共通テスト利用のボーダーについて、調査した結果は下記の表の通りです。
| 大学名 | 共通テストボーダー得点率 |
|---|---|
| 同志社大学 | 72%~90% |
| 立命館大学 | 71%~92% |
| 関西大学 | 67%~86% |
| 関西学院大学 | 69%~94% |
※この表は横にスクロールできます。
それぞれのボーダーが出ていますが、一番低いのが関西大学となっており、その他の3つの大学はそれぞれ高くなっています。
各学部によって大きくボーダーラインが異なる
共通テスト利用のボーダーラインは、各学部によって大きく得点率が異なります。
例えば、同支社大学の総合心理学部は77%がボーダーですが、理工学部では88%と11%も差があります。満点の値が異なることから差が生まれる可能性も考えられるでしょう。受験学部の目標としてボーダーを確認する場合には、間違った値を参考にしていないか再チェックしてください。
関関同立受験における共通テスト利用の特徴

関関同立受験で共通テスト利用を考えるとき、知っておきたい特徴を下記にまとめました。
- 複数受験が可能
- 一般受験との併願ができる
- ボーダーは高く見積もる必要がある
共通テストの結果だけで複数受験が可能なため、受験時の負担が少なくなります。また、日程によって一般受験との併願も可能で、受験するチャンスが増えることから合格の可能性も高まるでしょう。このメリットを最大限に活かして、志望校に出願してください。
ただし、難関私大である関関同立の共通テスト利用では、ボーダーを高く見据えて得点力を身に着けておく必要があります。共通テストで合格できるように、幅広く得点できる学力を備えましょう。
関関同立の共通テスト利用受験ならマナビズム
関関同立の共通テスト利用でボーダーを超えたい人は、マナビズムで学習することをおすすめします。
マナビズムでは、授業だけでなく、授業を受けっぱなしにせずに理解力を深めるためのゼミを用意しています。
さらに、自習のやり方や考え方についても専任の講師が丁寧に指導をおこなうため、これまで自習が苦手だった人や、何を勉強すれば効率よく学べるのかが気になる人にはピッタリです。
共通テストの対策を効率よく行うために、ぜひマナビズムを検討してください。
『無料体験授業』を受けよう関関同立・MARCH・難関私大を目指しているならマナビズムの『無料体験授業』がおすすめ!
・合格するためのマル秘合格戦略
・受験に成功・失敗する受験生の違い
・成績が上がる参考書の上手な使い方
・継続できるモチベーションアップ術
・部活と勉強を両立できる勉強術
『何をやれば受かるのか?』志望校合格までのはっきりとした道筋が見えるようになります。
【マナビズムの無料体験授業はここが違う!】
・気軽な相談だけでもOK!
・無理な勧誘一切なし!
・無料でプロのコンサルが受けられる!
まずは、気軽にお問い合わせください!
関関同立の共通テストはどうやって利用すればいいの?

関関同立の共通テストはどのように利用すればいいのか、下記にそれぞれの大学の利用方法をまとめました。
- 関西大学の共通テスト利用方法
- 関西学院大学の共通テスト利用方法
- 同志社大学の共通テスト利用方法
- 立命館大学の共通テスト利用方法
共通テストを利用して受験する予定がある人や検討中の人は、参考にしてください。
関西大学の共通テスト利用方法
関西大学の共通テスト利用は、下記の3つの方法があります。
- 併用
- 前期
- 後期
併用では、共通テストの得点と個別の学力試験の両方の得点によって、合否が決まります。例えば、関西大学法学部の共通テスト併用小論文なら、共通テスト+小論文(「現代社会」「政治・経済」を題材にしたものを出題)となっています。
前期と後期は併用とは異なり、個別の学力試験は課されません。2~3教科、3~4科目にて受験が可能で、それぞれの学部ごとに自分が得意な科目で受験できるようになっています。
共通テスト利用については学部によって違いがあるため、事前に関西大学の受験要綱をよく確認するようにしてください。
関西学院大学の共通テスト利用方法
関西学院大学の共通テスト利用方法は、下記の3つです。
- 併用
- 1月出願
- 3月出願
併用の場合、関学英語併用型と、関学数学併用型の2種類が用意されています。
共通テストに加えて、英語・数学どちらか1科目の得点を合計して合否を判断するというものです。
例えば、法学部の関学英語併用型であれば、2強化、2~3科目にて受験し、個別学力試験として、コミュ英(I・II・III・英表I・II)が用意されています。
数型であれば、個別学力試験で数I・II・A・B(数列・ベクトル)となります。
1月出願と3月出願の場合には共通テストのみでの合否判断です。
3科目型と4科目型があり、1月3科目型なら、共通テストでは古典は古文と漢文いずれかの高得点を採用される仕組みです。
こちらも学部によって違いがあるため、必ず大学の受験のページを確認するようにしてください。
同志社大学の共通テスト利用方法
同志社大学は、多くの学部で、共通テスト利用入試の利用方法のみが採用されています。
個別の学力試験はなく、法学部の場合には4教科、5~6科目での受験が可能です。
国語、数学、外国語の3教科は必須で、地歴、公民、理科から選択できます。
英語については、リーディングとリスニングの100点ずつ計200点満点のところを、リーディング200点、リスニング100点の300点満点で換算し、200点満点に圧縮するという方法がとられていますので、注意しましょう。
また、文学部の場合、個別学力試験として英語での口頭試問があり、社会学部と神学部では小論文の試験があります。
このように、学部によって同じ共通テスト利用でも個別の試験の有無に違いがあるため、事前によく確認してください。
立命館大学の共通テスト利用方法
立命館大学の共通テスト利用方法は、下記の4つです。
- 併用
- 後期分割方式
- 2月
- 3月
併用では、共通テストに加えて別途個別の学力試験があります。
共通テスト併用5教科型や、共通テスト併用3教科型が用意されているため、学部による違いを確認しておきましょう。
後期分割方式は、法学部・経済学部・スポーツ健康科学学部で利用できる方法で、法学部の併用3教科型では、2教科2科目で別途、現代文B、国総(古漢除外)、コミュ英(I・II・III・英表I・II)の試験を実施。
各学部が指定する共通テストの科目にて、合否判断があります。
2月・3月は共通テストのみでの試験となり、個別の学力試験は用意されていません。
立命館では高得点科目を自動的に採用する仕組みになっていることから、自分で共通テストの利用科目を申請する必要がない点が特徴です。
まとめ
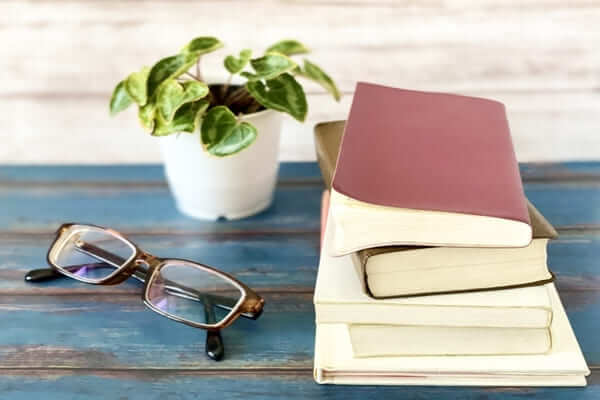
関関同立の共通テストのボーダーについて、どのくらいの得点率となっているのか、具体的にどういった利用方法があるのかについて紹介しました。
確実にボーダーを超えたい場合には、受験対策が可能な進学塾に通い、効率よく学べる環境を整えることをおすすめします。自分で考えて理解しなくてはならない問題が増えていることから、日々の生活の中でもできるだけ理屈を考えながら行動してみることが大切です。
志望校に合格するために、大切な時間を効率よく使って学習できるようにしたいですね。