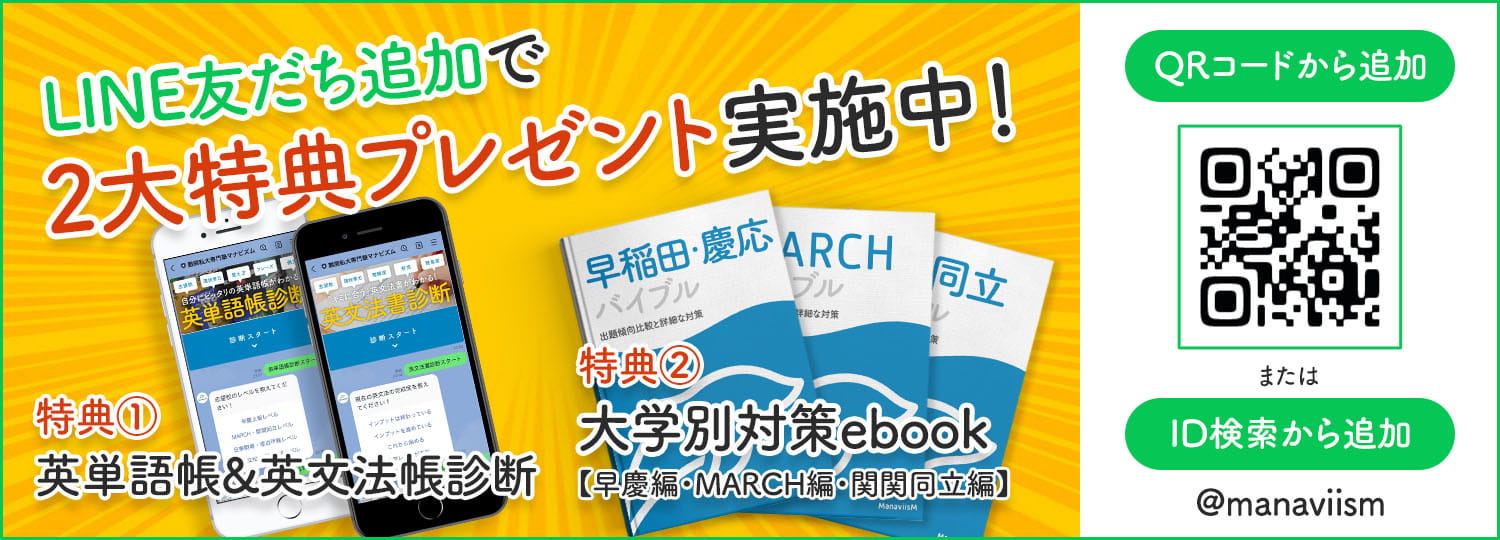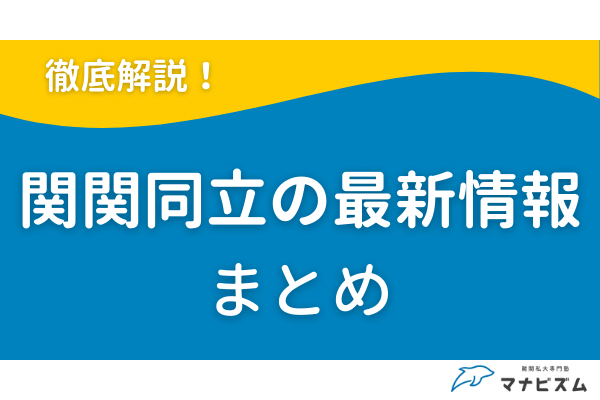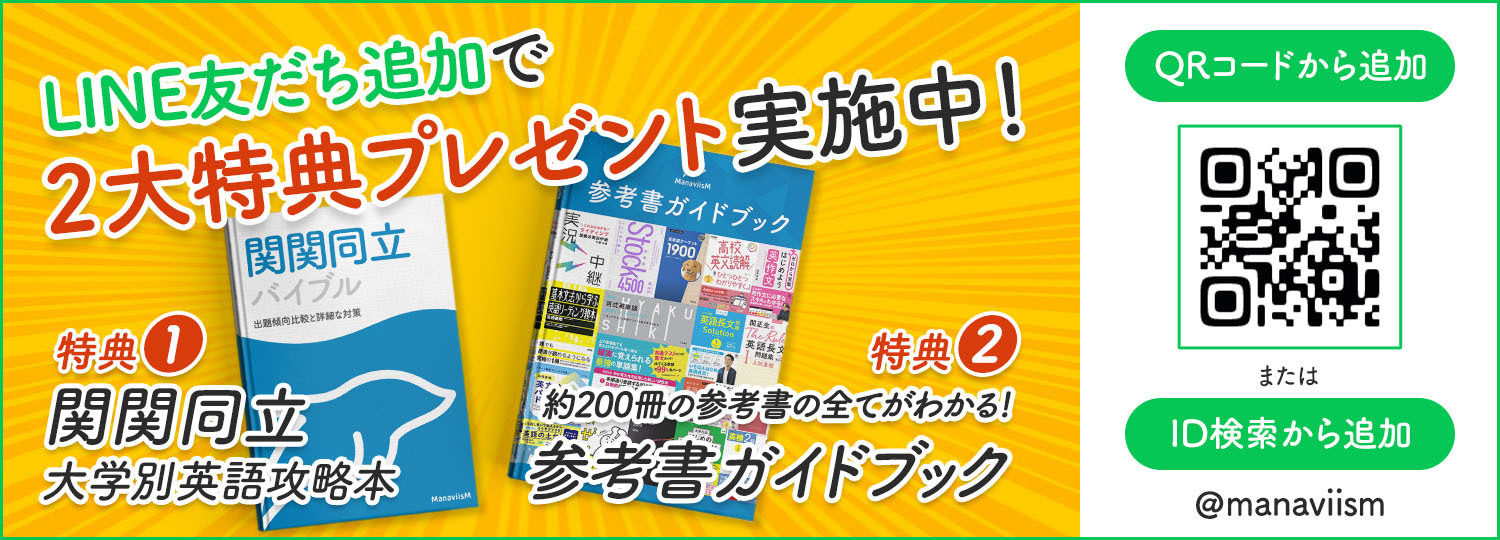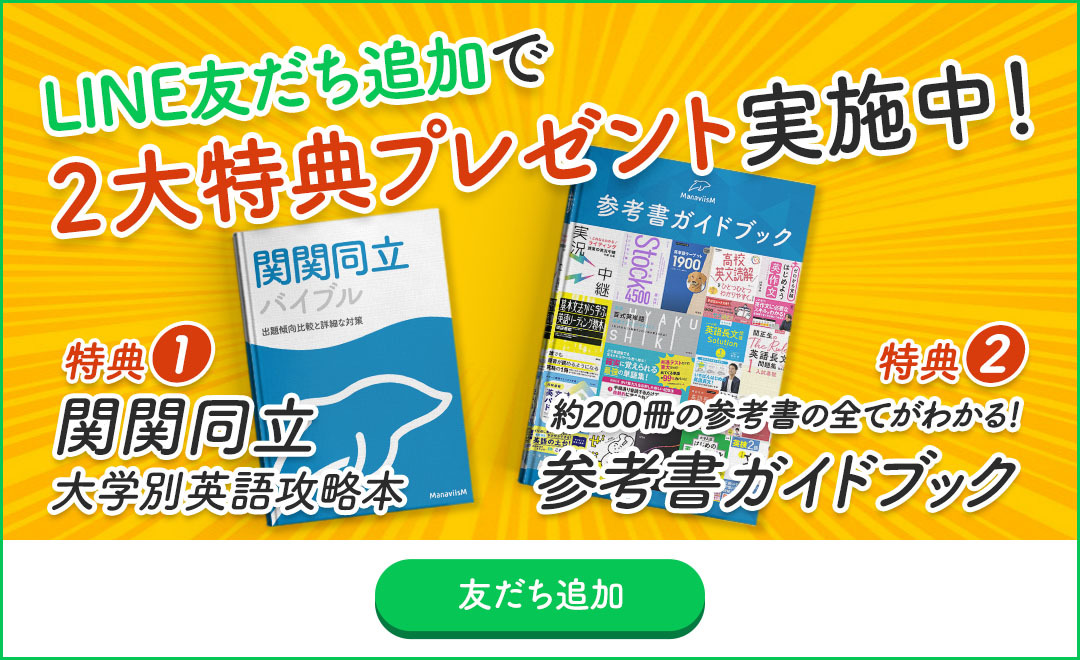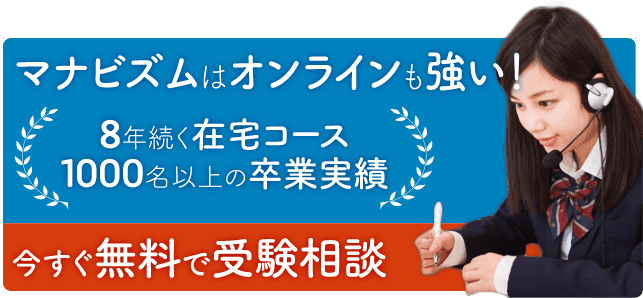今と昔の大学受験の違いは?認識の相違が引き起こす感覚のズレ【保護者様必見】
更新日: (公開日: ) COLUMN
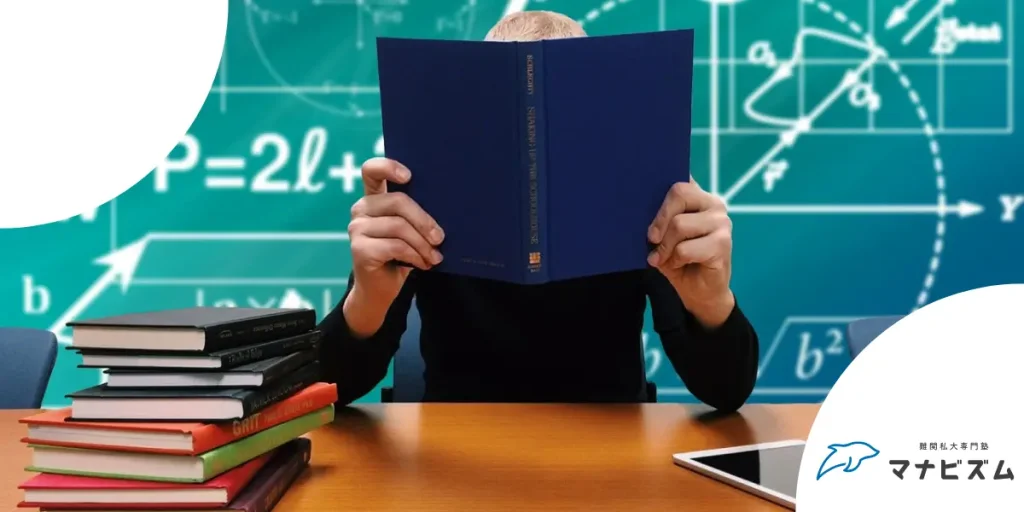
受験の厳しさ自体はそれほど変わっていませんが、今と昔では受験に対する考え方の部分で違いがあります。
受験相談をしていると、保護者様から「私の受験の時は」、「昔は」という話がよく出てきます。
しかし、時代の移り変わりによって、現在の価値観や考え方は保護者の方が思っている以上に変化しました。
その結果、お子様の考えとの差が生まれ、コミュニケーションもうまく噛み合いにくい状態です。
加えて、現在の大学受験を控えたお子さんの心境は、私たち親が思っている以上に複雑です。
親御さんの関わり方次第で、お子さんのモチベーションが下がったり、衝突が増えたりするケースもあります。
そこで、今回は今と昔の大学受験の違いを解説し、保護者様がお子様を適切にサポートする方法をお伝えします。
時代に合った関わり方で、お子様の力を最大限に引き出す参考にしてください。
YouTube動画でもご覧いただけます!
保護者さんから、受験相談でよく聞く「私の時代は…」、「昔は…」という声。
現役マナビズム講師の今井先生と八澤先生が、保護者世代と現在の受験の違いについて本音で語りました。
「うちの子はやりたいことがない」、「大学が決まらない」と悩む保護者様必見の内容です。
以下では、動画を閲覧できない方に向けて、テキストでもまとめています。
保護者の方が思う昔より厳しい?現代の受験の違い
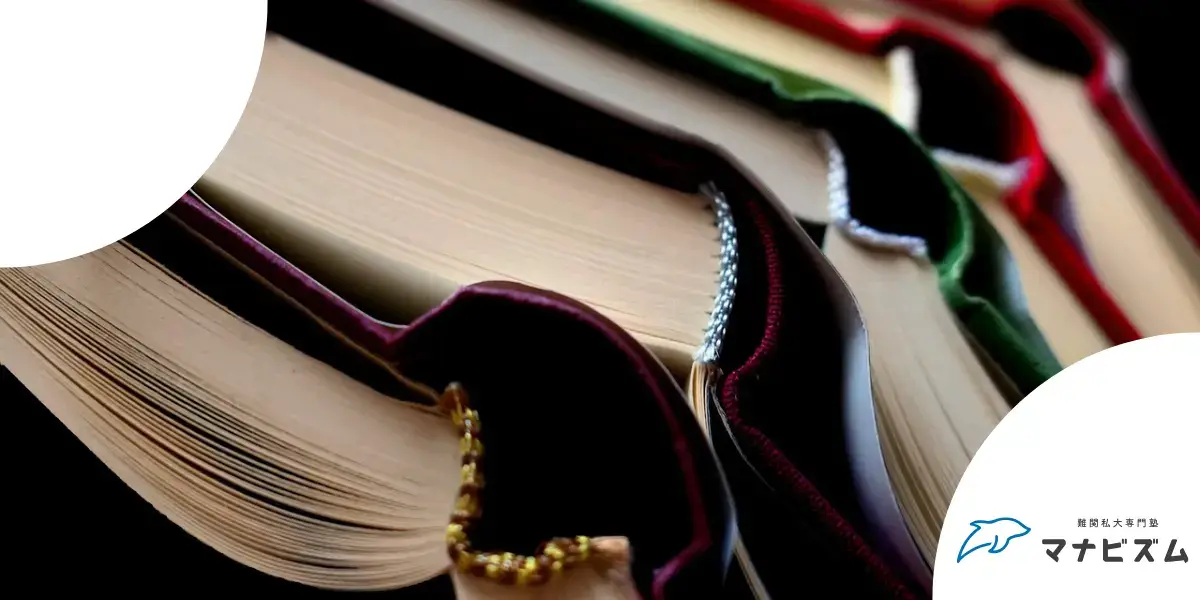
保護者の方と現在の受験生では、受験に対する考え方や価値観が異なります。
今と昔の大学受験では、単に制度が変わっただけでなく、受験生を取り巻く環境全体も様変わりしたからです。
まずは、今と昔の大学受験の違いで、もっとも知っておきたいポイントを以下に分けて紹介します。
- 受験へのこだわり
- 努力への価値観
- 受験の難易度
- 指導現場の変化
- 高校生を取り巻く環境
受験へのこだわり
保護者の方の世代では、強いこだわりがあるから頑張れる、という状況でした。
一方、今の受験生は以下のような強いこだわりを持たないケースが当たり前になっています。
- この大学に絶対行きたい
- このレベルには行きたい
こだわりがないからこそ、色々な選択ができるように今から頑張っておきたいという感覚を持っているわけです。
実際にマナビズムの出願戦略設計で添削をしていると、学部優先にチェックを入れる受験生はほとんど見ません。
この10年ぐらいで様変わりしてきているな、とマナビズムでも真摯に受け止めています。
もちろん、「学部優先」にチェックを入れる受験生も確かにいます。
そのほとんどは、教師になりたい(教育学部)、建築関係など、職業でやりたいことが決まっていました。
こうした受験へのこだわりは、また時代の移り変わりに応じて変化していく見込みです。
努力への価値観
今の高校生が考える頑張り、いわゆる努力への価値観も今と昔では違います。
保護者の方からすると、
- やりたいことが決まっていないから
- 大学が決まっていないから
などで、受験勉強ができないんだと考えやすいです。
一方、お子さんは、
- 何をしたらいいか分からない
- 今やってる勉強法が合ってるか分からない
などで頑張れていないだけです。
このような価値観の違いがある状態で、オープンキャンパスや大学の資料を保護者様が用意したとします。
結果、お子さんは「結局どうしたらいいか分からないし、情報も多くて…」となってしまうのです。
今の高校生は情報が溢れている環境で育っているため、選択肢が多すぎると逆に動けなくなってしまいます。
受験の難易度
また、今と昔では受験の難易度も変化しています。現在は、
- 一般入試経由の大学入学者 → 全体の約57%
- AO・推薦入試経由の大学入学者 → 全体の約43%
などのように、受験形式が複雑で難易度も高くなってきています。
ここ数年で急激に変化したというより、徐々に以下の形式が増え、一般入試が減ったというイメージです。
- 指定校推薦
- 学校推薦型選抜(推薦入試の新しい名前)
- 総合型選抜(AO入試の新しい名前)
昔はほとんどの人が一般入試で受ける、という非常にシンプルな受験でした。
今では、一般入試だけを切り取っても、以下のように大学によってさまざまで複雑になっています。
- 共通テスト(センター試験の後継)を使うのか使わないのか
- 日程がどうなっているのか
- 何回も受けられるのか
- 1日程で何回も結果を出してくれるのか
※[中央教育審議会 初等中等教育分科会(第59回)議事録・配付資料 [資料2-1]-文部科学省](https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/08030317/002.htm)
指導現場の変化
親御さんの予備校全盛期から、映像授業への移行が進んでいます。
マナビズムの今井先生が受験生だった頃(36歳時点)に東進が伸び、その手前ぐらいまでが予備校全盛期でした。
代ゼミ・駿台で有名な先生・人気の先生の授業にはなかなか入れない、講座もすぐ埋まるという時代です。
そこから東進がさらに活躍してきて、予備校が衰退していく流れになっています。
今では「映像って…」という感覚が、すでに薄れて一般化しています。
昔と異なり、高校生には映像での学習が当たり前の環境なのです。
高校生を取り巻く環境
高校生を取り巻く環境は、YouTubeも利用でき、小さいデバイスで動画を見るのも当たり前の時代です。
今から13〜15年前ぐらいにiPhone 3Gがソフトバンクから出て、そこから数年後に変化が起きたのです。
当時は保護者の方が「映像で教えるってどうなの」という感覚だったはずです。
しかし、子どもは全然映像に抵抗がないという時代を迎えているのです。
『大学受験に向けて映像で勉強するなんて』考えられなかったのに、今は結構それが主流になっています。
どれくらい違う?データで見る今と昔の大学受験の違い

ここまでは体感ベースでしたが、数字で見ると、今と昔の大学受験の変化がより明確になります。
以下ではデータを参考に、どれだけの変化が起きたのかを見てみましょう。
選べる大学数
まず、高校生が進路として選べる大学数の増加です。
令和6年までの推移で見ると、18歳の人口は1991年における206.8万人をピークに減少に転じました。
今後も減少傾向で推移する一方で、選択肢となる大学数は増加しています。
| 年度 |
大学数 |
|---|---|
| 昭和63年時点 | 490 |
| 平成30年時点 | 782 |
| 令和元 | 786 |
| 2 | 795 |
| 3 | 803 |
| 4 | 807 |
| 5 | 810 |
| 6 | 813 |
大学数は、昔と今を比較すると約1.7倍、つまり大学の多様化が進んでいる状態です。
お子さんの学部の選択肢も増え、従来にはなかった学際的な学部も多数設置されています。
- 国際関係学部
- 環境学部
- 情報学部 など
昔と比べると、今はお子様が迷うのも当然の状況になってきました。
大学への進学率
次に、選択肢が豊富になった大学への進学率も高まっています。
進学率(18歳人口に対する大学入学者数の割合)については、2021年で55.5%です。
昔と比較すると、今では大学に進学する高校生の割合が増加しています。
| 年度 |
西暦 |
大学・短期大学等への現役進学率(※) |
|---|---|---|
| 昭和25〜63 | 1950〜1988 | 約25.78% |
| 平成元〜30 | 1989〜2018 | 約34.37% |
| 令和元 | 2019 | 54.7% |
| 2 | 2020 | 55.8% |
| 3 | 2021 | 57.4% |
| 4 | 2022 | 59.5% |
| 5 | 2023 | 60.8% |
| 6 | 2024 | 61.9% |
※通信教育部への進学者を除く
数値から見ても、以前よりも大学へ行く高校生は増えていますね。
少子化の影響を受けつつ、大学数が増えている状態のため、これは大学に行きやすくなっているからです。
この変化により、大学進学が「特別なこと」から「当たり前のこと」へと意識が変わっています。
※[科学技術指標2022・html版 | 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)](https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2022/RM318_32.html)
受験の難易度
今と昔では、受験の難易度も異なります。
「昔は厳しかった、今は楽だ」というのは、先ほどの進学率だけを根拠にした場合の話です。
実際には、
- 時代背景
- 大学数
- 人口構成
- 教育制度 など
前提条件がまったく違うため、単純な比較はできません。
もちろん、当時は辛く、その反面にエリートコースのような印象をお持ちの方もまだいるはずです。
しかし、昔(昭和)は進学率が低く、大学数も少なかった状況です。
また、受け皿は少なく、金銭的な余裕がなく受験できなかった世帯もありました。
対照的に、今(令和)は以下の要因から進学率が高くなっています。
- 大学数が増加している
- 地方でも進学できる環境がある
- 奨学金制度も拡充している
- 大学側が「選ばれる側」になってきている
わかりやすくいえば、「入るのが難しい」ではなく、「行かない選択をする人が減った」時代です。
変化する時代に即して、お子さんと向き合わなくては対立してしまいます。
難関私大(関関同立など)の難易度
マナビズムが専門としている難関私大(関関同立など)の難易度は、昔に比べて総合的に上昇しています。
保護者の方の世代では、浪人による合格率の向上も一般的でした。
現在は現役合格重視で競争が激化しているほか、一般入試枠の縮小や総合型選抜の増加も起きています。
もはや、単純な偏差値だけでは測れない難しさとなっているのです。
こちらについては、以下のページで詳しく解説しているので、ぜひ気になったらご覧ください。
関連記事:親のときとは違う?関関同立とは?受験生の親が気になることを一挙解説
今と昔の大学受験で変わらないたった1つのこと
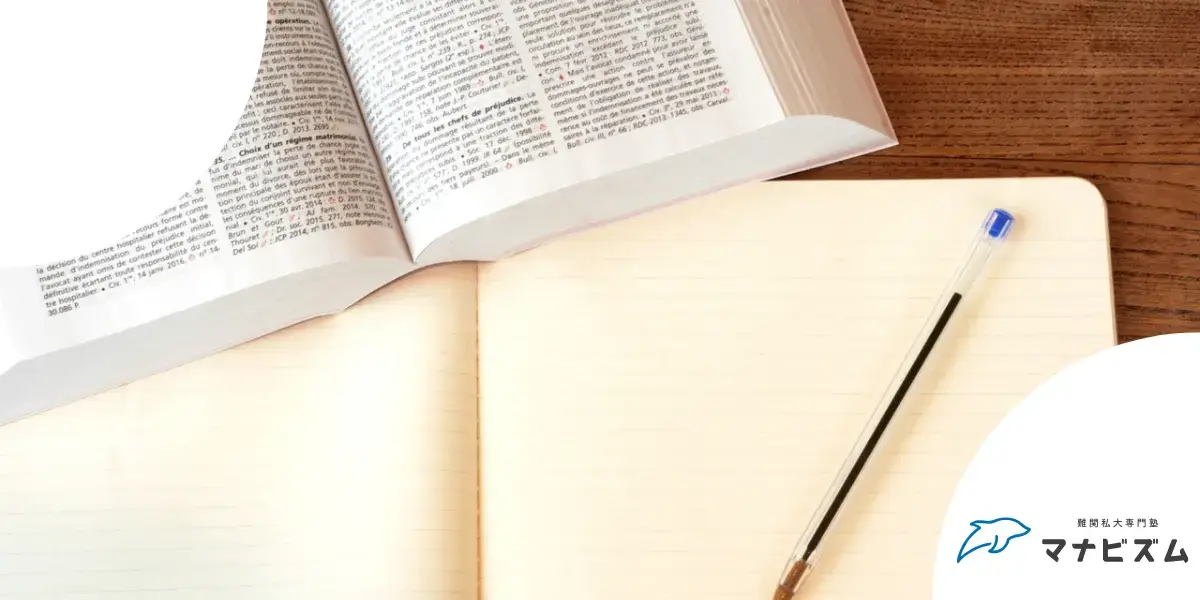
ここまで、今と昔の大学受験を比較してきましたが、変わらないのは授業だけでは成績が上がらないことです。
映像授業になろうが、集団授業だろうが、共通して今も変わらない現実です。
集団授業を受けていた保護者の方もいると思います。
しかし、「どの授業を取ろうかな」で『受かる・落ちる』は決まらなかったはずです。
「あの先生の授業は分かりやすかった」という、思い出には残っているかもしれません。
ただ、結局その先生の授業を取った子たちが全員受かって、そうじゃない子は落ちたかと言ったらどうでしょう?
そういうわけではなかったはずです。これは、30年前・50年前も今もまったく変わっていません。
大切なのは、授業を受けた後の自学自習(一人で勉強する時間)をどれだけ効率よく行えるかです。
むしろ、情報が溢れている現在だからこそ、正しい勉強法と計画を立てることがより重要になっています。
今と昔を比べずにこれから保護者の方が考えたいこと
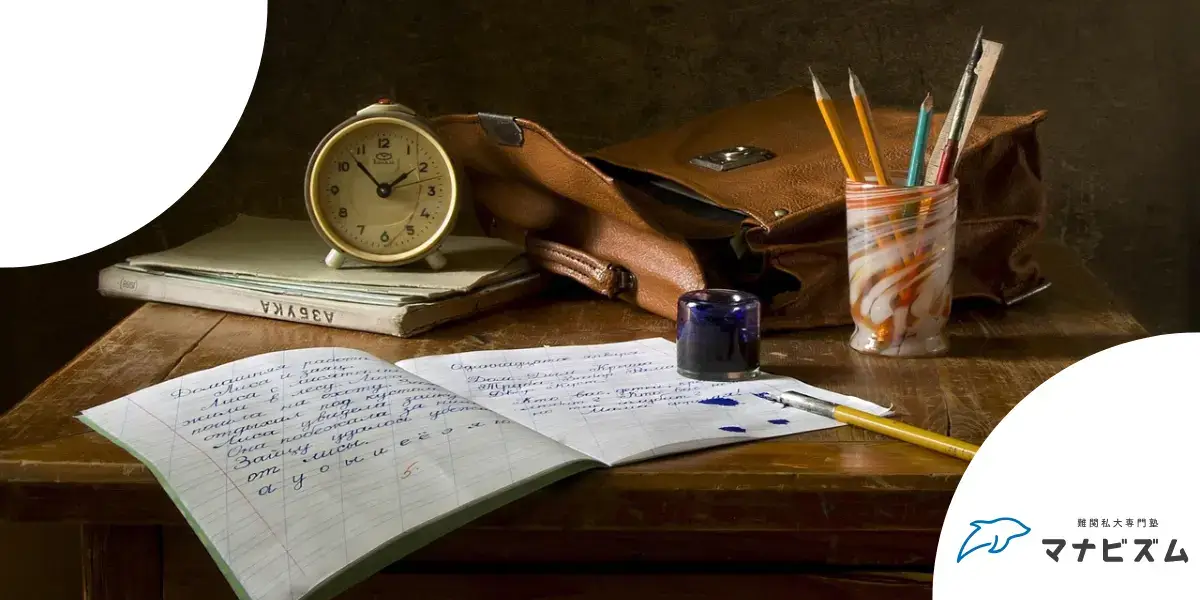
時代が変わった以上、昔の感覚でお子様にアプローチしても効果はありません。
今の時代に合った関わり方を理解し、お子様の成長を適切にサポートしてください。
以下のポイントを意識できれば、親子の関係をより良いものにできます。
- 情報に惑わされて空回りしない
- 悪い情報だけに目を向けない
- 決定を暖かく見守る
- 大学の説明では足りない
情報に惑わされて空回りしない
まず、大学受験では保護者の方が空回りしないでください。
色々な話を聞いて、色々な情報を手に入れると「もっとこうしなければ」となるはずです。
しかし、親御さんが空回りしても成績は上がりません。
やるのは受験生本人なので、親は理解したうえで接してあげてください。
やる気がない子でも、いい大人との出会いによって目覚めることもあります。
成績が上がる時はすぐなので、そういうものだと理解してほしいのです。
今と昔では受験環境が大きく違うのを受け入れ、お子様のペースを尊重しましょう。
悪い情報だけに目を向けない
次に、公平に判断できる親御さんだからこそ悪い情報だけに目を向けないでください。
情報感度が高い親御さんほど、色々な説明会や進路相談会に行って情報を収集しているはずです。
しかし、大学受験は保護者の方がどれだけ調べても、結果として有利になるケースはあまりありません。
他方、それをしていない家庭が不利になるとも、マナビズムの経験上あまり感じません。
どこまで調べたところで、以下の3つを1本軸でつなげないと語れないからです。
- 子どもがどうしたいか
- 子どもがどれだけ勉強したか
- どこに行きたいか
プラスに転じるとしたら、保護者様のモチベーションによって子どももスタートが早くなる程度です。
ただ、お子さんは全然やる気ないのに親だけやる気になって「しんどい」という家庭も見受けられます。
『情報』はきっかけにすぎず、必要な情報を整え、渡してあげる支援を考えましょう。
決定を暖かく見守る
保護者の方にとって、高校生の決定を暖かく見守るのも立派なサポートです。
焦って「決めろ」といわなくても、勝手にきちんと決めますので、一旦暖かく見守ってください。。
『こだわりのあるほうが頑張れる』と親なら思うはずです。
しかし、実際に出願日程を作るときに優先順位をつけはじめて勝手に決めます。
- 「この学部に行ってから何するんだろう」
- 「どこで休みの日を作ろうかな」
など、出願の時期が近くなれば今まで「どの学部でもいい」といっていた子でも決めるようになるのです。
なお、大学が決まっていないパターンなら、高3の夏ぐらいまでに決めておけば十分です。
大体の大学群・レベルさえ決まっていれば、勉強する内容に大差は生まれないからです。
夏休みに友達や塾生の仲間と勉強の息抜きがてら、午前中だけ大学を見に行くなどで決めれば問題ありません。
大学の説明では足りない
大学受験で志望校を探す際においては、大学の説明だけでは情報として足りません。
大学の説明会を聞きに行っても、大学側は大衆に向けて話すしかできないからです。
つまり、「あなたにとってはこれがいいですよ」という個人視点での情報は出せないのです。
そういう場合は、小中高を見ている塾ではなく、大学受験を専門にやっている塾や予備校が良い相談先です。
「今こういう状況ですけど、どういう風に勉強の戦略を組んでいくのがいいか」を聞いたほうが早いです。
ただし、そこまでにある程度決めておいてほしいのは、入試方式の大まかな決定です。
- 指定校推薦を受ける・受けない
- 総合型選抜を受ける・受けない
- 一般入試を受ける・受けない
- 公募推薦入試を受ける・受けない
これぐらいは決めておいて、志望校を聞いて現状を考えてください。
塾側も、全部紐づいて「じゃあこれが1番合理的です」というアドバイスができます。
まとめ:難関私大を本気で目指すなら
今と昔の大学受験の違いを理解できれば、お子様との関わり方が見えてきたはずです。
現在の高校生はこだわりがないのが当たり前です。
そして、焦らず見守りつつ、正しい環境と出会いを用意すれば、きちんと変わります。
昔と今では価値観も制度も違い、こだわりがないのは悪ではなく、むしろ選択肢を広げている状態です。
保護者が情報収集や決断を急いでも、本人から動かなければ意味がありません。
やる気や志望校は、きっかけ次第で急に芽生えるものです。
だからこそ、今は「詰める」よりも「見守る+出会わせる」が大切になります。
マナビズムでは、現在の受験環境に最適化した指導で、関関同立をはじめとする難関私大合格を実現しています。
時代に合った正しい勉強法と環境で、お子さんの可能性を最大限に引き出しませんか。
少しでも気になる疑問があれば、すぐ無料受験相談からお問い合わせください!