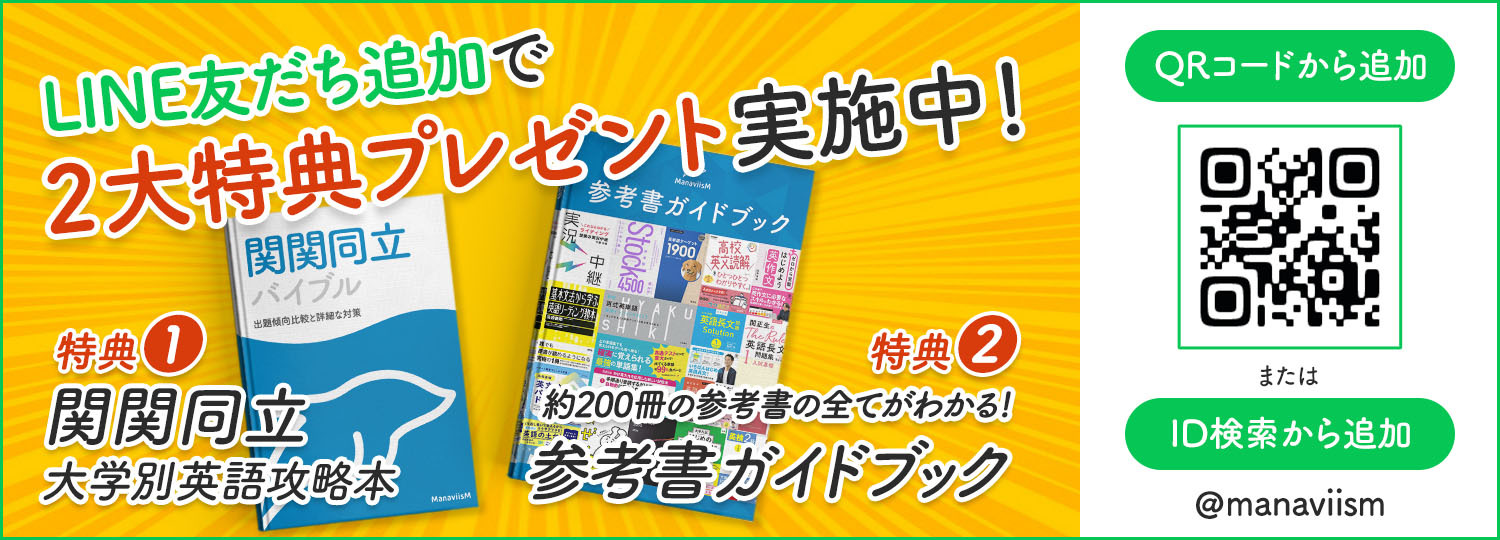- 「いつまでに何をすればいいの?」
- 「志望校はいつ決めるべき?」
- 「子どもの勉強ペースは適切?」など
高校3年生のお子様を持つ保護者の方、はじめての大学受験で不安になっていませんか?
大学受験は年間スケジュールの全体像を早めに把握し、夏までに志望校を大まかに決めるのが成功のカギです。
この記事では、保護者の方が知っておくべき高校3年生の受験スケジュールとペースについて解説します。
時期別の具体的な取り組み内容から保護者の役割まで「1年間の流れ」を知り、支援ができるようになりましょう。
今、この時点で不安を感じている、すぐに相談したい方はぜひ無料受験相談からお声がけください。
マナビズムの講師が親御さんやお子さんの疑問にお答えしつつ、明確な道筋をご提案します!
【保護者の方へ】高校3年生の受験スケジュール・ペース
【動画でもご覧いただけます!お子様に対して保護者がうるさくいうのではなく、動画を一緒に見るなどして自然な情報共有をおすすめします。】
高校3年生の受験は、年間を通して明確なスケジュールがあります。
保護者の方がまず理解すべきは、
- いつまでにどのくらいの成績を取るべきか
- 過去問はいつからやるのか
- 志望校・併願校はいつ決めるか
- オープンキャンパスの時期はどうするか
などの全体像です。
高校3年生という1年間は、お子様にとって人生の分岐点となる時期です。
とはいえ、実際には保護者の方における認識の違いで意外なギャップを生みます。
スケジュールや受験ペースは家庭で意識の違いがある
大学受験のスケジュールやペースについて、家庭内で意識の違いを生じるケースはよくあります。
保護者の方の経験や背景によって、受験に対する考え方が異なるためです。
例えば、以下の要因によりスケジュールやペースに対する感覚はガラッと変わります。
- はじめての大学受験(長男・長女)か、2人目以降か
- 公立高校か私立高校か
具体的には、公立高校出身の保護者は「中学の内申点」の感覚が残っており、定期テスト重視に偏りやすいです。
しかし大学受験(特に一般・公募)では定期テストの点と進学先に直接的な関係はほぼありません。
結果、誤解の原因となります。
また、公募推薦で評定が使われる場合でも、その配点は小さいです。
- 英語・国語200点
- 調査書25点
といったように、評定は合否を左右しにくいですから、高3から成績を上げても影響はありません。
では本題に戻って、次からは本題の大学受験のスケジュール・ペース配分を見ていきます。
【保護者必見】高3の大学受験のスケジュール・ペース
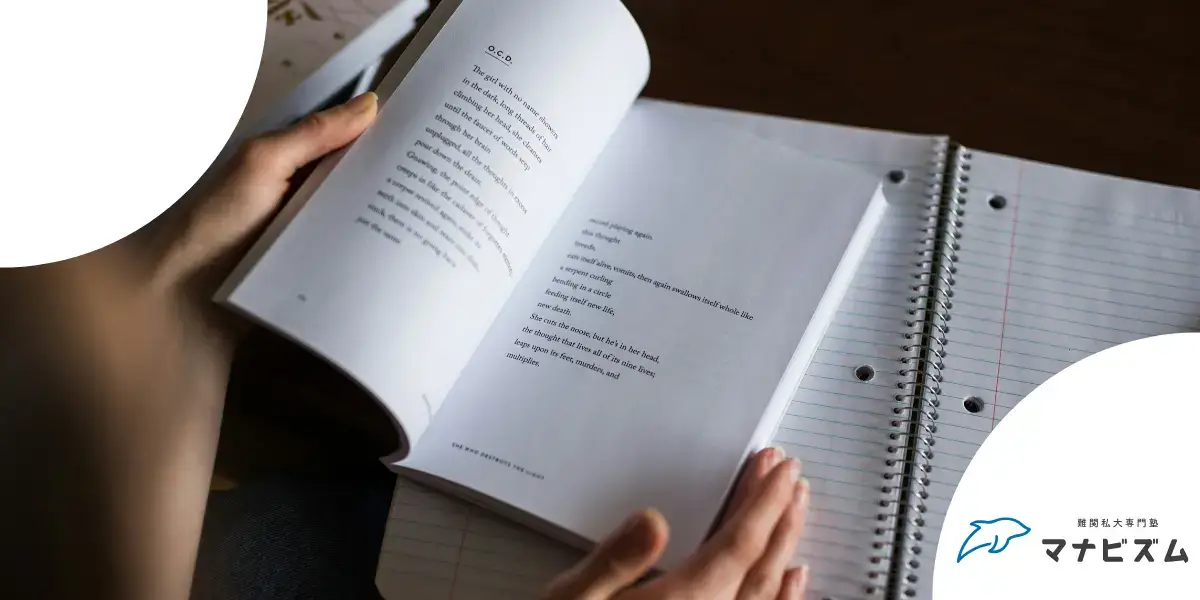
高校3年生の大学受験は、時期ごとに明確な目標と取り組み内容があります。
年間の流れを把握できれば、お子様の勉強状況を正しく理解し、適切なタイミングでサポートできます。
以下の表は、高校3年生の1年間における主要な活動内容とその時期をざっくりとまとめたものです。
| 時期 | 主な活動内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 3月〜4月 | 基礎の総復習 | 志望校未確定でも志望群レベルで走り出せる |
| 5月〜6月 | 基礎完成を目指す | 定期テストと受験勉強の両立が課題 |
| 7月〜8月 | 志望校・併願校の決定 | オープンキャンパスもこの時期に参加 |
| 9月〜10月 | 志望校の過去問演習を開始 | 大学別の傾向対策に分岐する時期 |
| 11月〜12月 | 公募推薦入試に挑む | 合格を確保できると精神的に安定 |
| 1月〜2月 | 私立一般入試を受験 | 出願・入試・発表が集中するラッシュ期 |
| 3月 | 進学先の最終決定と入学準備 | 繰り上げ合格や入学前課題の対応も必要 |
では、それぞれの時期の詳細を解説します。
3月〜4月(新高3スタート前後)
新高校3年生となる3月から4月は、本格的な受験勉強のスタート時期です。
春期講習・春休みのうちに基礎の総復習をはじめると、1年間の受験勉強の土台となります。
高校2年生までの学習範囲で弱点となっている部分を補強し、受験勉強の基盤を固める時期です。
この時点でまだ志望校が明確に決まっていなくても、まったく問題ありません。
- 「関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)あたり」
- 「産近甲龍(産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学)あたり」
など、大まかな志望群レベルでスタートできます。
目標到達時期や具体的な学習計画を立てる時期でもあります。
自習計画や教材選定について、塾や学習コンサルタントと相談し、お子様に最適な学習環境を整えてください。
5月〜6月(1学期中盤〜期末)
5月から6月は、受験勉強の本格的なペースに乗る時期です。
英語・国語など主要科目のインプット(基礎完成)を6月末を目安に終えているのが理想的です。
この時期の課題は、定期テストと受験勉強の両立となります。
なお、定期テストの扱いについては、進路によって異なります。
- 指定校推薦を目指す場合 → 定期テストに全力で取り組む
- 一般入試・公募推薦を目指す場合 → 定期テストは「うまくやる」程度に留める
学校の教材を活用しつつ、受験勉強と両立してください。
また、5月に学校で行う模試の結果をもとに、現状の学力分析も並行して進めましょう。
7月〜8月(夏休み・夏期講習)
この時期は、志望校・併願校の決定を遅くとも8月末までに行うことが、秋以降の学習につながります。
第1志望だけでなく、第2・第3志望となる併願校も明確に選ばなくてはなりません。
志望校の過去問研究を開始し、出題傾向や難易度を把握しはじめる時期でもあるからです。
志望校を選び兼ねているのであれば、オープンキャンパスは夏に必ず参加すべきイベントです。
校風や学生の雰囲気を肌で感じられると、「行きたい大学」という明確な目標を設定できます。
なお、学習面では、英語長文読解・現代文・古文・社会科目などの実践的演習にシフトします。
併願校の過去問にも少しずつ触れ、入試形式に慣れておくのもこの時期が最適です。
9月〜10月(2学期前半)
9月から10月は、本格的な過去問演習のステップに入る時期です。
志望校の傾向に特化した対策がスタートし、各科目で「点を取るための技術」を身につけます。
具体的には、夏までに決定した志望校の過去問を中心に、具体的な出題傾向を分析し、解答技術を習得します。
また、公募推薦・総合型選抜(AO入試)の出願がはじまる時期でもあります。
志望理由書や小論文の準備が必要な場合は、この時期に集中的に取り組んでください。
11月〜12月(2学期後半)
11月から12月は、私立大学の公募推薦入試を本格的に行う時期です。
合格を確保できると心理的に安定感が得られ、一般入試に向けた学習にも良い影響を与えます。
共通テスト利用方式を活用する場合は、共通テストに向けた対策を並行して進めるタイミングでもあります。
また、過去問演習と弱点補強のループを繰り返し、得点が安定しない箇所については再度インプットしてください。
1月〜2月(入試本番)
1月から2月は、大学入試のメイン期間です。
1月中旬に実施となる共通テスト、2月上旬以降の私立大学一般入試が集中します。
合格発表と入学手続きと、次々にイベントが押し寄せるもっとも忙しい時期です。
そして2月上旬以降には、関関同立や産近甲龍などの私立大学の一般入試が本格化し、連日の試験が続きます。
ここからが、合格のあった大学を見て進学先を最終決定するタイミングです。
3月(入試終了後)
3月は、国公立大学後期日程の受験や各種手続きが完了する時期です。
一部の滑り止め大学での繰り上げ合格もあるため、最終的な進学先決定まで気を抜けない時期となります。
進学先決定後は、「入学準備講座」や「大学基礎学力テスト」などへの準備もはじまります。
また、大学から送付される入学前課題への取り組みも必要です。
この時期は、受験生活の終了とともに新しい大学生活への準備期間でもあります。
長期間にわたる受験勉強の労をねぎらい、新しい環境での学習に向けた準備を整えてください。
関連記事:【脱失敗】大学受験の計画の立て方は?受験生に求められる修正力とは
保護者の方と高校生が受験初期にやるべきなのは進路の決定

保護者の方が「いつまでに大学を決めるべきか」で悩む理由は、「大学別対策の方が効率的では?」という意識があるからです。
しかし、実際には同志社大学でも、関西大学でも、春から夏にかけてやるべき基礎固めの内容はほぼ共通しています。
大学ごとの対策が分岐するのは、『夏以降』です。
春から夏までの期間は「大まかな志望群(例:関関同立、産近甲龍)」程度の設定で十分に学習が可能です。
逆に、夏までに志望校があいまいだと、秋以降の過去問演習や傾向別対策が非効率になってしまいます。
高3年では「春から夏は全大学で共通の基礎対策、夏から過去問と傾向別対策に移行」という流れを意識してください。
保護者の方が受験生のスケジュールに悩むときは
受験生のスケジュールについて具体的な悩みがある場合は、マナビズムの受験相談をご活用ください。
本記事はあくまで一般論であり、志望校・受験方式(共通テスト利用・私立専願など)により戦略は異なります。
志望校・受験方式・年間計画などの具体的な問題は、個別相談での解決が有効です。
ただし、保護者の方が前に出すぎて、お子様が受け身になる構図は避けるべきです。
「保護者だけが熱心で、生徒が上の空」というケースは、受験成功にとって好ましくありません。
推奨するのは、生徒と保護者が一緒に参加し、情報を共有して同じ方向を向くことです。
「今やるべきこと・今後の対策」を明確にする。
そのためにマナビズムではオンライン・対面どちらでも受験相談を実施しています。
ぜひ、まずはお気軽に無料の受験相談からお声がけください!
まとめ:高3の大学受験における保護者の方の役割
高校3年生の大学受験において、保護者の方の役割は「指示する人」ではなく「支える人」が基本です。
スケジュールと勉強の流れを一緒に整理し、口出しより「理解」と「対話」に努めてください。
「伴走者」として、お子様の自律的な意思決定を促す環境を整える意識を持ちましょう。
本記事をあらためてまとめると、保護者の方が意識すべきポイントは以下のとおりです。
- 年間スケジュールの全体像を把握し、夏までに志望校を大まかに決める
- 定期テストと受験勉強は「うまく両立」し、定期テスト至上主義にならない
- 保護者のスタンスは「指示する人」ではなく「支える人」が基本
- 進路選択のためには「現地(大学)」を見に行く
大学受験は、志望校選定から試験本番まで数か月〜1年以上と長期間に渡る過酷な道のりです。
だからこそ、保護者の方の理解とサポートが不可欠です。
少しでも気になる疑問があれば、すぐに無料の受験相談でそのお気持ちを聞かせてください!
高校3年生の保護者の方からよくある質問(FAQ)
受験校・志望校をいつまでに決める?
志望校選定においてもっとも重要なのは、以下の2つの基準です。
- 問題の相性
- 行きたいという気持ち(志望度)
同志社大学・立命館大学を第一志望にする場合、流通科学大学などと問題傾向が似ており、相性も良い関係です。
一方で、「関西大学+近畿大学」の組み合わせは人気がありますが、実際の問題傾向は必ずしも一致しません。
指導においては、選択肢を提示したうえで「どちらを選ぶか」を生徒に委ねる行動が大切です。
保護者の方も同様に、選択肢を押し付けるのではなく、提示・支援する役割を担いましょう。
関連記事:決定時期はいつ?大学志望校の決め方は5つのポイントで判断
オープンキャンパスにはいくべき?
志望校・併願校の最終決定にはオープンキャンパスへの参加を推奨します。
校舎の雰囲気や学生の様子を直接体感できる貴重な機会であり、志望度を高める要因です。
オープンキャンパスに参加すると、基本的にどの大学も「良く見える」ものです。
とはいえ、第2・第3志望校となる併願校の決定は8月末までの完了が好ましいです。
9月以降は過去問演習が本格的にスタートする時期のため、この時期までに方向性を固めてください。
なお、「滑り止め」という言葉は避け、「併願校」として前向きに捉えるのが基本です。
決定後は、併願校の過去問にも積極的に取り組み、「秋以降どのように得点力を伸ばすか」という具体的な計画を立てる前向きな姿勢が肝要です。
定期テストの対策は必要ですか?
定期テストへの取り組み方は、進路によって異なります。
- 指定校推薦を目指す場合 → 定期テスト重視(評定対策として当然必要)
- 一般入試・公募推薦の場合 → 定期テストに全振りしないほうが良い。受験対策を優先する
はじめての大学受験と向き合うご家庭では、春から塾に通わせた結果、「定期テストで高得点を取れるはず」と過度に期待してしまうケースがあります。
しかし、保護者の方が「テストの点が低い=勉強していない」と決めつけるのは危険です。
現代文や英語においては、学校の定期テストと大学入試問題の性質が異なります。
入試対策を優先した場合、定期テストの点数が一時的に低下しやすいですが、必ずしも学習不足を意味するものではありません。
過去問はいつからはじめるべき?
志望校の過去問は、9月以降に本格着手するのが理想的です。
そのためにも、志望校は遅くとも8月末までに決定する必要があります。
併願校の過去問も秋から並行して取り組めば、得点の見通しと戦略が立てやすくなります。
そうすると、過去問の購入時期も自然に実際の着手時期よりも前になります。