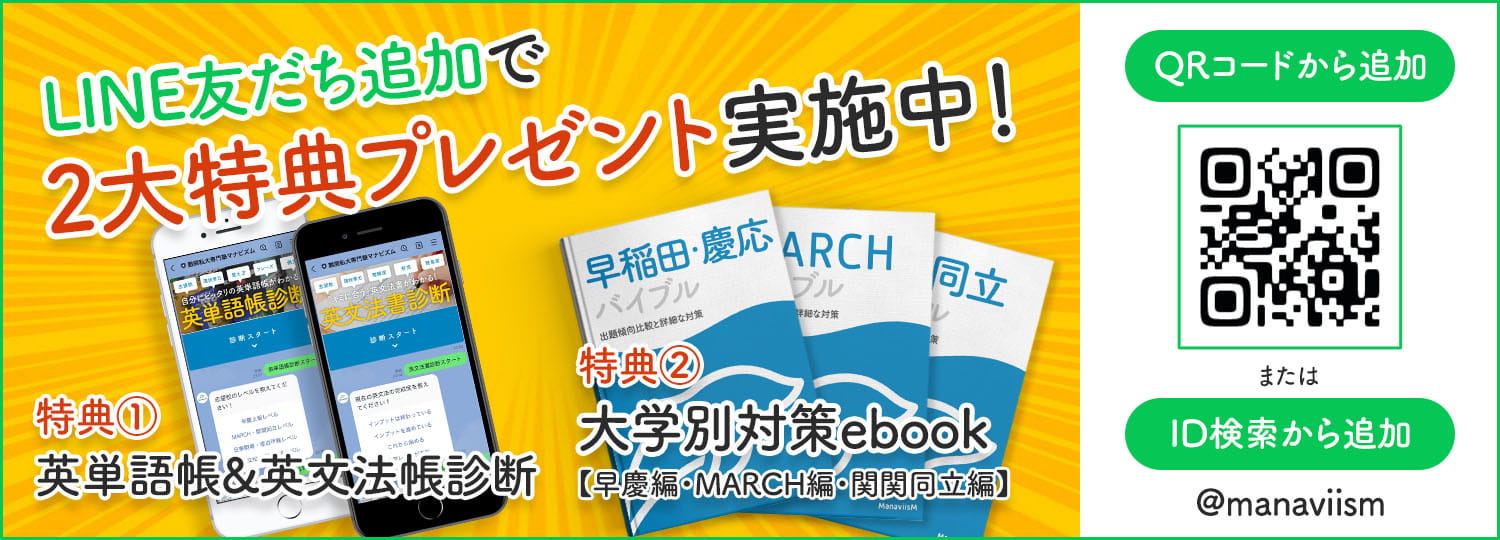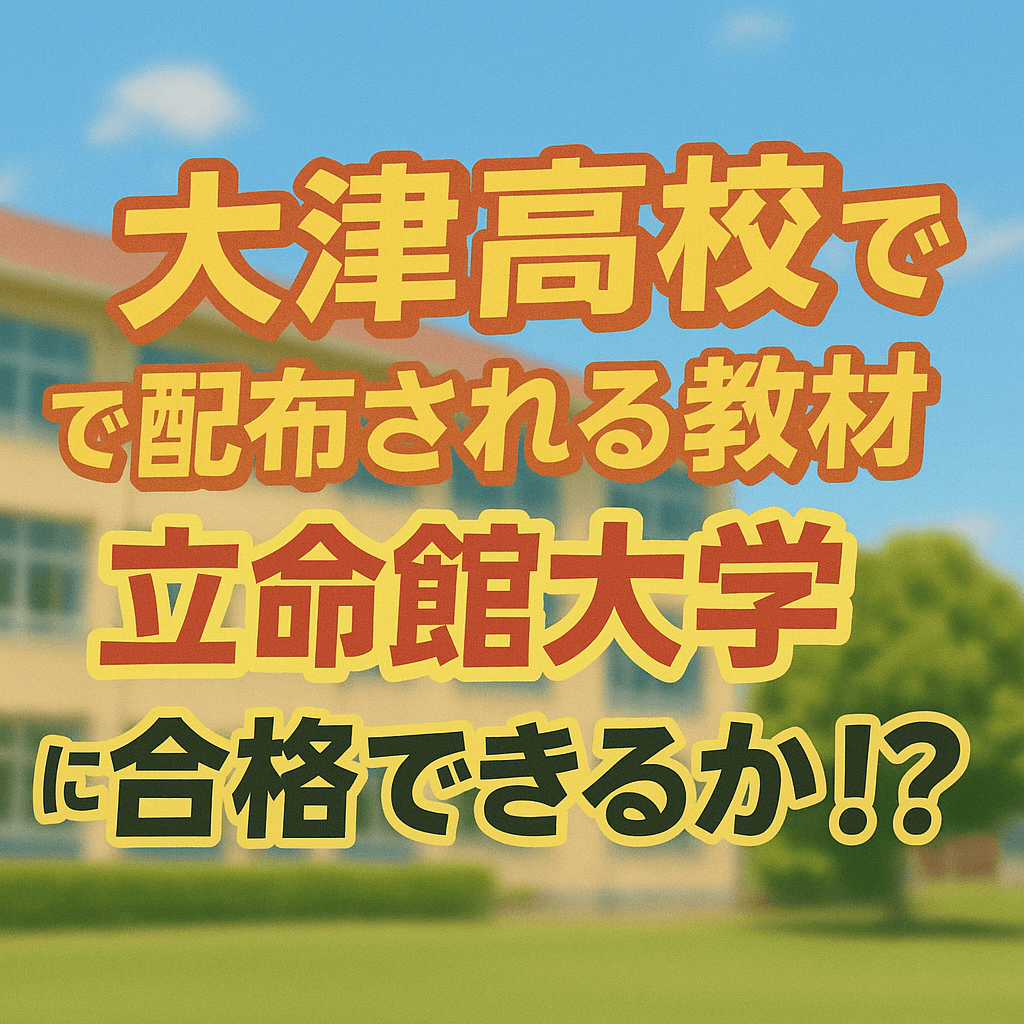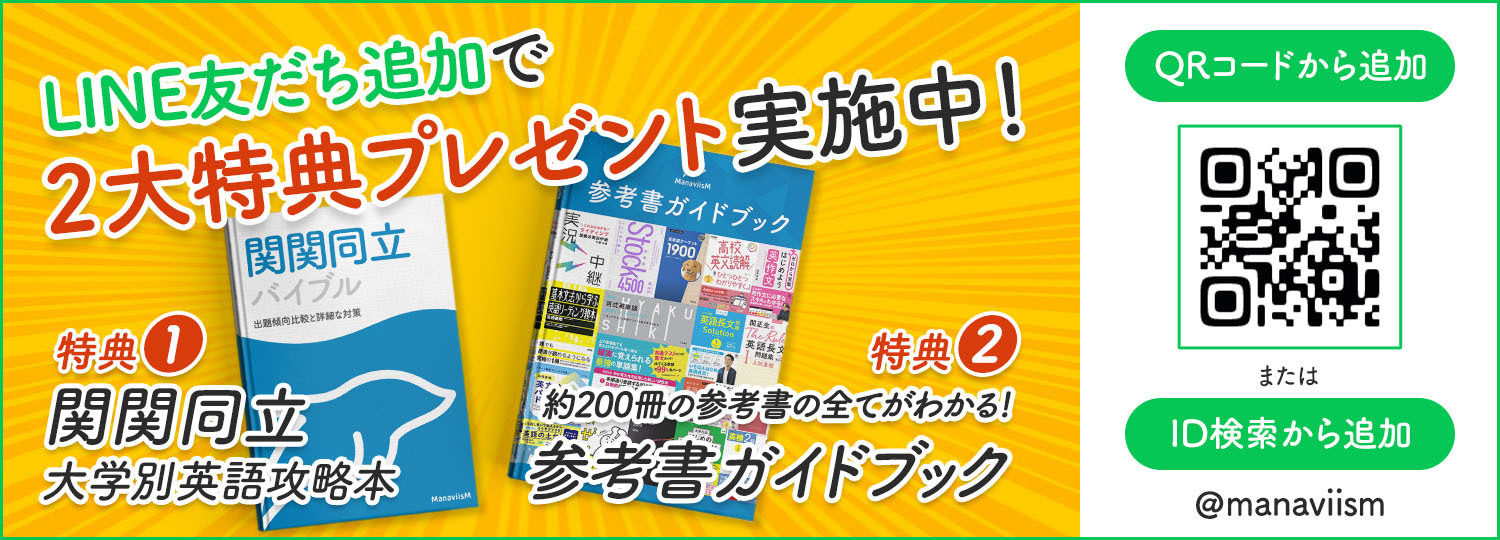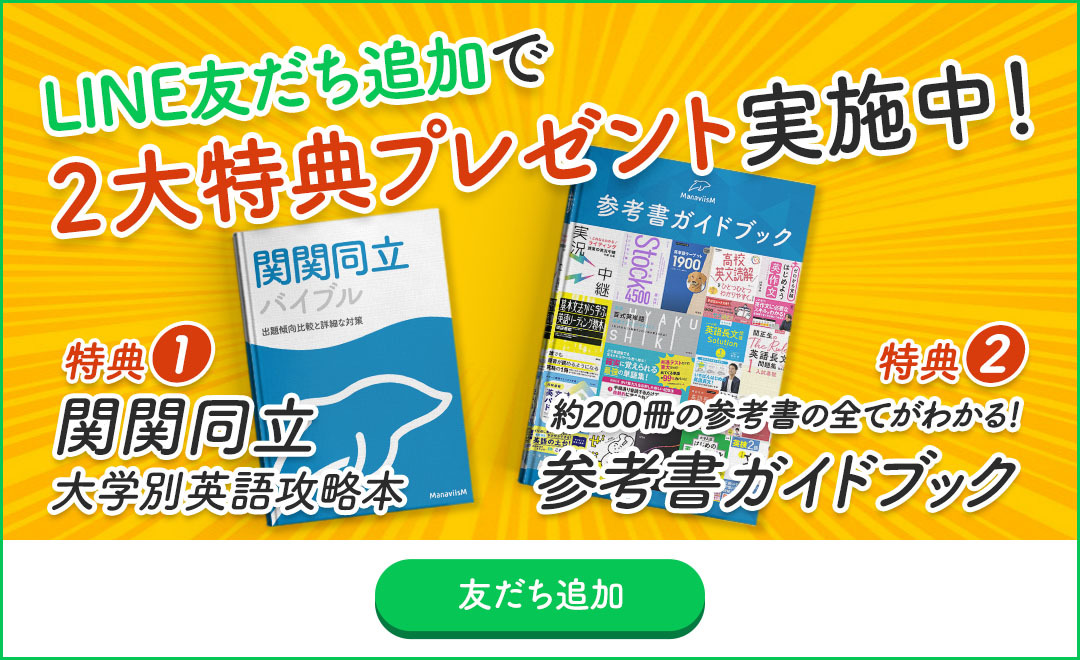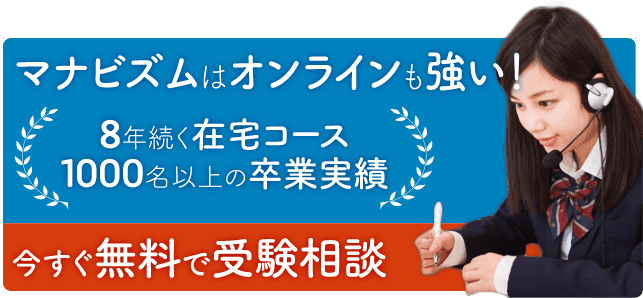【関関同立志望】英語参考書は“1冊を極める”が合格の近道!
更新日: (公開日: ) BLOG
こんにちは!マナビズム草津校です!
今回は「関関同立志望の受験生にとって、英語参考書はどう使うべきか?」というテーマでお話しします。
関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)を目指す多くの受験生にとって、英語はまさに合否を分ける最重要科目。
だからこそ「どの参考書をやるべきか?」「何冊やれば合格できるのか?」
と迷う人は多いですよね。
でも結論から言うと――参考書の数ではなく、正しい使い方で1冊をやり切ることが最強の戦略なんです。
参考書は「数」より「使い方」
「たくさんの参考書をこなさないと合格できない」と思っている人は少なくありません。
書店に行けば「速読英単語」「英語長文ハイパートレーニング」「ターゲット1900」など人気参考書がずらりと並び、どれも「これで完璧!」と書かれているのでつい手を出したくなります。
しかし、動画内でも繰り返し言われていたのが、
どんな参考書も正しい使い方をすれば必ず力になるということ。
逆に、目的を理解せずに「やった気」になってしまうと、
いくら数をこなしても成績は伸びません。
特に英語は「基礎の定着」から「長文読解力の養成」まで段階的に積み上げる科目です。
基礎が抜けたまま難しい問題集に飛びついても、ただの消化不良になるだけ。
「基礎レベルの徹底」がカギ
関関同立レベルの英語を解くためには、まず「基礎レベル」を徹底的に固める必要があります。ここでいう基礎とは、
- 単語・熟語の暗記
- 文法・構文理解
- 精読の習慣化
です。
特に注意したいのは「基礎=簡単」と思ってしまうこと。
動画の中でも「基礎レベルを本当に使いこなせる受験生はごく一部」と指摘されていました。つまり、**基礎は“できて当たり前”ではなく“極めるべき土台”**なんです。
おすすめは「特訓リーディング」
では具体的にどの参考書をやるべきか? 動画で紹介されていたのが「特訓リーディング」という一冊です。
この本の魅力は、
- 問題量がしっかりある
- 解説が非常に丁寧
- 基礎から応用へステップアップできる構成
という点。
「特訓リーディング」を1冊やり切れば、関関同立レベルの長文読解に必要な“基礎力+読解の型”を習得できます。複数の参考書に手を出すのではなく、この1冊を完璧に仕上げることが、最短の合格ルートになるわけです。
「目的意識」を持って取り組む
ただし、参考書は“やり切れば自動的に力がつく”わけではありません。大切なのは、その参考書をやる目的を理解することです。
- この本を終えたら、どんな力が身につくのか?
- 1日あたり何ページ進めるべきか?
- 復習はどういうサイクルで回すか?
こうした意識を持って取り組むことで、学習の質が一気に変わります。
「人気だから」「先輩が使ってたから」ではなく、自分の弱点を補うために選ぶことがポイントです。
演習は「やり方」で差がつく
最後に強調されていたのが、演習のやり方です。
実は約98%の受験生が、演習を“間違ったやり方”でやっているそうです。ありがちなのが、
- 解いたら丸つけして終わり
- 間違えた問題を軽く読み直すだけ
- 次の問題集にどんどん移ってしまう
これでは力は伸びません。
正しい演習法は、
- 問題を解く
- 徹底的に復習し、なぜ間違えたかを分析
- 解説を読み込み、正しい解法のプロセスを理解
- 時間を置いて再度解き直す
このサイクルを繰り返すことです。まさに「1冊を極める」姿勢がここでも重要になります。
まとめ:英語参考書は“相棒”にせよ
関関同立を目指すなら、英語の参考書選びで迷う必要はありません。大事なのは――
- 参考書の数ではなく、正しい使い方
- 基礎レベルを徹底的に仕上げる
- 「特訓リーディング」1冊をやり切る
- 目的意識を持って取り組む
- 演習は徹底復習+解き直し
この5つを意識すれば、英語の力は必ず伸びます。
受験勉強は「量」ではなく「質」で勝負するもの。あなたもぜひ、自分に合った1冊を“相棒”にして、合格まで走り抜けてください!
参考動画