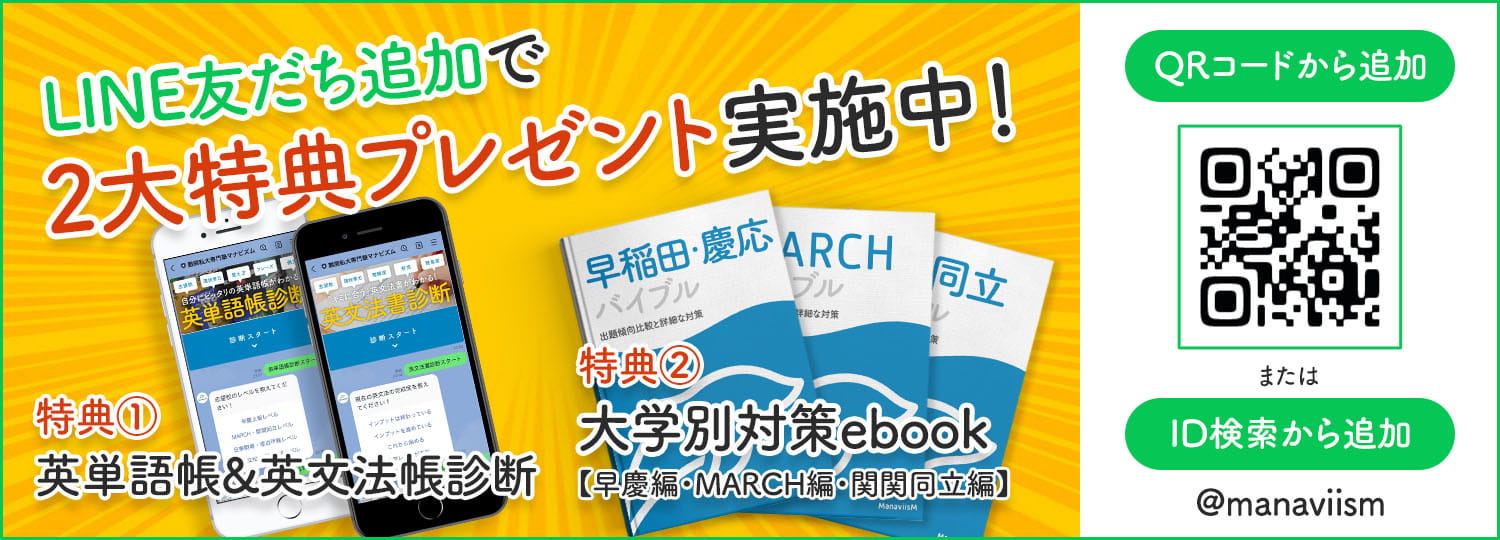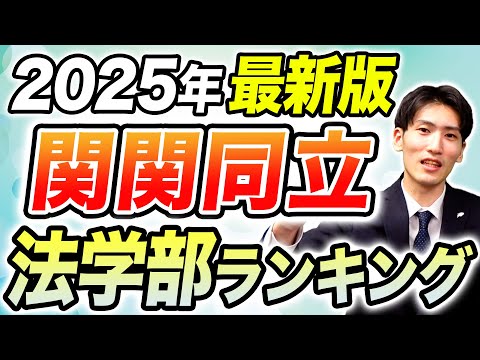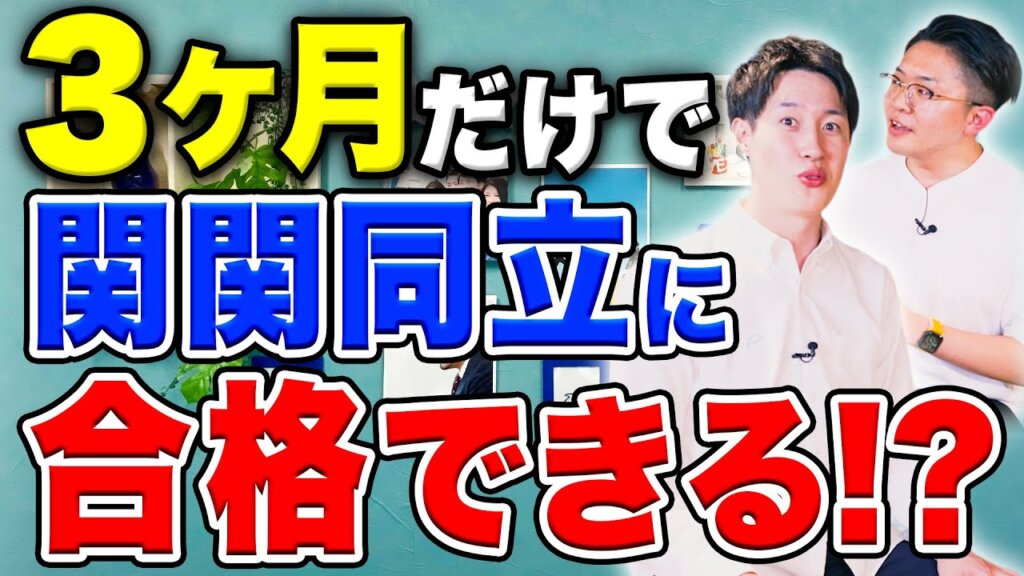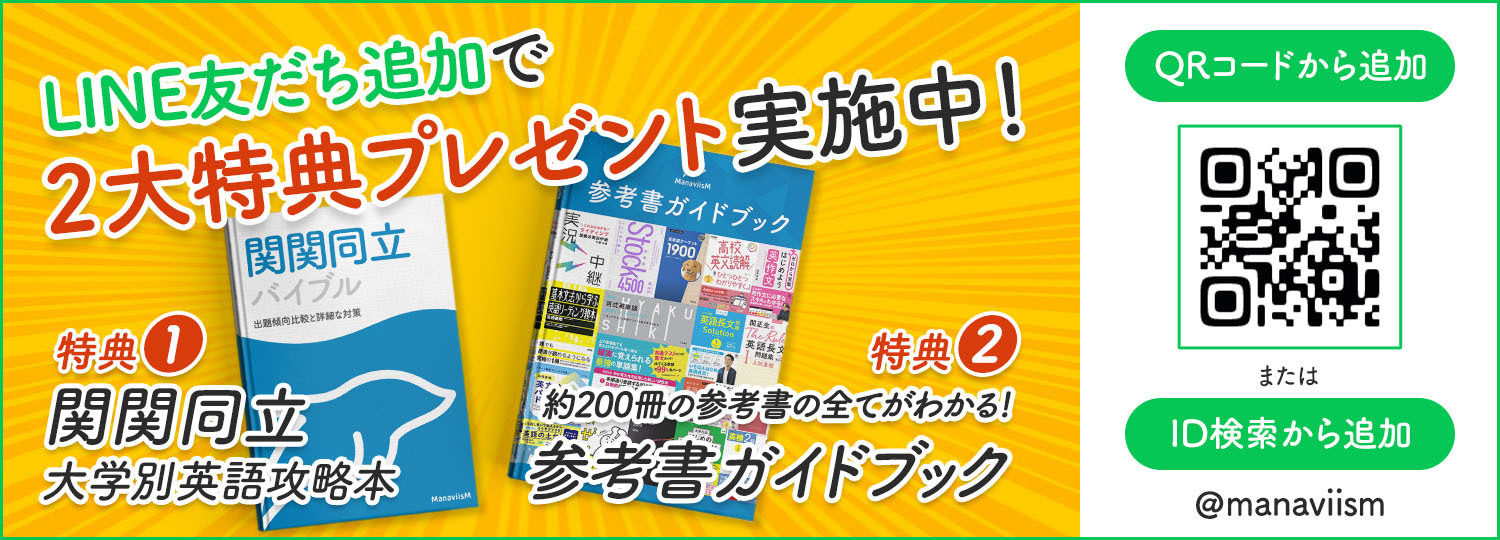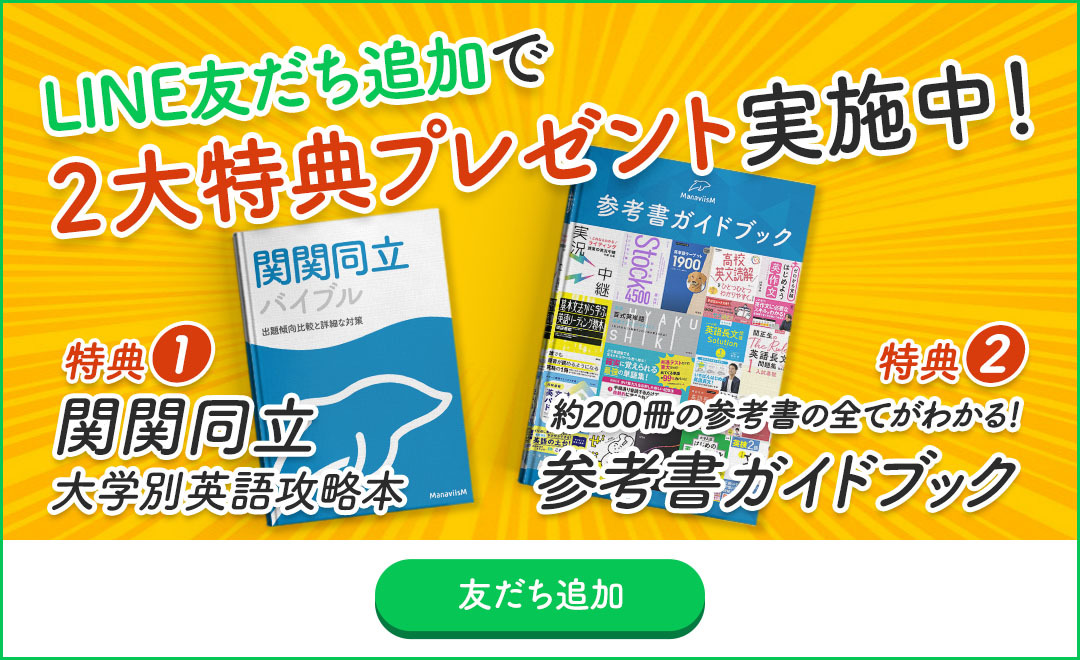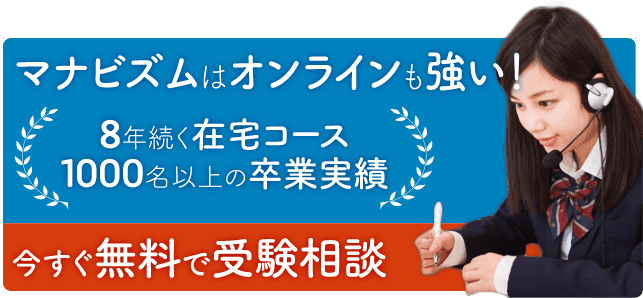【受験勉強の盲点】「基礎固め」を甘く見た受験生が、夏以降に伸び悩む理由
更新日: (公開日: ) BLOG
こんにちは!マナビズム草津校です!
受験生からよく聞かれる質問があります。
「そろそろ過去問やりたいんですけど、いつから演習に入ればいいですか?」
この質問、特に6月以降になると急増します。
模試が増え、周りも「問題集演習」や「長文読解」に走り出す時期だからこそ、焦りが生まれるんです。
でも、結論から言えば、“基礎が抜けたまま演習に突入する”のが一番危険です。
■「基礎=簡単」ではない。合格者ほど“基礎を深く理解”している
多くの受験生は「基礎」と聞くと、“簡単なこと”“もうできていること”だと思い込みます。
でも、トップ層ほど基礎を「深く・正確に・速く」扱えるんです。
たとえば英語。
単語・文法・構文の精度が甘いままだと、どれだけ長文を解いても伸びません。
模試で読むスピードが遅い、設問に迷う、選択肢を最後まで絞り切れない
こうした“もやもや”の正体は、ほぼすべて「基礎の理解が浅い」ことにあります。
数学も同じです。
基礎問題精講レベルの「なぜその公式を使うのか」が説明できない人は、応用問題で確実に詰まります。
「解けた」「正解だった」という表面的な理解ではなく、「なぜそうなるのか」「ほかのパターンにも使えるか」を意識して初めて“基礎が定着した”状態になるのです。
■夏に伸びない人の共通点:「演習量」だけを増やしている
夏以降、伸びない受験生の多くは「基礎の棚卸し」をせずに、問題演習へ突っ走ります。
たしかに量をこなせば“やった感”は出るし、安心感も得られます。
でも、いくら数をこなしても、土台がズレたまま積み上げれば、成績は頭打ちになるんです。
模試で「この問題、見たことあるのに解けない」という現象、心当たりありませんか?
それは記憶の定着ではなく、「解法の丸暗記」で止まっている証拠です。
“自分の頭で考えて理解した基礎”でなければ、問題が少し変わった瞬間に通用しません。
■じゃあ、どうやって「基礎固め」をすればいいのか?
ポイントは3つです。
- 「分かった」ではなく「説明できる」までやる
教科書や参考書を読んで理解した気になっても、それは“錯覚”。
自分の言葉で説明できるか、類題で再現できるかをチェックしよう。
たとえば英単語なら「品詞+例文」で覚える、数学なら「この解法を選んだ理由」を口に出して整理する。 - 同じ教材を“深く”何周もやる
1冊の基礎参考書を完璧にすることが、偏差値60〜65への最短ルート。
「1冊目→2冊目→3冊目」と浮気するより、「1冊を4周」するほうが100倍強い。
忘れかけた頃に復習して、「即答できる」状態を作ることが大切。 - 「何が苦手か」を具体化する
ただ「英語苦手」では改善しません。
“文法の比較が弱い”“数学のベクトルで符号をミスる”など、細かく言語化することで復習効率が上がります。
苦手を“感覚”ではなく“事実”で把握するのがポイントです。
■演習に入るのは、基礎を「自動化」できてから
本格的な演習に入るタイミングは、「基礎問題をほぼ考えずに正答できる状態」になったとき。
つまり、思考のリソースを“応用問題に使える”状態が理想です。
そこまで来て初めて、過去問演習や模試の復習が「伸びる時間」になります。
焦って演習に走るよりも、基礎を徹底的に磨いた方が、最終的な伸びは圧倒的。
受験の勝敗は“夏の演習量”ではなく、“春からの基礎の深さ”で決まります。
■まとめ
「基礎固め」は地味で退屈に見えるかもしれません。
でも、最終的に関関同立やMARCHレベルに受かる人は、例外なく基礎が盤石です。
彼らは「難しい問題ができる」から強いのではなく、“簡単な問題を完璧にできる”から強い。
あなたが今やっている「基礎固め」は、数ヶ月後の自分への最大の投資です。
焦らず、丁寧に、一つひとつ積み上げていきましょう。