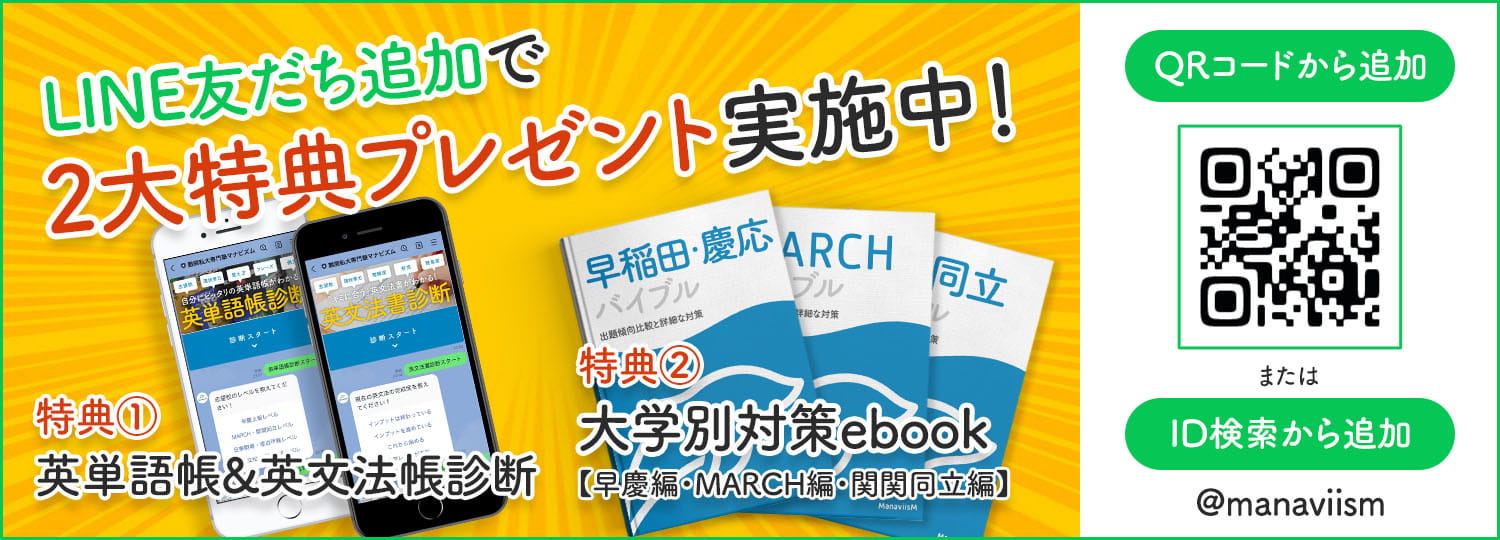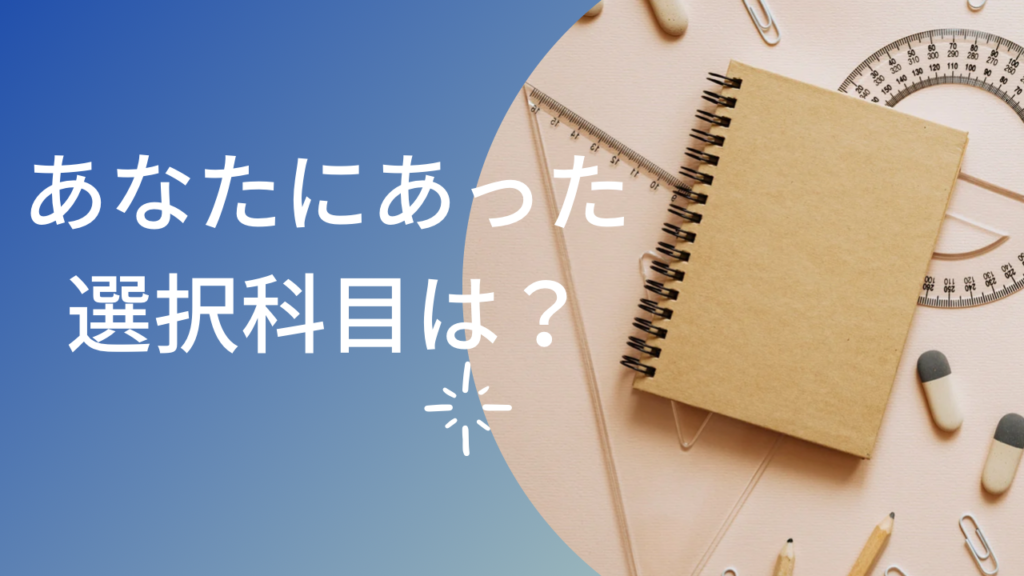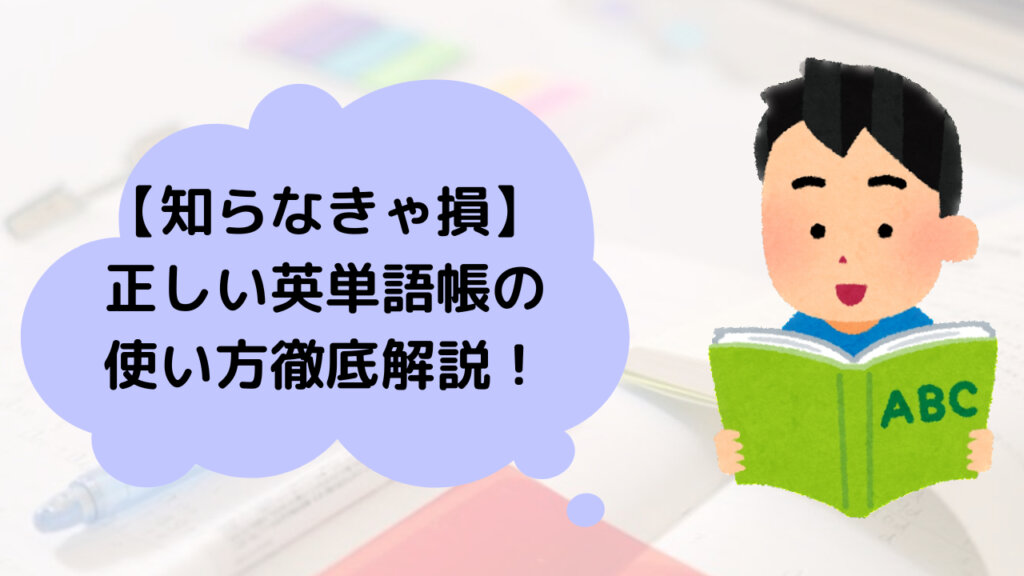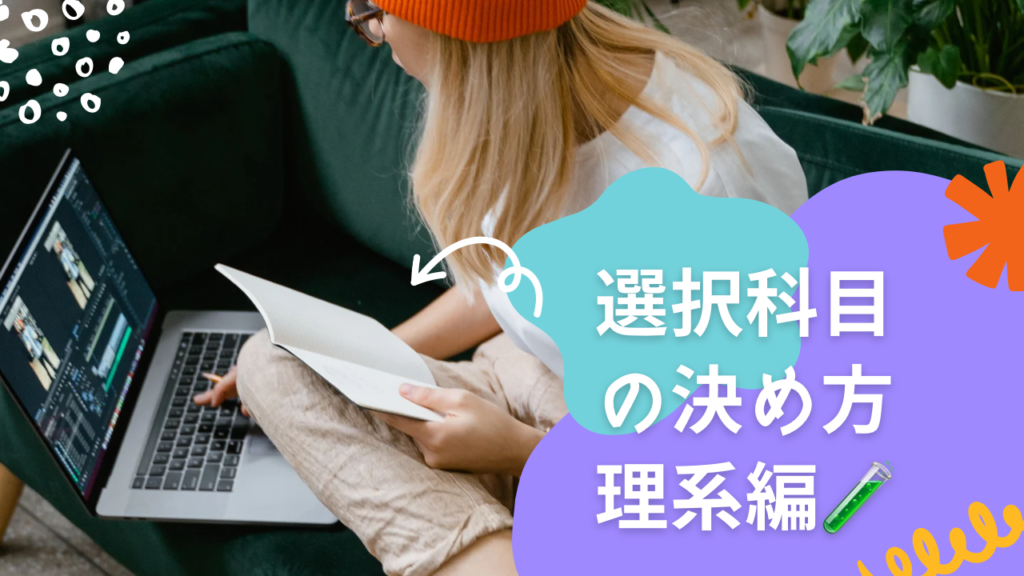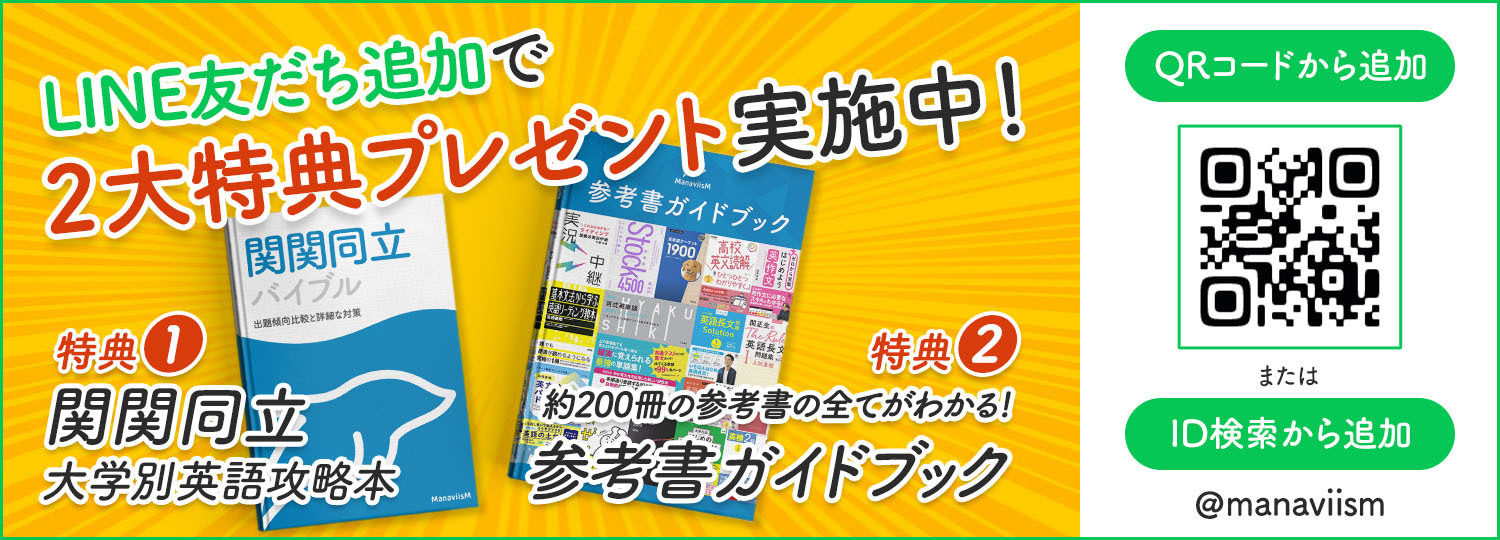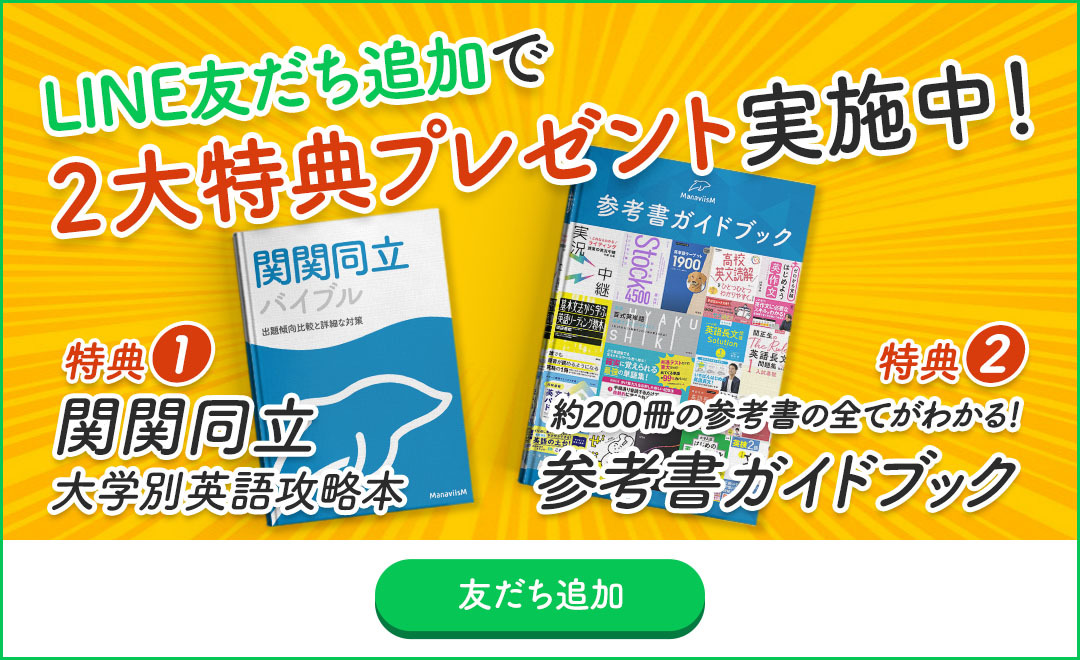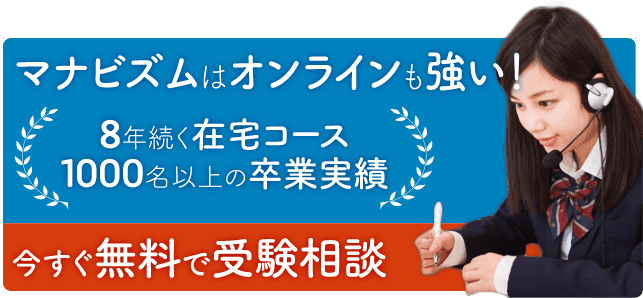【要注意】「〇〇大の英語」参考書は必要なのか?赤本・黄色本・青本の違いまで徹底解説
更新日: (公開日: ) BLOG
大学受験が本格化する秋以降、受験生の間でよく話題に上るのが
いわゆる 「〇〇大の英語(〇〇大の国語など)」と書かれた大学別参考書シリーズは使うべきなのか? という問題です。
本屋に行くと、同志社・関大・立命館・早稲田など、大学名がタイトルに入った問題演習系の参考書がズラリと並びます。しかし、これらは本当に必要なのか?赤本とどう違うのか?そしてどれが最も効果的なのか?
今回は,大学別参考書の「必要・不必要」を受験生目線で詳しく解説していきます。
■ 結論:必要か“不必要か”で言えば「不必要」。ただし“あってもよい”
結論は非常にシンプルです。
- 必要か不必要かの二択なら“不必要”
- ただし「絶対にやるべきではない」という意味ではなく、
目的が合っているなら“あってもよい”
つまり、使ってもいいけれど、使わなくても全く問題はないというスタンスです。
ではなぜこう言い切れるのか。
理由は「直前期に最も大事な勉強」が、別に大学別参考書ではないからです。
■ 直前期に最重要なのは「過去問分析」だけ
受験生が最後の2〜3ヶ月で最も成績を伸ばせるのは、
過去問を解く → 分析する → 改善の仮説を立てる → 再挑戦する
このサイクルです。
過去問の点数が伸びる受験生は、この分析力が高い。
逆に伸びない受験生は、どれだけ良い解説書があっても伸びません。
ここで問題となるのが「赤本の解説が薄い」という声。しかし、これは“構造上仕方がない”問題です。
赤本は
- 入試が2〜3月
- 出版が6月
という極端なスケジュールの中で大量の大学を扱う必要があるため、どうしても解説が薄くなります。
しかし、これは本質的な問題ではありません。
本来の基礎力ができている受験生は、赤本の薄い解説からでも大量の学びを得られる。
逆に、どれだけ分厚い説明があっても伸びない人は伸びない。
つまり、成績を上げる鍵は参考書ではなく「分析力」です。
■ では“〇〇大の英語(黄色本)”は何が違うのか?
大学別参考書(いわゆる黄色本・赤版など)は、赤本とは目的が異なります。
● 赤本の目的
- 過去問の分析・戦略決定
- 傾向を掴み、何が足りないか明確にする
● 〇〇大シリーズ(黄色本・赤版)の目的
- 自分の志望校の形式で演習を積む
- 過去問とは別の角度からアウトプット練習
目的がまったく違うので、
「黄色本をやってるから赤本やらなくていい」
という使い方は完全にNG。
この目的を理解しないまま使うと、勉強効果は極端に低くなります。
■ 黄色本と赤版、どっちが良い?
これは大学や著者によって質が違っており、一概にどちらが良いとは言えません。
- 著者の力量に差がある
- 改訂時に著者変更されることがある
- 大学ごとの相性がある
ただし
黄色の方が良いことが多い。
とはいえ、絶対ではありません。最大のポイントは「自分が何の目的で使うのか」です。
■ ただし早慶だけは“青本が圧勝”
例外として、早慶志望なら
青本(駿台)一択
と明確に言われています。
駿台講師が本気で書いた解説は非常に質が高く、早慶レベルの受験では強力な武器になります。
■ そもそも「なんとなく」選ぶのが一番ダメ
参考書選びで最も危険なのが、
- ルートに乗ってるからやってる
- 先輩におすすめされた
- みんなやってるから不安で買った
という“目的のない選択”。
大学別参考書はあくまで「志望校の形式に慣れる」道具であり、万人に必要なものではありません。
■ まとめ:必要かどうかは「目的」で決まる
最後にポイントを整理すると、
- 必要か不必要かで言えば“不必要”
- ただし目的に合えば“あってもよい”
- 成績を上げる本質は「過去問分析」
- 黄色本は演習目的、赤本は分析目的で全く別物
- 早慶志望のみ青本が最強
- 「なんとなくやる」は時間のムダ
参考書選びは“目的”がすべて。
自分が今どんな課題を抱えているのかを明確にした上で選択することが、
最短で成績を伸ばすための唯一の方法です。