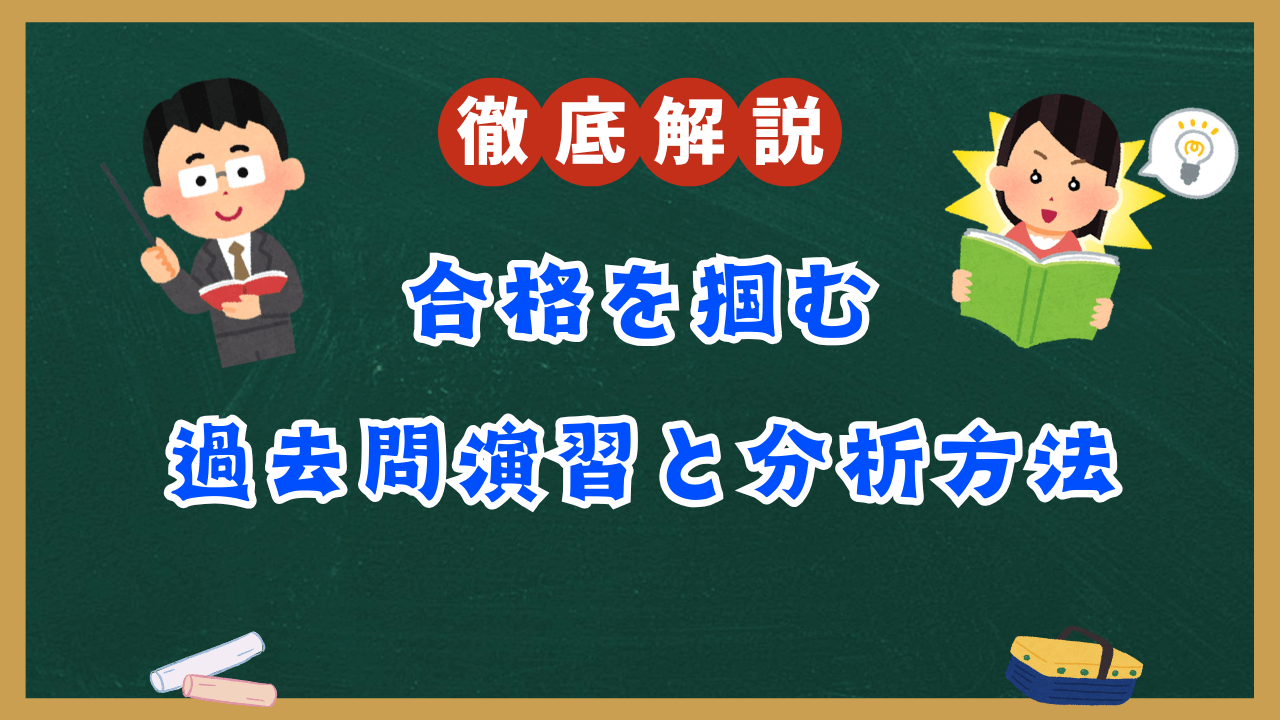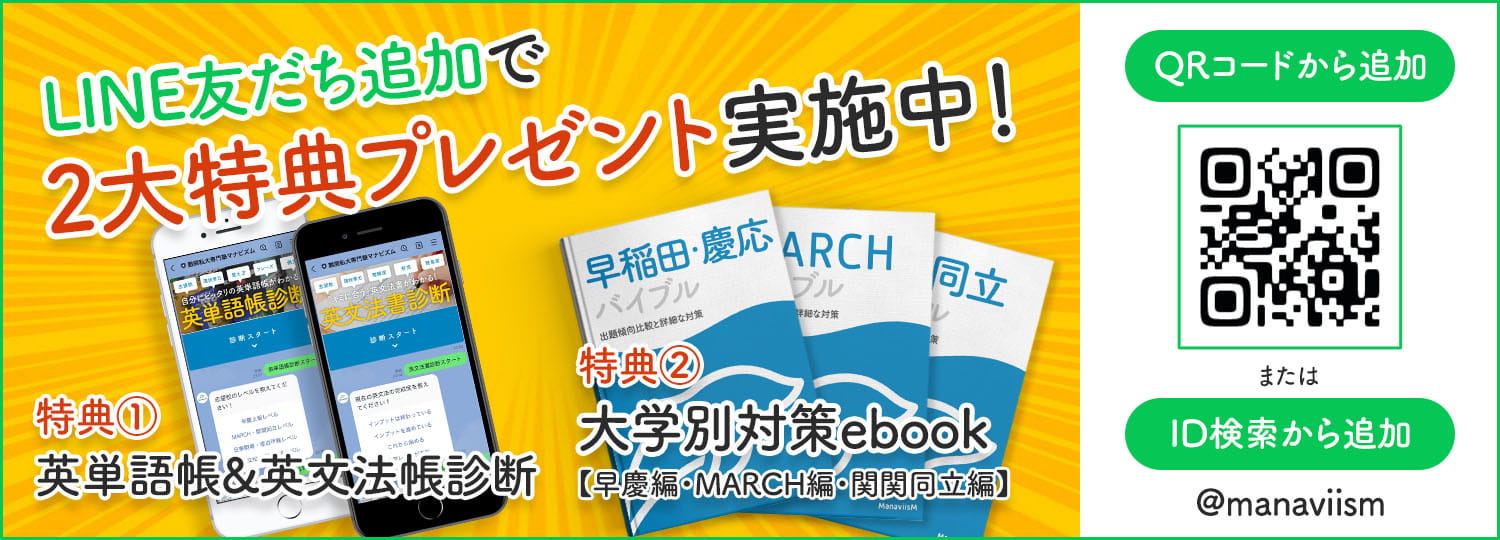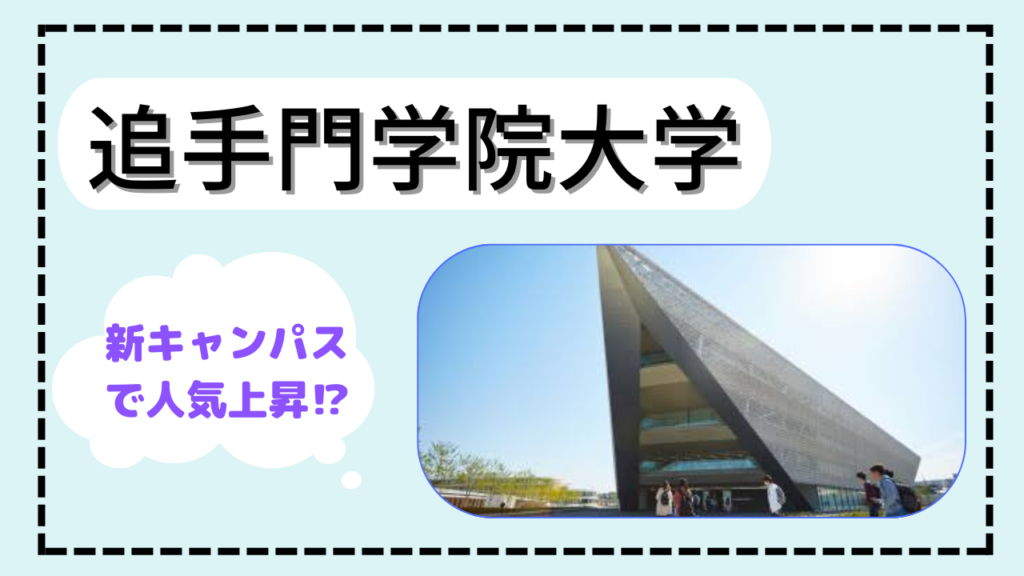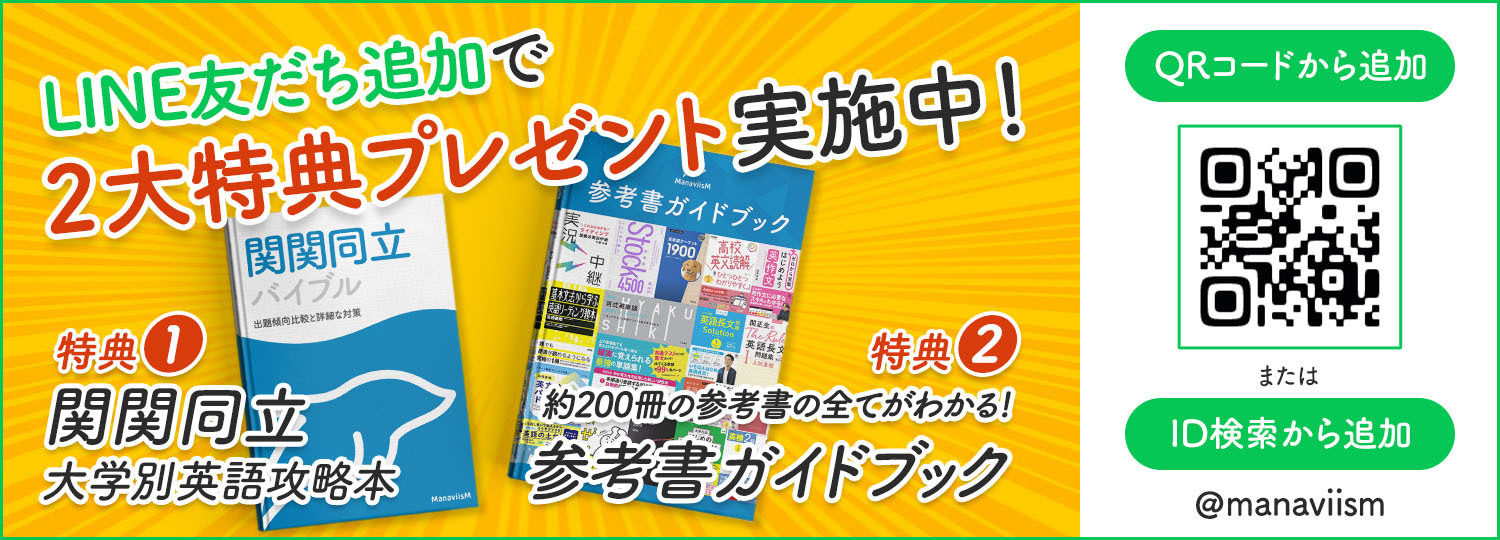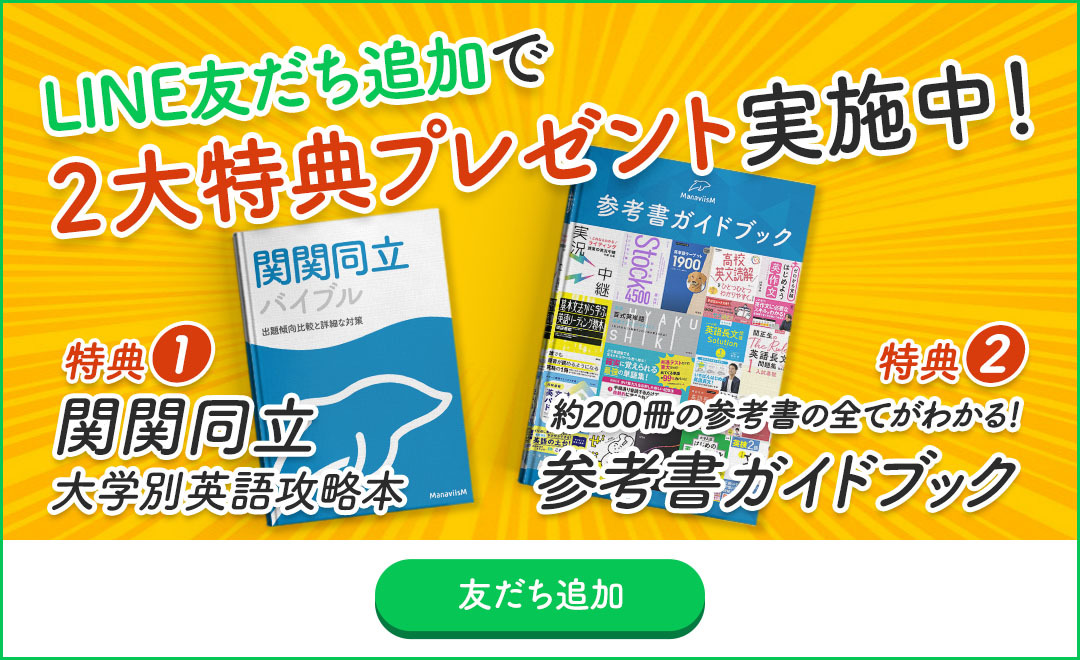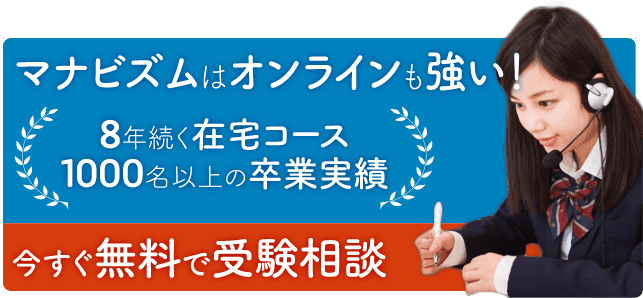【大学受験の羅針盤】”合格”を掴む過去問演習と分析方法大解説!
更新日: (公開日: ) BLOG
みなさん、こんにちは!
京阪枚方市駅「徒歩1分」💨
地域で圧倒的な関関同立・産近甲龍の合格率を誇る関関同立専門塾マナビズム枚方校です。
今回は…
「過去問演習とその分析方法のポイント」
について紹介していきます😁
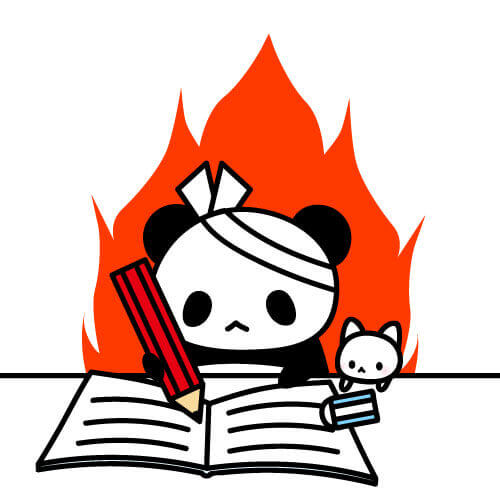
このように何となくで過去問をしている受験生はいないでしょうか?
もしいるのなら、非常にもったいないです。
過去問は、ただの力試しではなく、志望校があなたに何を求めているのかを教えてくれる『最強の羅針盤』です。そして、自分の弱点を明らかにし、今後の学習計画を立てるためのヒントを与えてくれます。
今回の記事では、過去問演習の真の目的から具体的な解き方、そして最も重要な『分析』の方法まで徹底的に解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
過去問演習の2つの目的

皆さん、この問いに明確に答えられますでしょうか…
「自分の実力を測るため」つまり合格最低点との差にしか着目していない受験生が毎年多く見受けられます。
もちろんそれも重要な目的ですが、過去問演習にはさらに深い2つの目的があります。
今回は、その2つの目的について詳しく紹介します。
最終の敵を知るため
過去問は実際の入試問題の過去問。つまり、受験勉強における「最終の敵」ともいえるでしょう。
この最終の敵でもある過去問で知ってほしい内容が3つあります。
- 時間配分:各大問にどれくらいの時間を割くべきか?
- 出題傾向:どの分野から、どのくらいの難易度で、どのような形式の問題が出題されるか?
- 求められる能力:基礎的な知識が重要か?応用的な思考力まで必要か?
これらの情報を知らなければ、今後の勉強計画をどうしていくかなどの分析のスタートラインにすら立てていません。必ず3つのポイントを考えるようにしましょう!
勉強計画を修正するため
過去問は、キミの「弱点」を客観的に教えてくれます。合格点に達しなかった場合、その原因が「知識不足」なのか「解き方の問題」なのか、あるいは「時間配分」なのかを分析することで、今後の学習で何をすべきかが明確になるでしょう。
闇雲に勉強するのではなく、過去問という「羅針盤」が指し示す方向へ進むことで、受験生のキミは最短距離で合格に近づくことができるのです!
過去問演習の頻度
前提として、ここでは「浪人を絶対しないと決めている現役生 & 今年で受験を終えると決めてる浪人生」を対象としています。
また、「年内中に合格最低点を出すことが出来るペース」でご紹介します。
今回は志望校を3つの種類に分けて考えるとよいでしょう。
- チャレンジ校:5回に1回合格最低点が出る。又は、合格最低点が出ていない。
- 実力相応校:5回に2~3回合格最低点が出る。つまり、過半数以上の確率で受かる大学。
- 滑り止め校:5回に5回合格最低点が出る。つまり、必ず合格できる保証がある大学。
| 月 | チャレンジ校 | 実力相応校 | 滑り止め校 | チャレンジ校の目標点 |
| 9月 | 1~2回/月 上旬・下旬に1回ずつ |
1~2回/月 | 1回/月 | 合格最低点-40~50点 |
| 10月 | 1~2回/月 中旬・下旬に1回ずつ |
1~2回/月 | 1回/月 | 合格最低点-30~40点 |
| 11月 | 2~3回/月 2週間に1回 |
2~3回/月 | 2回/月 | 合格最低点-10~20点 |
| 12月 | 4回/月 毎週1題 |
3~4回/月 | 2回/月 | 合格最低点-10点 合格最低点に到達 |
| 1月 | 4~5回/月 毎週1題以上 |
3~4回/月 | 2回/月 | 合格最低点に到達 |
公募推薦入試で実力相応校や滑り止め校の合格を確保できている場合は、チャレンジ校の過去問は2週間に3題ぐらいのペースに増やして演習をしていくとよいでしょう。
過去問演習5つのステップ
解く前にすべき戦略立案
過去問を解き始める前に、まず以下の3つを決めましょう。
- 目標点数
合格最低点を調べ、どの科目で何点取るのかを具体的に設定します。 - 時間配分
各大問に何分かけるかを決め、時間内に解き終えるためのシミュレーションを行います。 - 5分短縮
本番で焦ることやマークシートを塗る時間を差し引て、過去問は制限時間より5分短く設定してましょう。
本番と同じ環境で解く
入試本番は非日常的な環境のため緊張などで実力が出せない可能性が考えられます。そのような状態になるリスクを最小限に抑えるために、入試本番と環境を合わせれるものは合わせて過去問演習を行いましょう。
- 全科目を連続で
集中力が続く時間帯を選び、本番と同じように全科目を連続で解きましょう。これにより、入試本番での体力と集中力のマネジメントを練習できます! - 中断しない
途中で休憩したり、スマホを触ったりせず、最後まで集中して取り組みましょう。 - 実際の時間割通りに
実際の入試時間割通りに過去問を解きましょう。そうすると丸一日かかるので日曜日の朝からすることをおススメします。 - 本番で使う腕時計で
最近はスマホで時間を確認することがメジャーになっていると思います。しかし、入試本番は慣れていない腕時計になるので、本番を想定して腕時計で過去問演習をしましょう。また、アナログかデジタルのどちらが使いやすいかも考えてみましょう!
丸付けと失点の原因の特定
- すぐに答え合わせ
全て解き終えたら、思考のプロセスを覚えている間に、すぐ丸付けを行いましょう。 - 3つのマーク
単に正誤を確認するだけでなく、以下の3つに印をつけます。
A:完全に正解し、自信のある問題
B:正解したが、根拠が曖昧な問題
C:不正解だった問題
丁寧な解き直しと復習
過去問分析の鍵は、この丁寧な解き直しと復習から始まります。
- 「C」の問題を解き直す
解説をすぐに見るのではなく、もう一度、自分の力で解き直してみましょう。ここで解けた問題は、知識はあったが、考え方が間違っていた可能性が高いです。
- 「B」の問題を再度考える
Bの問題の根拠を時間無制限の状態で再度考えてみましょう。 - 解説を熟読する
解説をただ読むだけでなく、なぜその答えになるのか、その解法に至る思考プロセスを理解するように努めましょう。
分析と学習計画へのアクション
- 分析ノートの作成
大問ごと、分野ごとに、どの問題で何点失点したかを記録し、分析等も記入しましょう。 - 弱点克服計画
分析結果に基づいて、「単語力が不足している」「古典文法が曖昧だ」といった具体的な課題を特定し、今後の学習計画に反映させます。
過去問分析5つのポイント
「なぜ間違えたのか」をさらに深掘りするための、5つのチェックポイントをご紹介します。
「知識不足」 or 「思考力不足」?
単語や公式を知らなかったのか、それとも解法は知っていても、それを応用する力が足りなかったのかを明確に区別しましょう。前者は暗記で解決できますが、後者はより多くの演習が必要です。
正解の選択肢にも「なぜ」を問う
正解した問題でも、なぜその選択肢が正解で、他の選択肢が間違いなのか、その根拠を本文中から見つけ出しましょう。この作業が、本番で迷ったときに正解を導き出す力を養います。
時間配分が適切だったか?
どの問題に時間をかけすぎてしまったかを振り返り、次に同じような問題に出会ったときに、解き進めるか、潔く捨てるかの判断を練習しましょう。入試は満点を取る戦いではありません。
得点戦略が適切だったか?
「得意科目で点を稼ぐ」などの戦略が過去問で機能したかを確認します。もしうまくいかなければ、戦略の見直しが必要です。
解説の行間を読む
多くの受験生が解説を「答え」としてしか見ていません。しかし、解説の背景にある解法のプロセスや、思考のステップこそが最も重要ですべきことです。解説を鵜呑みにせず、なぜその解法に至るのかを自分で言語化する癖をつけましょう。
科目別過去問分析の方法
科目別に過去問分析のポイントを軽く紹介します。ぜひ参考にしてください。
英文法
①4択問題
選択肢を見て、どの文法単元から出題されているかを特定します。なぜその選択肢が正解で、他の選択肢が間違いなのかを明確にしましょう。
②整序問題
構文が問われてるかどうかと日本語が意訳されているかどうかを確認しましょう。日本語が意訳されている場合は、並び替える単語等を参考にしながら、主語や動詞を特定し、英文解釈的に矛盾がない文を作りましょう。
また、両方の問題に共通して言えることは、間違えた単元はインプット教材で全て総復習しましょう。その際に、典型表現・構文か演習をメインに復習するかは失点の原因を参考にして行いましょう。
英語長文・現代文
「読み」と「解く」に分けて分析を行いましょう。
①「読み」
なぜ筆者がそう主張しているのか、その論理的なつながりを意識しながら読み解きます。
②「解く」
全ての選択肢について、なぜそれが正解・不正解なのか、本文中の根拠を明確に説明できるようにします。
また、英語長文でよくある正誤問題は、間違えの根拠としてよくパターンに当てはまっていないかも確認しましょう。
- 否定と肯定のすり替え
本文では否定されている内容が、選択肢では肯定されている。 - 因果関係のすり替え
原因と結果が逆になっている。又は、原因を本文の全く別の箇所から持ってきている。 - 部分的な一致
選択肢の一部は正しいが、全体としては本文と異なっている。 - 抽象と具体のズレ
本文の具体的な内容が、選択肢では過度に抽象化されている、またはその逆。
古文
文章読解では、登場人物の心情や場面を想像しながら読み進めます。設問では、文法や単語の知識、古文常識で選択肢を絞り込めるかを確認します。
数学
数学の解き直しの手順は以下の3ステップで行ってから、分析を行いましょう。
- インプット教材を見ながら解き直し
インプットが完璧であれば解けるかどうか? - 解説を見て手を動かしながら熟読
インプットで学んだどの解法を使うのかに重点を置いて読む - 同じ問題を説明できるような基準になるまで解き直し
立式や解法の手順を人に説明できるレベルまで理解を深めることが大切
まとめ
今回は、過去問の演習方法と分析方法について詳しく解説させていただきました。

この言葉を意識して、今日から過去問演習にしっかり取り組みましょう!
無料受験相談&体験授業実施中
関関同立専門塾マナビズムでは、一人ひとりの実力と合格までに必要な能力を逆算し、オーダーメイドの勉強計画を作成いたします。

▢ 受験勉強何から始めたらいいか分からない🤔
▢ うまく勉強計画が組めない😥
▢ 今まで全く勉強してこなかった😯
▢ 最短で難関私大に合格したい🔥
▢ 参考書についてもっと知りたい😁
チェックが一つでも入った方は、ぜひマナビズム枚方校の無料受験相談へお越しください。
相談後すぐにでも勉強を始められるよう、親身に対応させていただきます!
👆マナビズムのサービスについての紹介動画👆
マナビズム枚方校ではInstagramにて校舎の日常を投稿しております!
ぜひ、気軽にご覧ください👀
この投稿をInstagramで見る