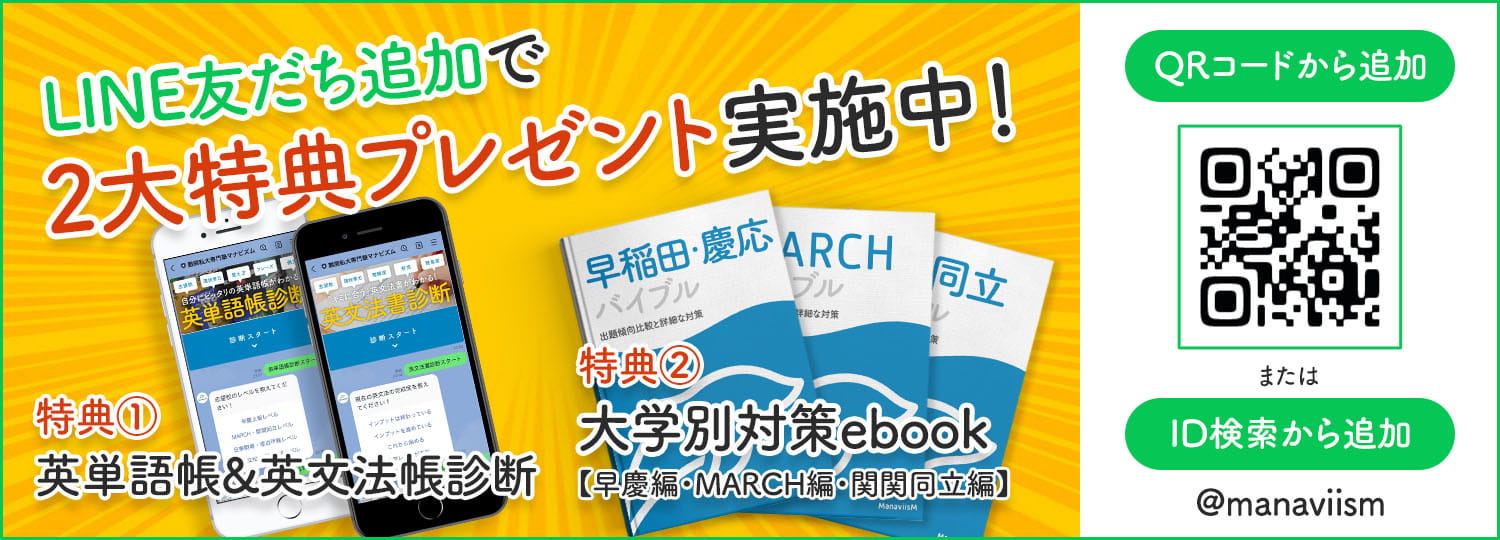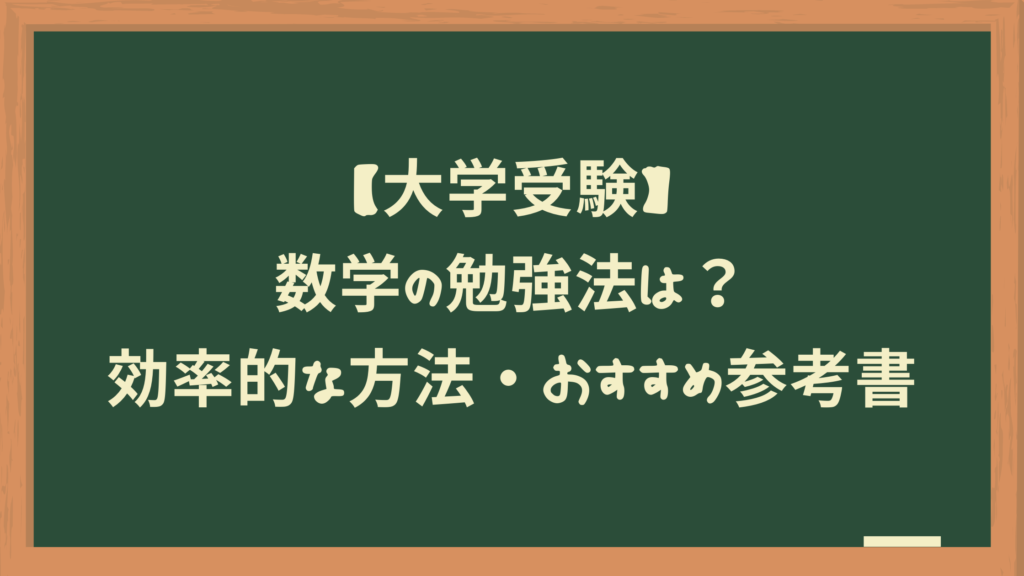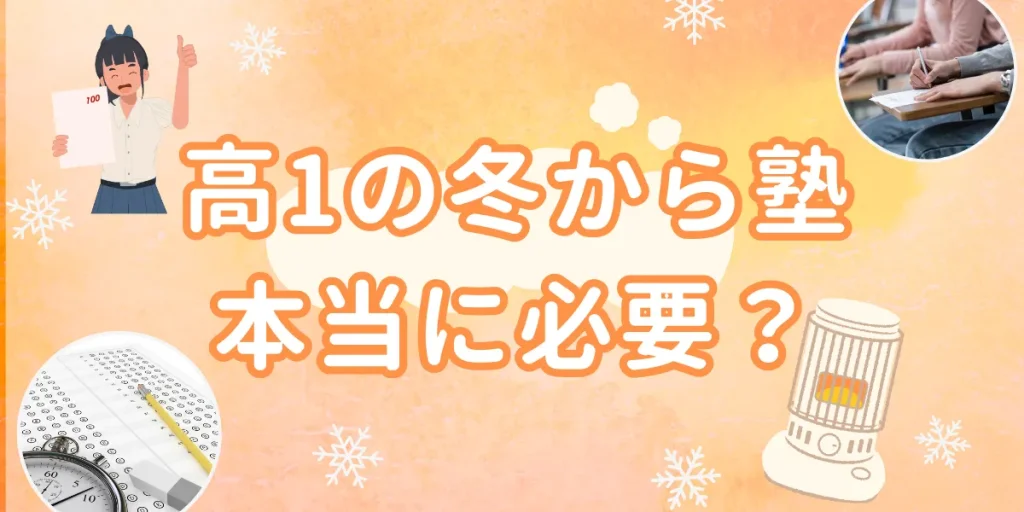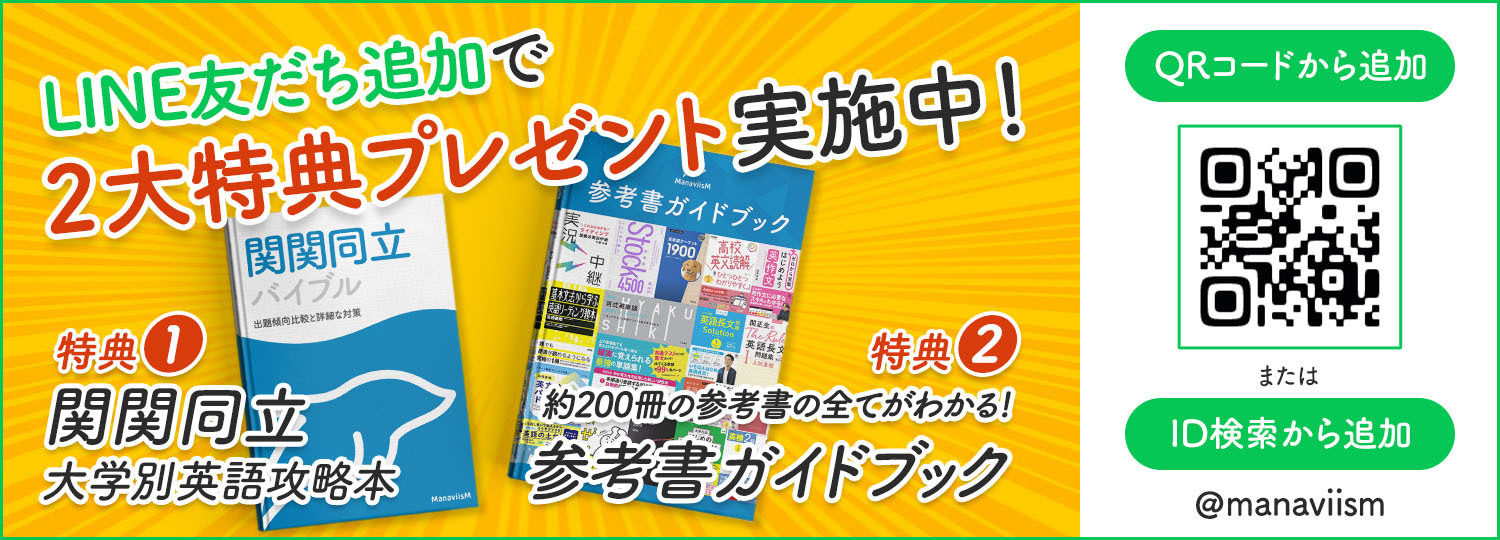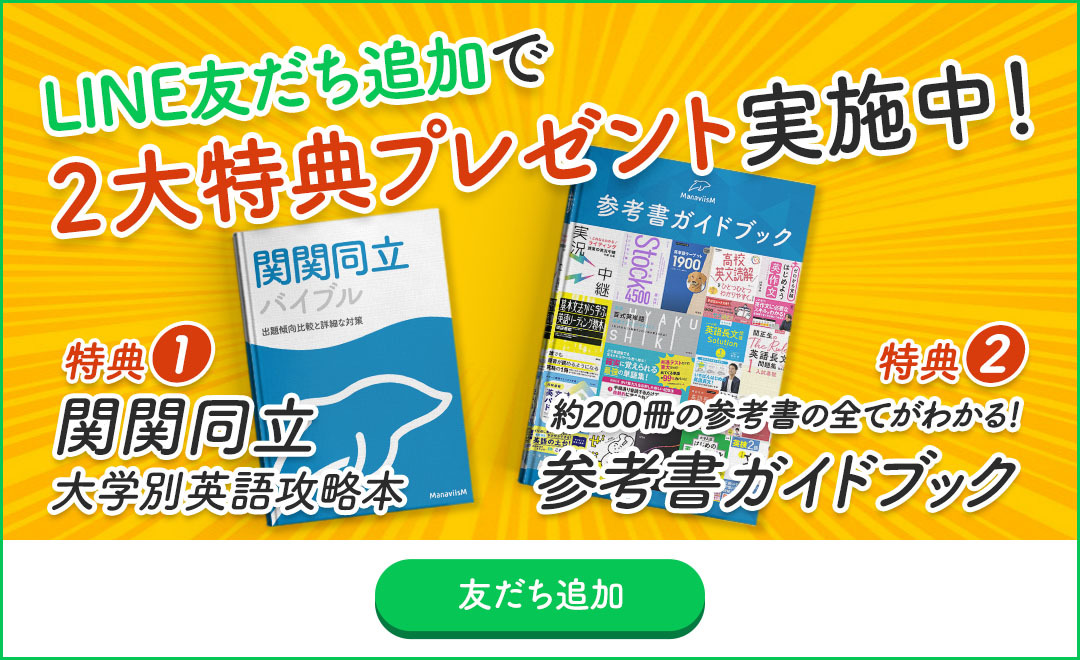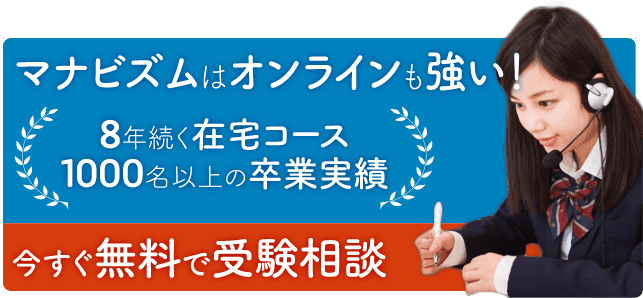関関同立の古文を大学別に解説!おすすめ単語帳や参考書の使い方も紹介
更新日: (公開日: ) COLUMN
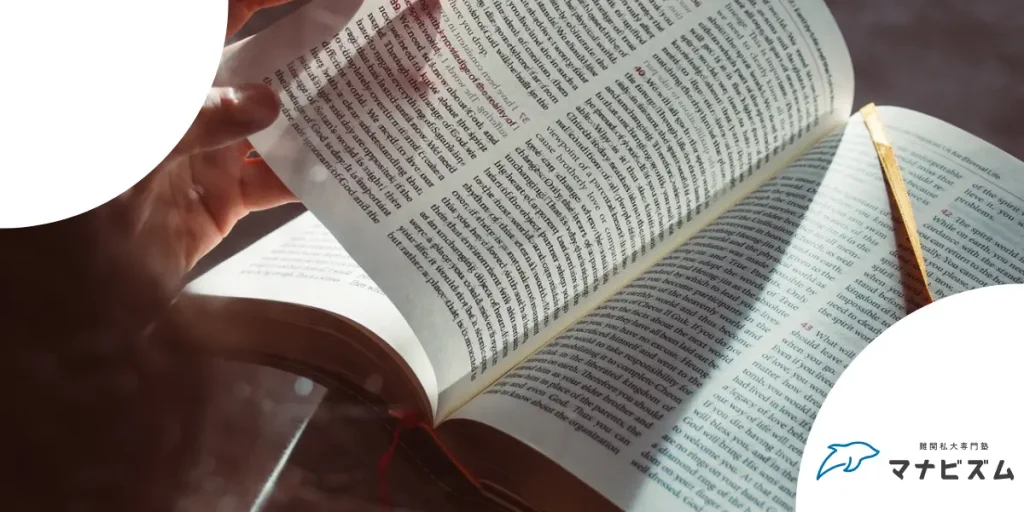
関関同立を目指す受験生の皆さん、古文に苦手意識はありませんか?
- 「そもそも何が書いてあるかわからない」
- 「主語がなくて、だれが・何をしているのか把握できない」
- 「適当に読み流してしまう」
- 「最終的にこの話は何が言いたかったのか理解できない」
このような最悪のスパイラルに陥っている受験生が多いのではないでしょうか。しかし、志望校の傾向を知り、効率的な勉強法を身につければ、古文は十分に得点源になります。
今回は、関関同立の古文試験の特徴を大学別に解説し、単語帳だけに限らず、ポラリス1を例にした参考書の使い方を紹介します。
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————
関関同立の古文で大切なのは傾向を知ること
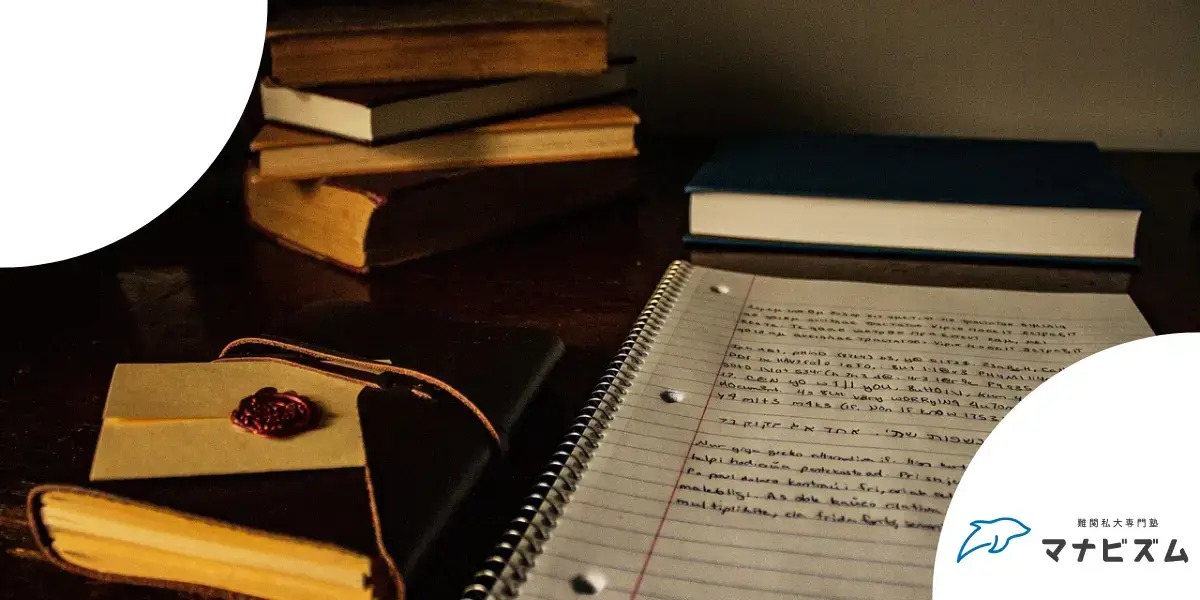
関関同立の古文は、文法・単語・読解・文学史などさまざまな角度から出題され、大学ごとに特徴が異なります。各大学によって重視するポイントが違うため、志望校に合わせた対策が必須となります。
【簡単なまとめ】
- 関西大学は『ひたすら長い』
- 関西学院大学は『設問が複雑』
- 同志社大学は『本文が多少難しい』
- 立命館大学は『文脈判断が必須』
残念ながら関関同立の古文は、一括りにできません。次からは、各大学の特徴を詳しく見ていきましょう。
【大学別】関関同立の古文試験の難易度

関関同立各校の古文試験には、それぞれ特徴的な傾向があります。志望校に合わせた対策を立てるために、詳しく見ていきましょう。
関西大学は『ひたすら長い』
関西大学の古文は、とにかく本文がひたすらに長いのが特徴です。長文に取り組むのは、面倒に感じるかもしれません。
ただ、しっかり訳せばそれだけヒントも多く含むということです。注釈をヒントだと捉えて解けると、問題自体は比較的簡単な傾向にあり、しっかり取り組めば満点も十分狙えます。
また、関西大学の古文の特徴は、文章中に傍線部が引かれていないことです。そのため、先に問題に目を通し、本文を読みながら該当箇所を見つけたらチェックする読み方が重要です。
関西学院大学は『設問が複雑』
関西学院大学の古文は、本文自体が面白い内容で作られているほか、設問も複雑な傾向があります。
例えば、本文を読んでそこから古文常識を用いて選択肢を絞り込むという形式がよく見られます。テクニック・単語・文法だけの知識では解けない問題が多いのです。
とはいえ、関学の古文は癖が少なく、標準的な問題をバランスよく出題します。単語や文法などの基礎問題はもちろん、文学史や現代語訳などの応用問題も出題されます。
演習後に自らの力で現代語訳ができているか、これを日ごろから訓練できれば得点源になるはずです。
同志社大学は『本文が多少難しい』
同志社大学の古文は配点が少ないなかで、記述問題の配点が高いという特徴があります。国語全体では120〜130点は取りたいところなので、記述が0点では合格は厳しくなります。
とはいっても、関関同立のなかでは文章量がもっとも少なく、難易度も易しめです。本文は多少難しいものの、満点が狙えるレベルでしょう。
とりわけ選択問題は簡単な問題が多く、記述問題にしっかり対応できれば得点も十分可能です。ただし、難易度が易しい分、高得点が求められます。
ほかの受験生と差をつけるためには、最後の記述問題をいかに正確に解答できるかがポイントになるでしょう。
立命館大学は『文脈判断が必須』
立命館大学の古文は本文が難しく、なかでも有名な出典からの出題の場合はさらに難しくなる傾向があります。設問では短文和訳を2題出題するのが特徴で、そのうち1題は比較的簡単です。
ただ、もう1題は文脈判断を求める難問になっており、関関同立のなかではもっとも満点を取りにくい部類だといえるでしょう。また、ほかの大学と比較して文章量がもっとも多いです。
出題内容も文法問題から文学史まで幅広く出題する傾向があるため、基礎的な文法を大事にして丁寧に訳す力を養ってください。
マナビズムでは、関関同立の出題傾向を熟知した講師陣が、弱点を分析し、成績を着実に伸ばす堅実な学習計画を立てます。志望校合格に向けた最適な対策をキミに合わせて作るので、ぜひ無料受験相談から相談してください!
関関同立の古文に使える単語帳は何がいい?
【動画でもご覧いただけます!】
古文の単語帳は数多く出版されていますが、マナビズムで32種類を調査した結果、以下のような代表的な単語帳が受験生に使われていました。
- フォーミュラ600
- ゴロゴ
- マドンナ古文単語230
- 古文単語315
- 見て覚える読んで解ける古文単語330
見出し語がもっとも多いのは「二刀流古文単語武蔵」で、総収録語彙数は634語、総収録語彙種類は638語となっています。一方、「繋がる・まとまる古文単語500プラス」は総収録語彙数が約1200語ともっとも多いです。
単語帳選びの理想は?
単語帳選びでは、見出し語でいうと600語程度が理想的です。
学校の先生が「古文単語315でいける」と言うのも間違いではありません。この単語帳の総収録語数は529語なので、これをしっかり覚えれば十分な基礎力が身につきます。
ただし、「関西と関東だったら関西の方が古文は難しい」傾向があるため、「MARCHや関関同立以上のレベルになったら1000語は最低覚えてほしい」です。
ほかに、望月先生の古文単語333は「令和版マドンナ古文単語」とも呼ばれ、ミニブックは周回学習がしやすいと評判です。横書きで古文単語と単語の意味だけが載っているシンプルな構成で、無駄なく理想的な周回学習ができるので試してください。
関連記事:【古文講師が教える】古文読解で押さえておくべきこと3選
関関同立の古文で使える参考書の使い方
【動画でもご覧いただけます!】
ここでは、「どこがダメなのかという理由まできっちり明記してくれている」と評判の「古文ポラリス1」を例に、参考書の使い方を紹介します。
【大学入試問題集 岡本梨奈の古文ポラリス[1 基礎レベル]の特徴】
出典:Amazon
- 過去10年分の入試問題から厳選した14題を収録
- 実力がつく順に問題を配列
- 問題文の読み方、語句・文法の解説、論旨の展開について詳細な解説付き
- 「参考書のような詳しさ・丁寧さ」がコンセプト
- シリーズ累計100万部突破(2018年出版からの鉄板参考書)
では、以下でじっくり確認しましょう。
1. 「はじめに」を読む
まずは岡本先生がこの本を作った目的を理解しましょう。
どういう力をつけてほしいのかをしっかり把握することが大切です。参考書の意図を著者と使い手でしっかりすり合わせておけば、何をするのかが明確になった学習が可能になります。
2. 問題演習
第1回から順番に問題を解いていきましょう。
初期段階では制限時間は気にしすぎなくても大丈夫です。演習はあくまで予習スタイルで取り組み、じっくりと問題と向きあってください。
3. 丸付け作業
問題を解き終わったら必ず丸付けをしましょう。
この段階では「合っている・間違っている」の判定だけで十分です。初期段階では、正答率よりも知識の運用力を重視します。単語・文法・解釈の知識が実際に使えているかを確認しましょう。
4. 自己分析
丸付け後、もう一度本文に戻りましょう。
「どう読めば正解になるのか」を自分で考え、「どこがバツなのか」を自分で検討してください。完全に分からない場合は、ここで一旦保留してもかまいません。
5. 解説を読む(最重要)
ここからが重要です。解説を読む際には、以下の3つのポイントに注意しましょう。
5-1. 論旨の展開を必ず読む
物語性のある古文では、頭のなかでのイメージ化が重要です。
自分が読んだイメージと違う場合は「どこで読み間違えたのか」を特定してください。「あ、そういう風な話の展開の流れだったのね。自らの読んだ感覚と全然違った」という場合は要注意です。
5-2. 本文解説の使い方
論旨の展開を読んでイメージと合っていれば、細かな解説はそれほど必要ありません。
しかし、イメージがずれていた場合は、どこかで読み間違えているため細かく読んでください。1文単位の細かな解釈を確認しましょう。
5-3. 問題に応じた解説の読み方
古文において、躓いた原因に応じて解説の読み方を変えましょう。
- 語彙が分からなかった → 「語彙」の解説を読む
- 文法が理解できていなかった → 「文法」の解説を読む
- 設問の切り方を間違えた → 「設問解説」の部分を読む
自分がどこでつまずいたかによって、読む場所を変えれば、間違い方に合わせて学習できます。
6. 徹底的に復習する
古文は、解説を読んだだけでは終わりません。必ず問題に立ち帰って復習しましょう。
「解説で説明された内容が自分で再現できるか」を確認してください。経験上、古文でつまずく子に限って、「復習のときに書き直してやるという作業をしていない」ことが非常に多いです。
「全部読み終わりました」では意味がないのです。
7. イントロダクションを活用する
すべての復習が終わったあとは、イントロダクションを読みましょう。例えば「宇治拾遺物語」などの作品全体の説明を理解し、「こういう話の流れですよ」という情報を知識として蓄えてください。
古文は。できあがっている文章を入試問題で使い回します。だからこそ、「この話の流れはこうだったなって整理できているだけでも自らの力になる」でしょう。
まとめ
関関同立の古文は。大学ごとに特徴が異なります。関西大学は長文で注釈が多く、関西学院大学は設問が複雑、同志社大学は記述問題の配点が高く、立命館大学は文脈判断が必要な和訳問題をします。
古文単語は600語程度を基本に、関関同立レベルなら1000語程度の習得を目指しましょう。そして参考書は「読んで終わり」ではなく、徹底的な復習を通じて自らの力にしてください。
マナビズムでは、関関同立合格に向けた古文対策にも対応し、キミの受験を徹底サポートします。関関同立の古文で悩んでいるなら、ぜひマナビズムの講師に無料で相談してください!
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————