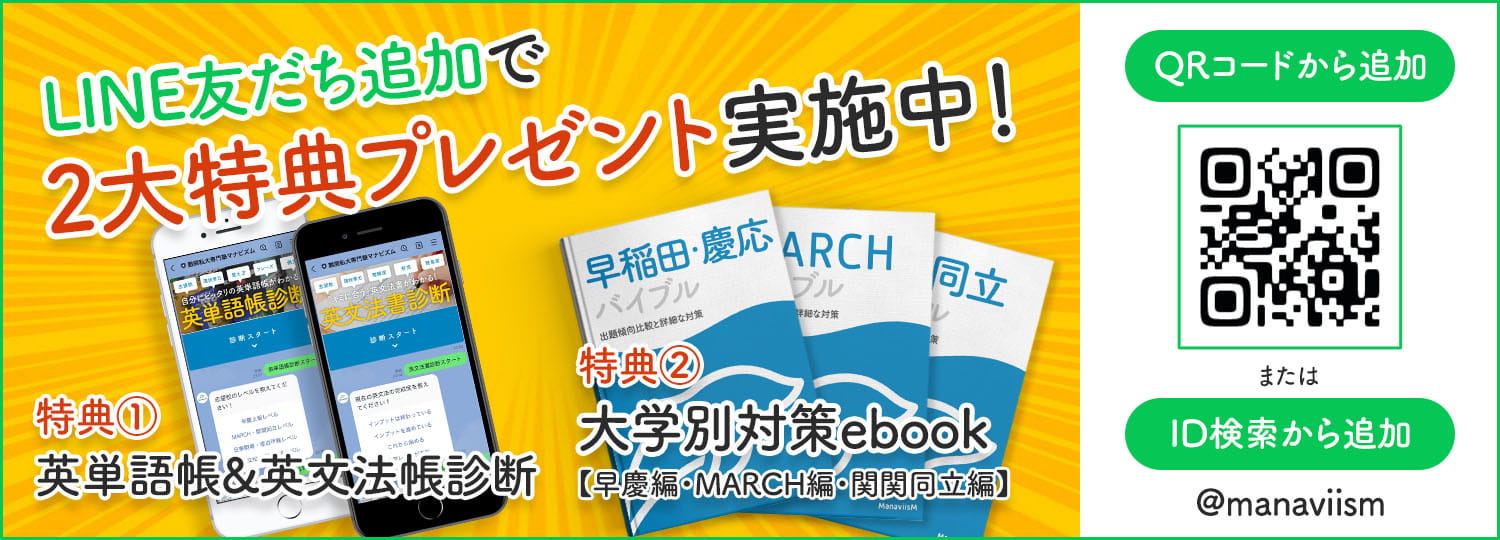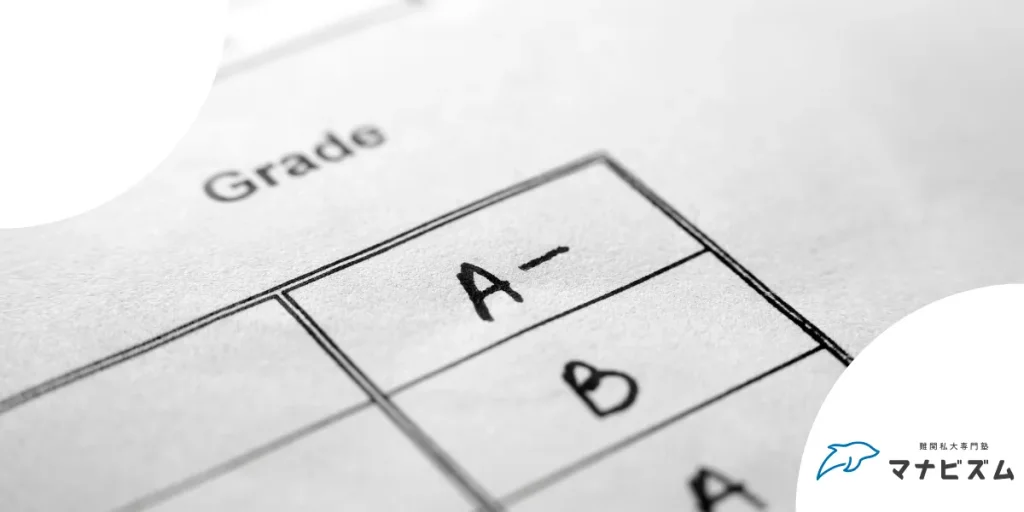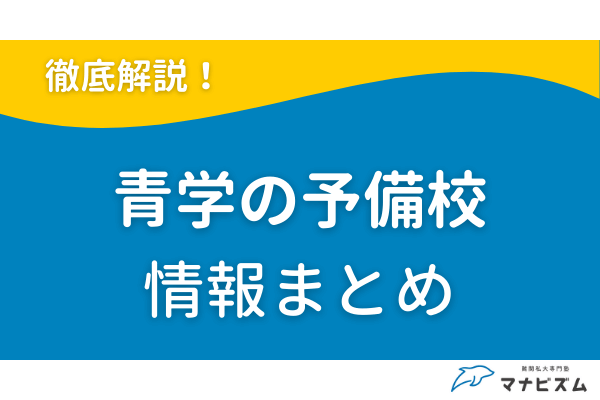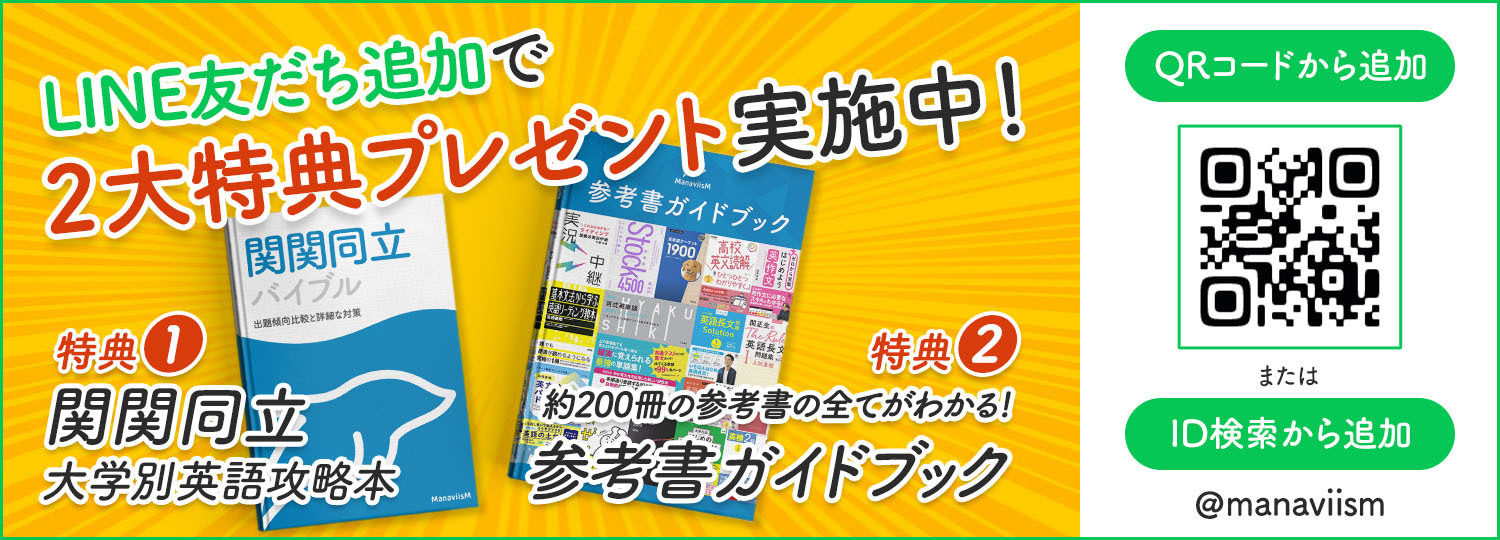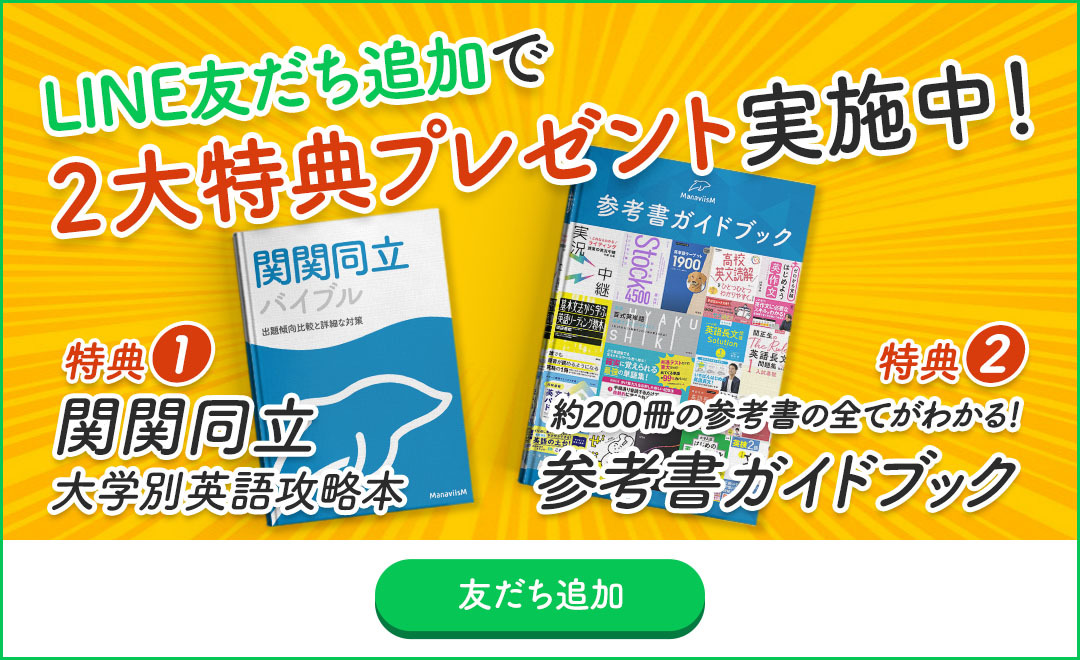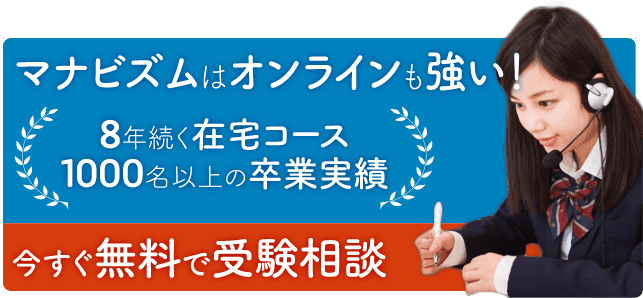【高校受験】赤本の正しい使い方を5ステップで解説!3つの落とし穴に注意しよう
更新日: (公開日: ) COLUMN

赤本を買ったけれど、どう使えばいいのか悩んでいませんか?「ただ解くだけでは意味がない」と聞いた方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、赤本は「志望校の傾向把握と自己分析のツール」です。正しい使い方をすれば合格の確率を高める要因となりますが、間違った使い方では時間の無駄になってしまいます。
赤本は単なる問題集ではなく、志望校からのメッセージが詰まった戦略的な教材だからです。この記事では、赤本の使い方を5つのステップで解説し、受験生が陥る3つの落とし穴についても触れます。
赤本とは
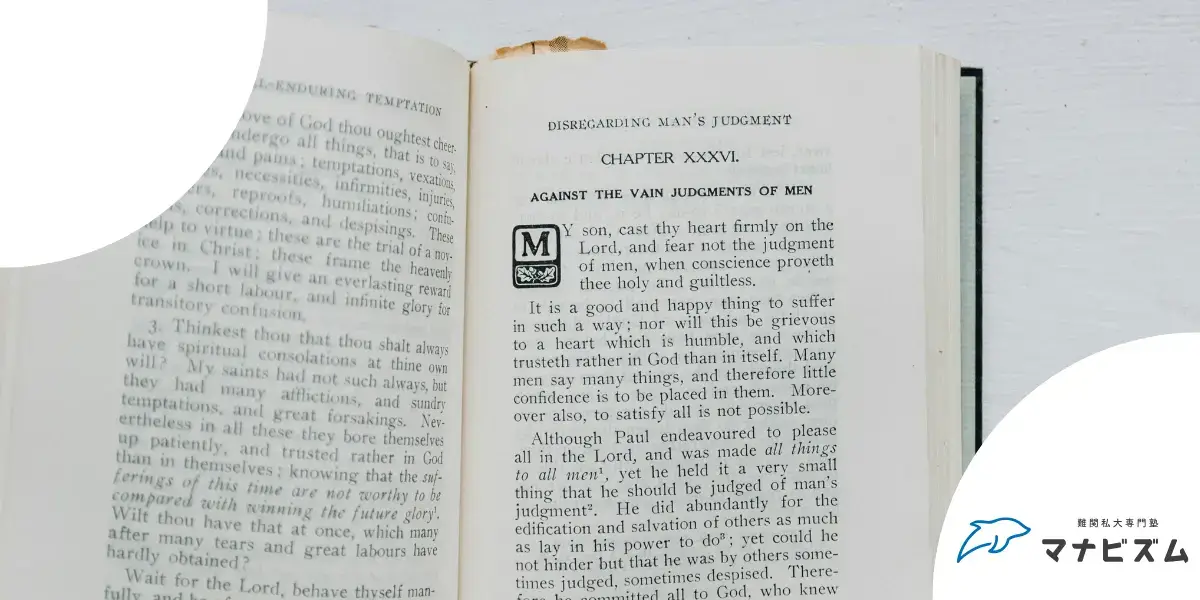
赤本とは、教学社が出版している「大学入試シリーズ」の総称のことです。表紙が赤いので「赤本」と呼ばれています。全国378大学の過去問を収録しており、志望校の「生の問題」に触れることができる唯一無二の教材です。
赤本では、各大学の学部ごとに過去問を数年分まとめています。単に問題や解答・解説が載っているだけではなく、大学の概要や出題傾向、対策法などもあり、受験勉強の効率を高めるための情報が満載です。
赤本と一般的な参考書の違い
赤本と一般的な参考書には、決定的な違いがあります。参考書は「実力を伸ばす」という点を目的に作られているのに対し、赤本は「受験生を振りわける」ための問題が載っています。
参考書は学力向上のために問題の選定から解説まで工夫していますが、赤本の問題は「合格/不合格を決める」ために作られているのです。この違いを理解せずに赤本を使うと、効果が半減してしまう可能性もあります。
赤本を使うべき理由
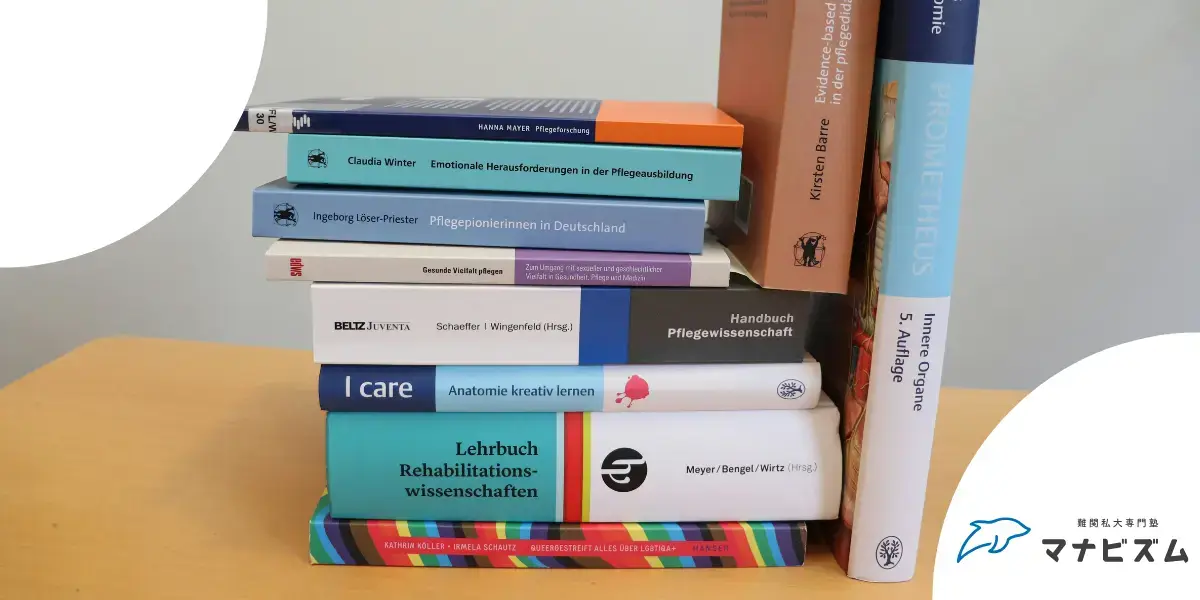
赤本を使うべき理由は、以下のとおりです。
- 志望校の出題傾向を把握できる
- 自らの弱点を明確に発見できる
- 本番の試験形式に慣れることができる
- 時間配分の感覚をつかめる
- 合格への自信を育てられる
目的意識を持って赤本に取り組むと、合格の可能性が高まります。志望校が毎年どのような分野から出題しているのかを分析することで、対策が可能でしょう。
ただ、赤本の使い方では注意したい点があるのも事実です。次の章では、受験生が陥りがちな落とし穴について解説します。
使う前に知っておきたい赤本の落とし穴3選
【動画でもご覧いただけます!】
赤本の使い方を知る前に、以下3つの落とし穴を知っておきましょう。
- 解説が鬼薄い
- 合格最低点が「得点調整後」
- メンタルブレイクの原因になる
解説が鬼薄い
赤本の解説は「ここにこうあるから答えは4番」というように結論だけが書かれており、その過程の理解に苦しみます。「分かったつもりになる」のが一番危険で、それが受験対策での罠となります。
本当に必要なのは、「どういう視点で読めばそこにたどり着けたのか」という思考の過程の言語化です。しかし、赤本の解説ではそこまで踏み込んでいないため、復習の質も上がりにくいです。
解説に書かれていない部分を「自分で埋めていく」。これが求められます。
また、「結果を知っただけでテンションが上がる、分かった気になる」という状態も危険です。過去問演習の目的は、自分で考えた根拠が合っているかを検証して精度を上げることです。
その場で正解か不正解かは分からないからこそ、仮説を立てて検証していく使い方が重要です。解説が薄いからこそ、自分で思考する習慣をつけましょう。
合格最低点が「得点調整後」
赤本に書かれている合格最低点は、得点調整が入ったあとの点数です。そのまま鵜呑みにして「これで足りてるやん」となるのも良くありません。
マナビズムでは、0.85をかけることを推奨しています。得点調整で30点近く落ちるというケースも普通にあります(例:同社の文系で130点→104点など)。「0.9で届いてるからOK」ではぬか喜びになる可能性が高いのです。
本番で最悪のシナリオを想定せずに準備するのだけは避けたいことのはずです。だからこそ、0.85で計算してそこに届いているという設計にしましょう。
メンタルブレイクの原因になる
先の話に続いて、点数で精神面を保とうとする人ほど、本番で一番メンタルを崩します。合格最低点と自らの点数の差にショックを受け、メンタルをやる子は少なくないでしょう。
「解説が薄い → 改善点が見えない → 不安が加速する」という悪循環に陥りやすくなります。解説がしっかりしていれば反省しやすいのですが、赤本は薄いので「次どうしたらいいか」も分からなくなります。
その結果、点数だけを見てメンタルがやられてしまうわけです。
点数に一喜一憂しないためにも、分析ノートなどの”道しるべ”が必要です。自分で反省し仮説を立てる力があれば、「0.85点落とした部分」をどう埋めるかにも焦点を当てられます。
次章では、この落とし穴を避けながら赤本を使う方法を解説します。
マナビズムが教える赤本の正しい使い方
【動画でもご覧いただけます!】
ここからは、赤本の正しい使い方を5つのステップで紹介します!
- 制限時間は -5分で解く
- 丸付けは〇×だけ
- ×と曖昧な正解は必ず解き直す
- 赤本の解説は鵜呑みにするな
Step①:制限時間は 「-5分」 で解く
赤本に書かれている制限時間通りに解いてはいけません。本番ではマークずれの確認や、回答用紙への転記など+αの作業が発生するからです。
本番でのミスを防ぐには、普段の演習から5分ほどの短い時間で設定した使い方が基本です。例えば、同志社大学の英語が100分なら、95分で解くようにしましょう。
もし普段からギリギリで解いていると、本番の緊張で時間切れになる危険性が高まります。「本来解けたはずの問題を落とす」ことになりかねないので、必ず5分ほどの短い時間で行いましょう。
Step②:丸付けは「〇×」だけ
赤本を解き終わったあと、受験生がやりがちな間違った使い方は、以下の2つです。
- 「正しい選択肢を赤で書き直す」
- 「各選択肢の単語の意味を赤でメモる」
これでは自己満足の勉強で、復習効率が悪いです。そのページを何度も見返すわけでもなく、記憶にも残りません。
本当に意味があるのは、「普段使っている単語帳」に転記する、「単語カードを作って回す」などの継続的な対策です。赤本に正答を書き写すのではなく、問題番号の横に〇×だけの記録をおすすめします。
正答も書かない・丸もしない→〇×だけにすることが重要です。これにより、次のステップである「解き直し」に集中できます。
Step③:×と「曖昧な正解」は必ず解き直す
赤本の正しい使い方のステップ3では、以下の2つの問題を必ず解き直しましょう。
- ×になった問題(間違えた)
- 正解したけど、根拠が曖昧だった問題
この解き直しのときは、解説・和訳・途中式など一切見ないようにします。英語・現代文・古文などの読解系は文を読み直して再度解きましょう。数学や理科の「まったく分からん」問題は潔く切ってOKです。
見切りをつけつつ、「自らの知識でアプローチできる問題」には本気で再チャレンジすることが大切です。解き直しによって、自らの理解度を深め、同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。
Step④:赤本の解説を「鵜呑みにするな」
赤本の解説を「読んで満足」するだけでは、点数は伸びません。頭が良い人は、無意識にやっている読み方・分析方法をしているだけです。
復習で大事なのは、次の2点です。
- 本文の復習→文構造・訳し方・論理展開の復習
- 設問の復習→解答根拠の「見つけ方」「視点の持ち方」
例えば、同義語選択問題の解説には「この単語は〇〇という意味だから〜」としか書いていません。しかし本当に大事なのは、「知らなかった場合にどうアプローチしたか」「文脈で判断できなかった理由」など解説にない部分です。
使い方次第で自分で思考し、仮説を立てる学びを得られます。解説を読むだけでなく、そこから自分なりの学びを引き出す姿勢を持ちましょう。
Step⑤:復習結果から「勉強計画を修正」
赤本を正しく使ったうえで、復習分析から見えてくるのは、自分に「何が足りていないか」です。具体的には、勉強計画の2つの側面を修正しましょう。
【1. 量の修正】
苦手なA文法で落としたのであれば、A文法の演習量・インプット量を増やします。そのためにほかの得意科目の勉強時間を少し削る調整などが必要です。
【2.質の修正】
英語長文の読み方が悪かったのであれば、普段から「論理展開を意識した読解」に変えます。
この量×質の両面で修正できなければ、復習は意味をなしません。Step⑤にたどり着くには、Step④での分析が必須です。そして、Step①〜④の流れを一貫してやることが超重要です。
マナビズムでは、こうした学習方法を詳しく指導しています。志望校合格に向けて本気で学びたいキミは、ぜひ無料で講師に相談してください!
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————
赤本の使い方で「書き込み」は良い?悪い?
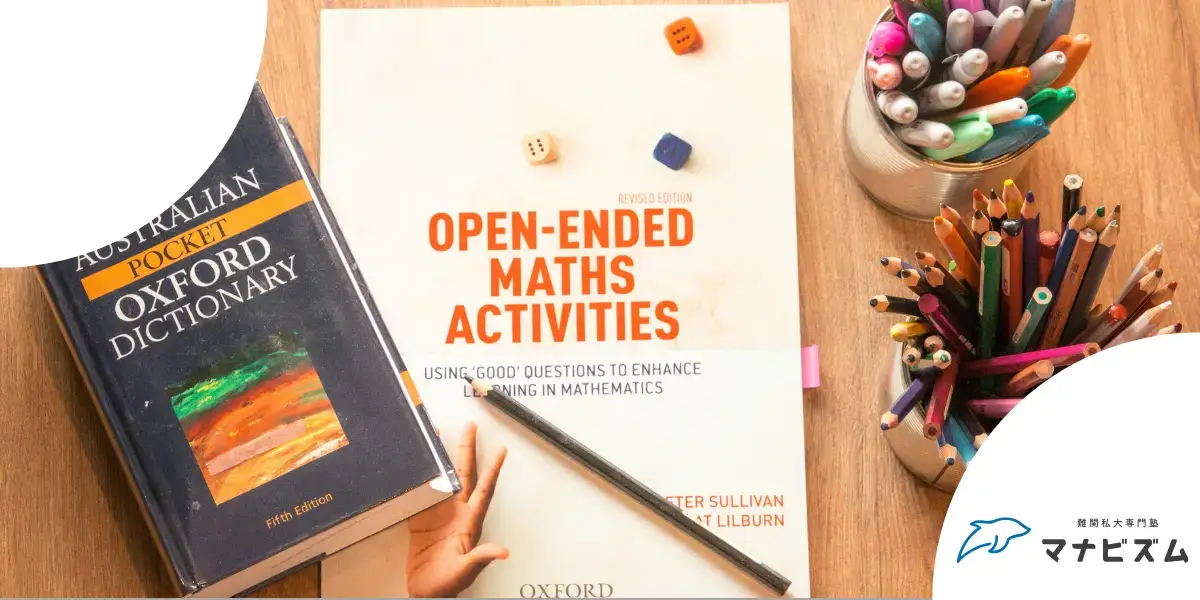
赤本の使い方では、「復習の質を上げる書き込み」であれば良いといえます。例えば、以下のような書き込みは工夫として有効です。
- 回答根拠が不明確だった問題に「※要再確認」と書く
- 曖昧な選択肢に「なんで選んだか?」を横にメモする
- 文構造が難しかった英文に、構文・論理展開を書き込む
- 長文読解で「ここが具体例」「ここが言い換え」などの視点を書く
全部、次に赤本を開いたときに学びが続くようにする方法ばかりだからです。
一方、以下のような書き込みは避けるべきです。
- 正解を赤で書き写す(〇つけた後に上からなぞるなど)
- 全選択肢の意味を赤字で並べて書くだけ
- 和訳に頼って、本文の英語を塗りつぶすような書き方
こういうのは、その場で「やった感」はあるけれど、次に見返す価値が低いです。”思考のプロセス”を記録する書き込みこそが価値のあるものだといえます。
赤本への書き込みは、単なる記録ではなく、自らの思考を整理し、次回の学習につなげるためのものであることを意識しましょう。
まとめ
赤本は単なる問題集ではなく、志望校の傾向把握と自己分析のために使える教材です。正しく使えば合格への近道となりますが、間違った使い方では時間の無駄になってしまいます。
この記事で紹介した5つのステップを実践することで、赤本の効果を最大化しましょう。
- 制限時間は「-5分」で解く
- 丸付けは「〇×」だけ
- ×と「曖昧正解」は必ず解き直す
- 赤本の解説を「鵜呑みにするな」
- 復習結果から「勉強計画を修正」
マナビズムでは、こうした学習方法を詳しく指導しています。志望校合格に向けて本気で学びたいキミは、ぜひ無料相談から講師に声をかけてください。赤本を戦略的に活用して、一緒に志望校合格を勝ち取りましょう!
よくある質問(FAQ)
赤本はいつ使う?
赤本を使いはじめるベストなタイミングは「志望校が決まったら」です。早すぎても、遅すぎても効果が薄れます。受験直前になってようやく赤本を開くというのでは遅すぎるでしょう。受験学年の夏頃には一度過去問全体に目を通すことがおすすめです。
赤本は年に何回解いたらいいですか?
赤本は何度も繰り返し解くことで効果を発揮しますが、単に回数を増やせばいいわけではありません。質を重視すべきです。1週間に解く量は1年分程度を目安とし、その代わりに分析と解き直しに時間をかけてください。
赤本で点数を出すには?
赤本で点数を出すには、単に問題を解くだけでなく、解いたあとの分析と対策がカギです。間違えた問題の原因を特定し、弱点を克服する取り組みを行ってください。解説を鵜呑みにせず、自分なりの考え方を確立しましょう。
赤本を解くなら何年?
赤本で解くべき年数は、第一志望の大学であれば5年から10年分ほどが目安です。最低でも5年分は解くのが望ましいでしょう。大学によって収録している年数が異なりますが、傾向や難易度を把握するために必要な学習量は5年〜8年分の過去問です。
赤本は何年分買うべき?
第1志望校の赤本は、5年から10年分程度で購入するのが理想的です。最新の出題傾向を把握するために、最新版は必ず入手しておきたいところです。第2志望や第3志望など併願校については、3年分程度解けば出題傾向を把握しやすくなります。すべて購入する必要はなく、学校や塾で借りたり、インターネットでダウンロードしたりする方法もあります。
赤本は何のために使うのですか?
赤本を使う目的は主に4つあります。志望校の問題に慣れる(傾向と対策を掴む)、捨て問の見極め、本番対策、勉強不足な部分を見つけることです。大学受験では同じ科目でも大学、学部、学科、受験方式によってまったく異なる問題が出されます。出題方式、難易度、配点、試験時間、それぞれ変わってくるため、知るために赤本は必須です。
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————