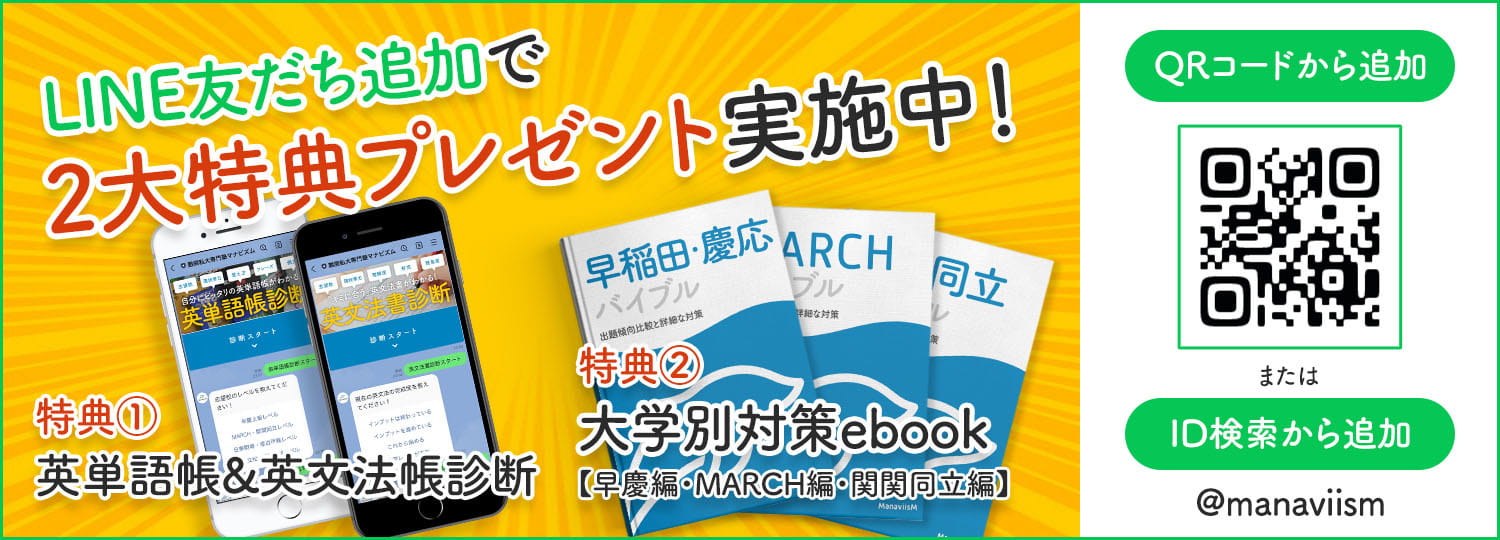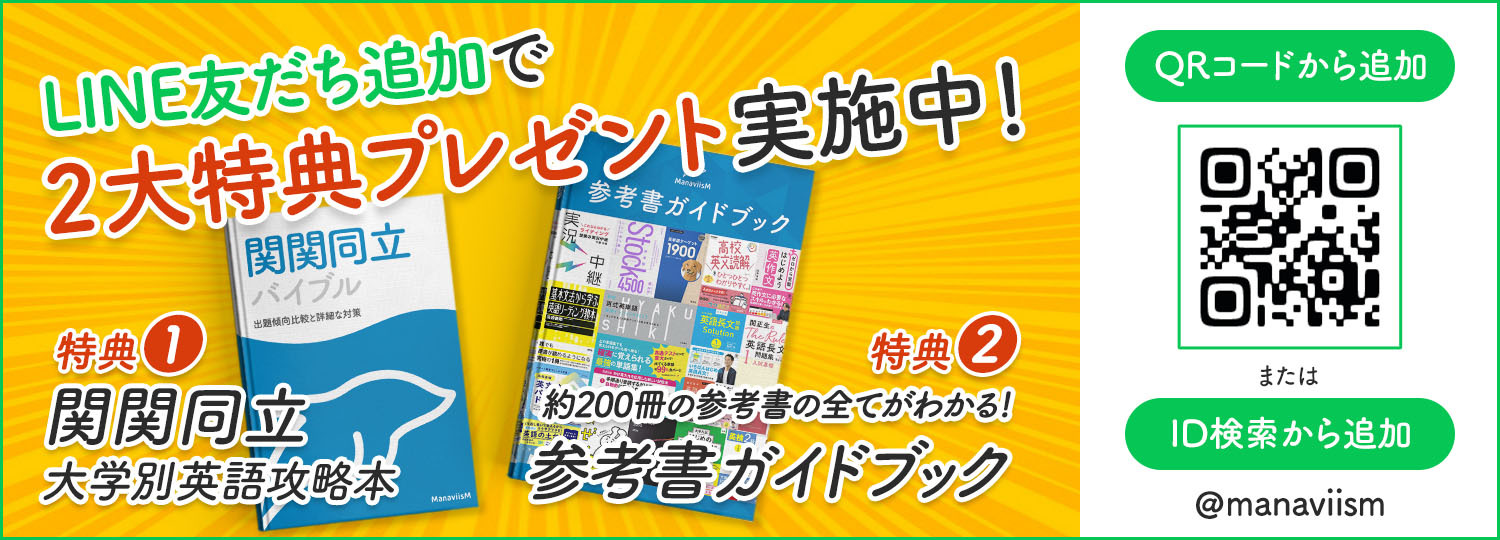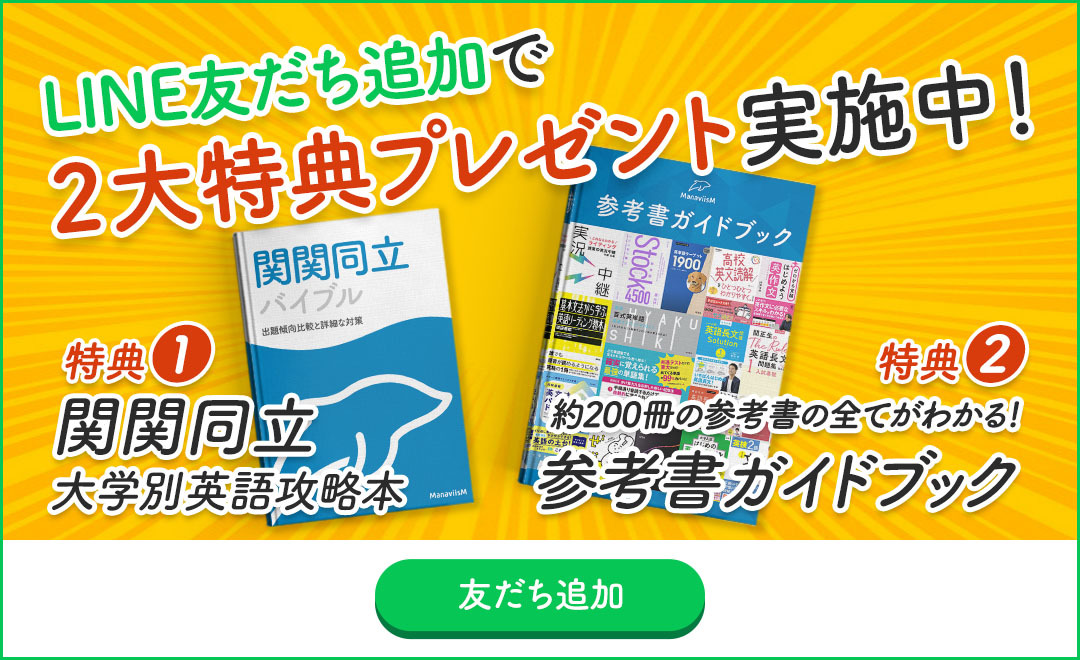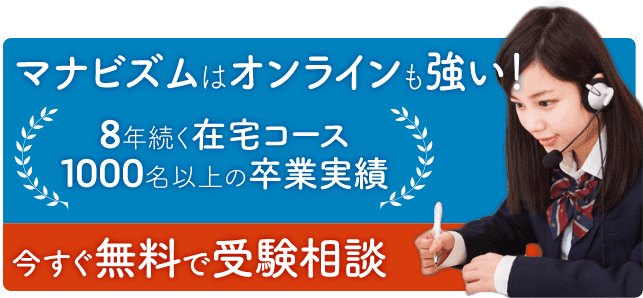【大学受験】塾の送迎が負担な保護者必見|主な理由と対策をあわせて紹介
更新日: (公開日: ) COLUMN
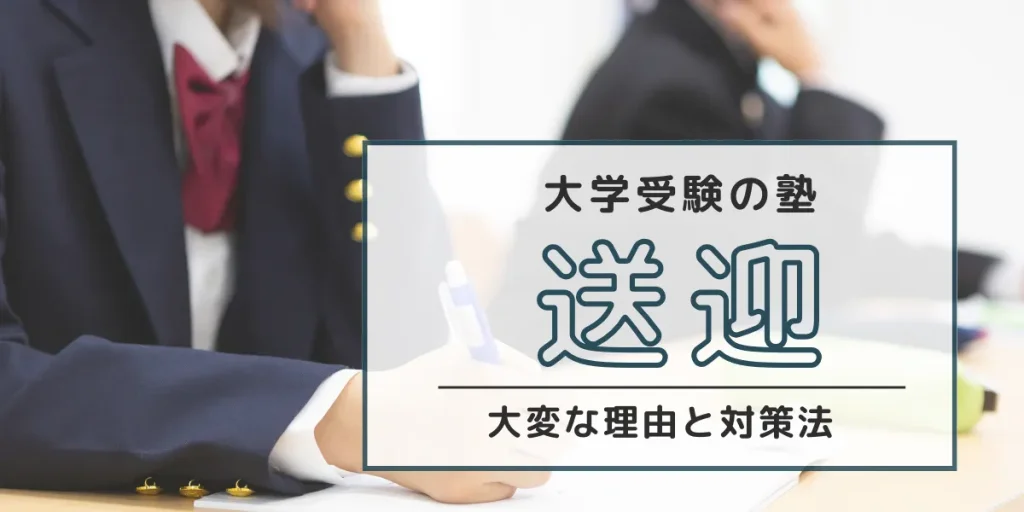
「塾の送迎、毎日のように走り回って疲れ果てている…」「仕事が忙しくて、送迎の時間が作れない」「子どもを一人で通わせるのは不安」という悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
高校生になれば、移動手段を自分で見つけて通えるとはいえ、遠方であったり、不安や心配があったりする際に送迎を行う親御さんもいるはずです。
そこで本記事では、塾の送迎にまつわる現状と課題を整理したうえで、負担を軽減するための具体的な8つの方法を紹介します。子供の学習環境を守りながら、親御さんの生活の質も維持したいとお考えの方は、ぜひ最後までご一読ください。
塾の送迎をする保護者はどれくらいいる?

子どもの塾や習い事の送迎は、多くの保護者にとって日常的な光景となっています。全国調査によると、実に6〜7割の保護者が子どもの送迎を行っているというデータがあります。
特に塾の送迎については、夜間の帰宅時の安全確保や、荷物が重いことへの配慮から、保護者による送迎のニーズが高くなっています。2022年の調査では、習い事全般の送迎について約6割の保護者が実施していると回答。その中でも塾は、学校と並んで送迎頻度の高い場所の1つです。
【参考出典】
約7割の保護者が行う送迎 親子の会話を楽しむ時間にも|ベネッセ教育情報サイト(https://benesse.jp/kyouiku/201502/20150204-1.html)
習い事の送迎がツラい‥ストレスの種や解決策を全国522人の保護者に調査|PRTIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000105786.html)
大変?塾の送迎が負担になる3つの理由

塾の送迎は、以下の3つの理由から、日々の生活に支障をきたすケースが少なくありません。
- 平均通塾日数が2〜3日と頻繁な送迎が必要
- 兄弟・姉妹のいる場合の複数回送迎
- 送迎と忙しい時間の重複
平均通塾日数が2〜3日
通塾頻度は週に2〜3日が一般的ですが、実際の日数は通う塾の種類によって大きく変わってきます。例えば、学校の授業に合わせた補習塾であれば週2日程度ですが、受験に向けた進学塾となると週3日以上の通塾を求められることも珍しくありません。
特に受験を控えた時期には、通常授業に加えて特別講座や模試対策なども入ってくるため、さらに通塾日数が増える傾向にあります。定期的かつ頻繁な送迎が必要となると、保護者にとって大きな負担となります。
兄弟・姉妹のいる場合の複数回送迎
兄弟姉妹がいる家庭では、学年が異なれば授業時間や曜日も違うため、週4〜5日とほぼ毎日の送迎が必要になることもあります。
保護者の自由な時間が著しく制限されるだけでなく、ガソリン代などの経済的負担も無視できません。同じ塾に通わせる場合であっても、時間割の確認は必須となります。
送迎と忙しい時間の重複
多くの中学生の塾は19時から21時に終わりますが、家庭にとってもっとも忙しい時間です。共働き家庭では保護者の退社時間と重なり、専業主婦家庭でも夕食の準備や片付けの真っ最中ということもあるでしょう。
21時以降になると、翌日の準備も始まります。お弁当作りや朝食の下準備など、やるべきことが山積みの時間帯に送迎することで家事のスケジュールが大きく乱れてしまうこともあるのです。
このように、塾の送迎にはさまざまな負担が伴います。しかし、こうした状況を少しでも改善するための方法がいくつかあります。次は、そのような送迎の負担を軽減するための具体的な対策について見ていきましょう。
つらい塾の送迎にかかる負担を抑える8つの方法

つらい塾の送迎にかかる負担を抑える方法は、以下の8つが挙げられます。
- 塾で自習をさせておく
- 自宅近くの塾を選ぶ
- 防犯対策のうえ一人で通わせる
- 親戚に頼む
- 保護者間で協力し合う
- 送迎バスを活用する
- 代行サービスを使う
- オンライン塾に切り替える
塾で自習をさせておく
夕方から夜にかけての時間帯は、塾の自習室を活用する方法が有効です。よくある17や21時台に送迎するのではなく、22時以降などの一段落した時間帯に迎えに行くことで、保護者の負担を大きく減らせます。
また子どもにとっても、自習時間が確保できるメリットもあります。実際の成績向上には授業以外の学習時間が重要なため、自習習慣を身につけられる点でも効果的な対策といえます。自習室がない塾の場合は、この機能がある塾への転塾も検討に値するでしょう。
>>自習室で選ぶおすすめの予備校6選|選び方からポイントまで徹底解説
自宅近くの塾を選ぶ
自宅から近い、例えば徒歩10分圏内であれば、夜間でも高校生なら安全に一人で通塾できます。また、急な体調不良や天候の変化があっても、すぐに対応できる安心感もあります。
通塾時の経路に危険な場所がないかなど、実際に下見をして確認しておきましょう。交通手段に費用がかかっても良いなら、さらに範囲を拡大することも可能です。
防犯対策のうえ一人で通わせる
高校生でも女の子の場合は、以下の対策を講じましょう。自ら対応できれば問題ないですが、夜間となれば危険性がないとは言い切れません。
- 通塾経路の事前確認
- 緊急連絡先の共有
- 防犯アプリの活用
SNS上での犯罪など、現在では接点がどうしても多いため、ただ塾に通うという点だけでも『ある程度の安心』は用意しておくと良いでしょう。
親戚に頼む
高校生でも、近くに住む祖父母や親戚に送迎をお願いするのも1つの方法です。一時的な帰宅先としても良く、特に共働き家庭にとって信頼できる身内のサポートは助かるはずです。
自習室のような場所としても最適で、自宅での学習が進まないときにも役立ちます。
保護者間で協力し合う
同じ塾に通う子どもの保護者と協力して送迎を分担する方法は、負担を半減できる効果的な対策です。ただし、トラブル防止のため、ルールを事前に決めておくことが重要です。
遠方の塾になるほど、どうしても負担が片方に偏りやすくなることから、夫婦間の問題に発展しかねません。
送迎バスを活用する
塾では、送迎バスサービスを行っていることもあります。高校生は自ら交通手段を使って通うことができるものの、バスなら一定の費用または無料で利用できるのも利点です。
ただし、停留所や時刻表が決められているため、事前に詳細を確認し、自宅の生活リズムと合うかどうかを検討する必要があります。また、高校生向けの送迎バスサービスは少ないのが難点です。
代行サービスを使う
送迎代行サービスを使うと費用が発生するものの、送迎バスと同様に不安はグッと減ります。特に都市部では、ファミリーサポートセンターなどの公的サービスも利用可能です。
費用対効果を考慮しながら、活用を検討してみましょう。高校生向けに対応しているか、地方で対応しているサービスがあるかは確認してください。
オンライン塾に切り替える
すでに軽く触れましたが、インターネットの普及により、質の高いオンライン学習が可能になっています。自宅で学習できるため、送迎の心配が完全になくなるだけでなく、以下のメリットもあります。
- 移動時間の学習時間への転換
- 天候に左右されない
- 柔軟な時間設定
- 保護者の負担軽減
ただし、対面授業とは異なる特徴があるため、まずは体験授業などで子どもに合うかどうかを確認することをおすすめします。
>>【高校生向け】オンライン塾おすすめランキング12選|内容から費用まで解説
このように送迎の負担を軽減する方法はさまざまですが、いつまで送迎を続けるべきかという判断も重要になってきます。次は、塾の送迎をやめるタイミングについて考えていきましょう。
いつまで?納得できるタイミングで塾の送迎をやめること
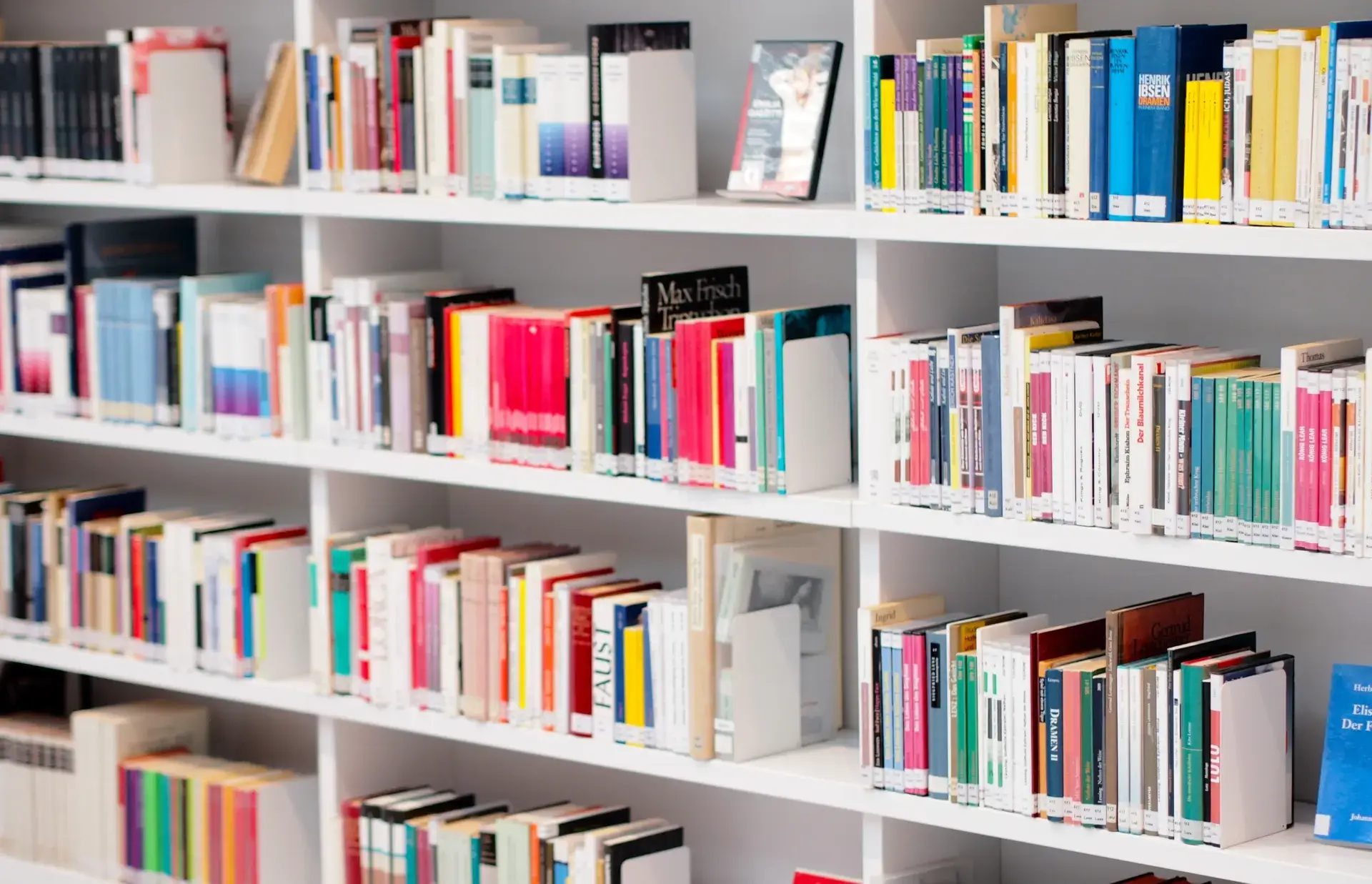
塾の送迎をやめるタイミングとしてもっとも多いのが、中学校・高校への進学時期となっています。特に高校生になると送迎する保護者は減少し、高校卒業後まで送迎を続けるケースはほとんどありません。
ただし、塾の場所や授業終了時間、治安、子供の性格や成熟度によって、送迎を続けるべきかどうかは変わってきます。繁華街を通る際、声をかけられたことがトラウマになってしまう…ということがあるかもしれません。
大切なのは、「いつまでに送迎をやめなければ」という固定観念にとらわれすぎないことです。保護者と子どもがしっかり話し合い、双方が納得できるタイミングで送迎を終えることが、もっとも望ましい選択です。
塾の送迎における3つの注意点
塾の送迎では、以下の3つの注意点を意識しておく必要があります。
- 車内に忘れ物がないか確認する
- 駐車できない塾が多い
- 講師と話せるわけではない
車内に忘れ物がないか確認する
塾の送迎でもっとも多い失敗が、車内での忘れ物です。自宅では持ち物をしっかり準備していても、車内で荷物を広げたまま塾に向かってしまい、大切な提出物や教材を置き忘れてしまうことがあります。
特に要注意なのが、車内で宿題をするケースで、使用した教科書やノート、筆記用具などが車内に残されたまま気づかないことが多いです。車を降りる際は必ず後部座席まで目視で確認することを徹底しましょう。
駐車できない塾が多い
多くの塾には専用の駐車場がないため、送迎時の駐車場所の確保は課題となります。特に人気の塾では、近隣の有料駐車場も送迎時間帯には満車になりやすく、毎回の送迎で駐車場所を探すストレスを感じる保護者も少なくありません。
路上駐車は一見簡単な解決策に思えますが、近隣住民からの苦情の対象となりやすく、塾からも注意を受ける可能性があります。また、交通違反のリスクもあるため避けるべきです。
塾から少し離れた場所でも確実に駐車できる場所を事前に確保し、子どもと待ち合わせ場所を決めておくなどの方法も検討しましょう。
講師と話せるわけではない
送迎のメリットとして「講師と直接コミュニケーションが取れる」と期待する保護者は多いものの、実際にはその機会を得るのは難しいのが現状です。授業終了後、講師は次の授業の準備、生徒からの質問対応、他の保護者への連絡など、さまざまな業務に追われています。
そのため、送迎時に立ち話程度の短い会話は可能でも、じっくりと子どもの学習状況について相談するような時間は取れないことが一般的です。重要な相談事がある場合は、事前に面談の時間を取ってもらうことをおすすめします。
塾の送迎が厳しいならマナビズムのオンラインコースへ
送迎の負担から解放されたい方には、オンライン塾という選択肢がおすすめです。自宅で受講できるため、送迎の心配が完全になくなるだけでなく、親御さんにとって以下のようなメリットがあります。
- 子どもの学習状況をリアルタイムで確認できる
- 夜遅くなっても安全面の心配がない
- 送迎時間を他の家事や仕事に活用できる
- 天候に左右されない安定した学習環境を提供できる
難関私大専門塾「マナビズム」では、生徒1人ひとりに専属の自習コンサルタントが付き、志望校に合わせた個別指導を行っています。通常の塾と違い、大学別に特化した授業を提供しているため、効率的な受験対策が可能です。
また、定額制で授業が受け放題なので、勉強量が増えても追加料金の心配がありません。送迎の負担がなくなることで、その分の時間とエネルギーを子どもの学習サポートに向けることができます。
お子さんの将来のために、最適な学習環境を整えてあげませんか?まずは無料でマナビズムに話を聞きに来てください!
まとめ

塾の送迎は多くの保護者にとって避けられない日常的な課題で、週2〜3日の通塾頻度、兄弟姉妹がいる場合の複数回送迎、夜間の時間帯と重なる家事など、さまざまな負担が重なっています。
- まず自宅近くの塾の情報を集め、送迎バスの有無や自習室の利用可否を確認する
- 同じ塾に通う保護者とコミュニケーションを取り、協力体制を築く
- 子どもの自立度に応じて段階的に送迎を減らしていく計画を立てる
- 必要に応じてオンライン塾への切り替えも検討する
送迎は確かに大変ですが、それは子どもの学習環境を支える役割の1つです。ただし、保護者自身の生活の質も大切にしながら、バランスの取れた対応を心がけることが、長期的な子どもの成長支援につながるでしょう。
塾の送迎に関するよくある質問(FAQ)
塾の送迎サービスはある?
はい、専門の送迎サービスがあります。代表的なものとして『オクレル』というサービスがあり、身元確認された専属ドライバーが塾への送迎を代行します。このようなサービスでは、塾だけでなく習い事やイベントなども含めて送迎を依頼可能です。
塾に送迎バス付きのところはある?
送迎バスを運営している塾は確かにありますが、主に小中学生向けのサービスとなっています。高校生向けの送迎バスを提供している塾は少ないのが現状です。送迎バスがある場合でも、利用可能なエリアや時間帯を限定しているため、入塾前に詳しい条件を確認することをおすすめします。
塾の送迎はタクシーサービスがある?
はい、日本交通グループをはじめとする大手タクシー会社が、塾への送迎サービスを提供しています。ただし、高校生向けのサービスは限定的です。タクシー送迎は、事前予約制で定期的な利用が可能で、専用アプリなどで配車状況を確認できるサービスもあります。