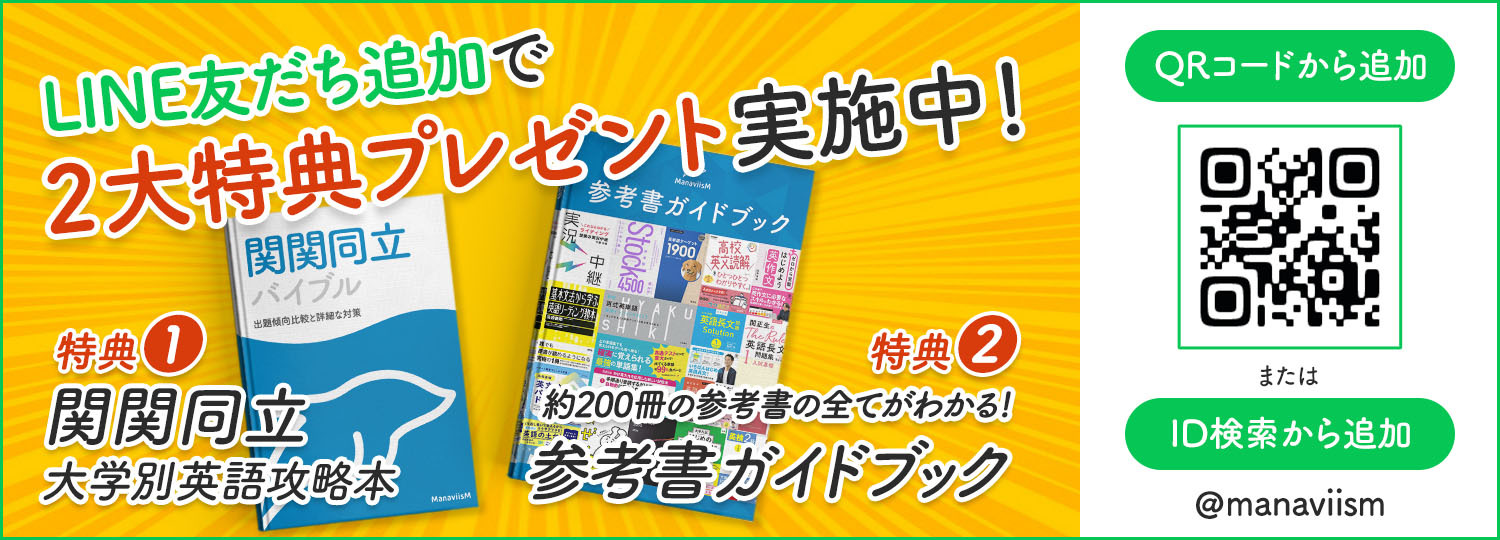新高2・高3になる春の時期は、大学受験において転換点となります。
しかし、保護者の方は「何からはじめればいいか分からない」「どこまで関わるべきか悩む」といった不安を抱えているのではないでしょうか。
そこで本記事では、新高2・高3の保護者の方が春にやるべき具体的な5つのポイントを詳しく解説します。
マナビズムでは、無料受験相談で、お子さんの状況に応じたご提案も可能です。
お子さんの「やる気」を最大限に引き出し、志望校合格まで全力でサポートしますので、お気軽にお声がけください!
新高2・高3の保護者が春にやるべき5つのこと
本動画は、「新高2・高3生の保護者」が春にやるべき5つのことをテーマに、大学受験のリアルな現実とその対策を詳細に解説します。
以下では、動画の内容をテキストでもわかりやすくまとめました。
新高2・高3の保護者の方が、この春の時期(4月・5月)に取り組むべきことは以下のとおりです。
- ① 受験方式を”仮決定”する
- ② 定期テストの「共通認識」を持つ
- ③ 本人の「やる」を信じてあげる
- ④ 子どもに「選択」させる習慣を持たせる
- ⑤ 全体のスケジュールを把握する
① 受験方式を”仮決定”する
第一に、新高2・高3、そして保護者の方は、受験方式を”仮決定”してください。
よく、学校の先生からの「総合型がいいんじゃない?」というアドバイスを受けるはずです。
しかし、数年前の感覚をもとにしており、現在の入試状況とは異なります。
現在の受験方式は、受験戦略の起点です。
そのため、保護者の方とお子さんで必ず話し合い、4月・5月の春の時期には仮決定します。
大学入試の受験方式は、大きくわけて以下の4つがあります。
- 一般入試
- 学校推薦型選抜(指定校推薦含む)
- 総合型選抜(旧AO入試)
- 共通テスト利用
いずれにおいても、中途半端な方向性で受験に臨むのがもっとも危険です。
どの方式で戦うのかを早期に明確にし、その方針に沿った戦略を立ててください。
② 定期テストの「共通認識」を持つ
第二に、定期テストの「共通認識」を保護者の方とお子さんで持ってください。
このとき、親子で一致した定期テストの目的と優先度をすり合わせます。
大学受験は、入試方式によって定期テストの重要性がまったく異なるからです。
一般入試を目指すなら、定期テストの得点に重きを置くのは非効率になります。
場合によっては、年間平均4回 × 2週間前後、つまり『年間にすると約2か月』をロスしかねません。
また、保護者の方の「点数が上がってない」という指摘は、お子さんのやる気を下げる要因にもなります。
③ 本人の「やる」を信じてあげる
第三に、お子さんが「やる」と言ったときに、保護者の方は過去を持ち出して否定しないでください。
新高2・高3のお子さんがやる気を見せたとき、すぐ信じてあげられるのは保護者の方だけです。
「本気の表情」のお子さんを見たときこそ、信じて背中を押してあげるタイミングです。
マナビズムの講師(今井先生)も、過去に親に信じてもらえなかった経験があります。
本気でやると決めたが、「過去の行動」で信用されなかったのです。
しかし、最後は「信じてもらえた」経験から本気の覚悟に火がついて見事合格を勝ち取りました。
関連記事:大学受験時に親ができるサポートは?関わり方やしない方がいい行為
④ 子どもに「選択」させる習慣を持たせる
第四に、新高2・高3のお子さんに、保護者の方が「選択」させる習慣を持たせます。
自分で決めて行動するお子さんほど、大学受験の後半に伸びる傾向があります。
本人が「やる」と選ばないと、勉強は継続しません。
入塾や勉強開始を、よく保護者の方が決めるケースを見てきました。
しかし、強制的な塾通いは「やらされ勉強」となってしまいます。
保護者の方が勝手に春期講習を申し込み、お子さんがキャンセルするのは代表的な失敗例です。
本人の「やる気」が伴っており、自らの意志で選ぶ経験によって自尊心が育ち、継続力もつきます(※)。
⑤ 全体のスケジュールを把握する
第五に、全体のスケジュールの把握が、保護者の方ができる唯一の”能動的な支援”です。
勉強を教えるのではなく、管理・支援するイメージを持ってください。
【スケジュールの節目の例】
- 試験本番
- 出願時期
- 成績確定
- 秋前に出願
- 学校経由で申請(締切に注意)
マナビズムが見てきたなかでは、男子生徒がスケジュール管理を苦手とする傾向にあります。
その際には、保護者の方の管理・声かけが有効です。
塾側でももちろん案内しますが、家庭でも併走してほしいのが春の4月・5月の時期です。
新高2・高3の大学受験は中途半端なスタートで失敗する
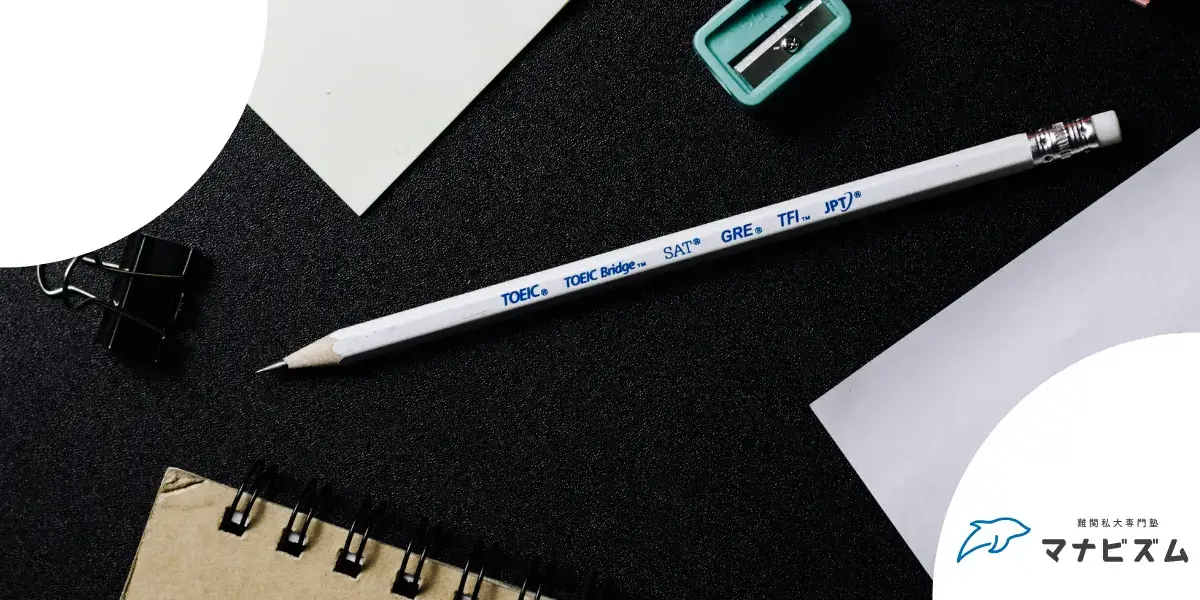
- 「定期テストも大切だよね」
- 「総合型も視野に入れてみたら?」
- 「一般入試も保険でどうだろう」 など
大学受験は、こうして選択を曖昧にするとすべてが中途半端になってしまいます。
やる気がなければ結果も伴わないからこそ、『受験方式の仮決定』をおすすめしました。
だからこそ、マナビズムでは覚悟がないなら、「まだやめておけ」と素直に受験相談で伝えています。
“やる気がある子を受からせる塾”であって、”やる気を維持させるだけの塾”ではないからです。
全力で応援いたしますので、少しでも不安を感じたらぜひ講師に相談してください!
新高2・高3の保護者が春に知っておきたい注意点
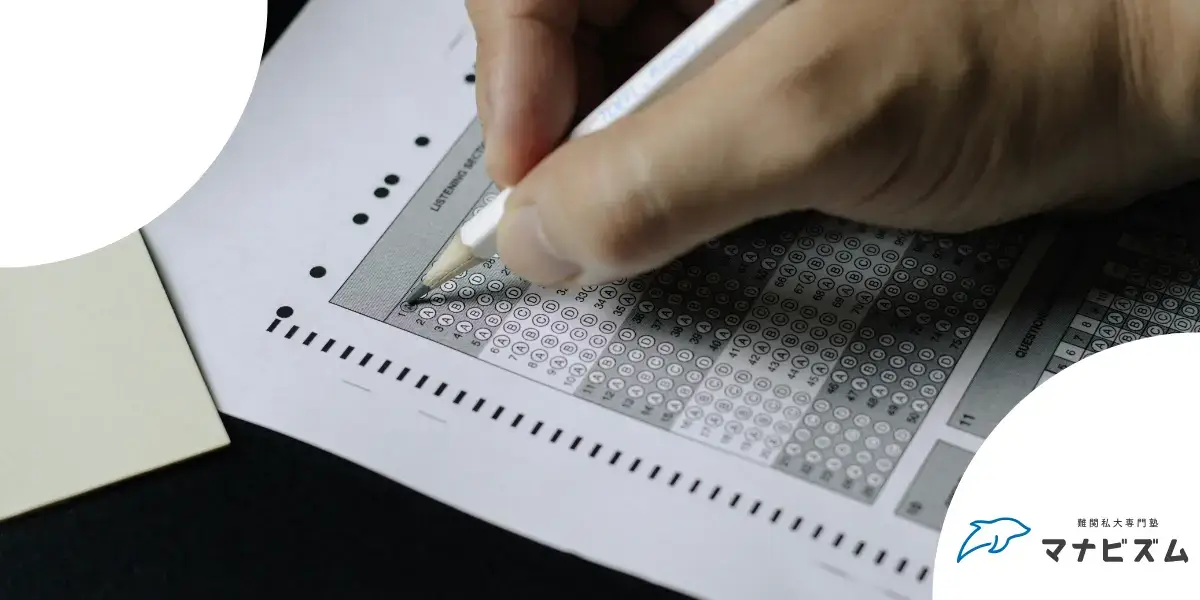
新高2・高3の保護者の方が、春(4月・5月)の時期に知っておくべき注意点は以下のとおりです。
- 指定校推薦は中途半端に狙わない
- 総合型選抜を受かりやすいと誤解しない
- 「総合型+一般」の併用は安易に選ばない
指定校推薦は中途半端に狙わない
もし、指定校推薦にかけるなら、完全に一本化したほうが良いです。
新高2・高3の指定校推薦は、中途半端に狙うのが最悪のパターンです。
「行けたらラッキー」という考え方は典型的な失敗例で、夏前に不合格となった場合、一般対策が間に合わず悲惨な結果になります。
そして、保険としての一般対策は必須だと考えましょう。
総合型選抜を受かりやすいと誤解しない
新高2・高3から総合型選抜を狙うのであれば、明確な目的意識と実績から熟考してください。
総合型選抜は、昔(数年前)と違い、「逆転合格」がもう起こらない形式に変化しています。
いわゆる、実力のある生徒しか受からない形式になっており、専門塾でも「逆転しない」とちらほら聞く状態です。
総合型選抜は、学びたい学科、成績、課外での実績などがそろってはじめて有効な受験方式です。
「早く終わるから」「受かりやすいから」という理由で選ぶと、痛い目を見ます。
「総合型+一般」の併用は安易に選ばない
「総合型+一般」の併用は、やればやるほどチャンスが増えるように見えて、実は合格確率を下げています。
総合型はマッチング型であり、中途半端な準備ではどちらも中途半端な結果になるからです。
仮に併用するなら、「一般8:総合型2」程度の比重で臨むべきです。
この辺りの判断は非常に難しいので、不安な場合は受験相談を活用して第三者の意見も取り入れるのがおすすめです。
まとめ:「受験方式」を決めて行動・優先順位を決めよう
新高2・高3の保護者の方が、この春にやるべき5つのことを再度確認しましょう。
- ① 受験方式を”仮決定”する
- ② 定期テストの「共通認識」を持つ
- ③ 本人の「やる」を信じてあげる
- ④ 子どもに「選択」させる習慣を持たせる
- ⑤ 全体スケジュールを把握する
受験の成功には、早期に受験方式を仮決定し、その方針に沿った戦略と役割分担を親子で明確にしてください。
特に保護者の方は、干渉ではなく理解と信頼でお子さんを支え、自ら選択し自走するお子さんを後方支援する姿勢が求められます。
マナビズムでは、保護者の方とお子さんが同じ方向を向いて受験に取り組めるよう、全力でサポートいたします。
お子さんの「やる気」を最大限に引き出し、志望校合格まで伴走させていただきます。
まずは無料受験相談で、お子さんの現状と目標を詳しくお聞かせください!