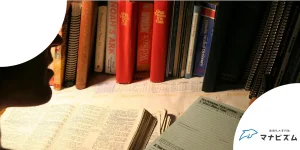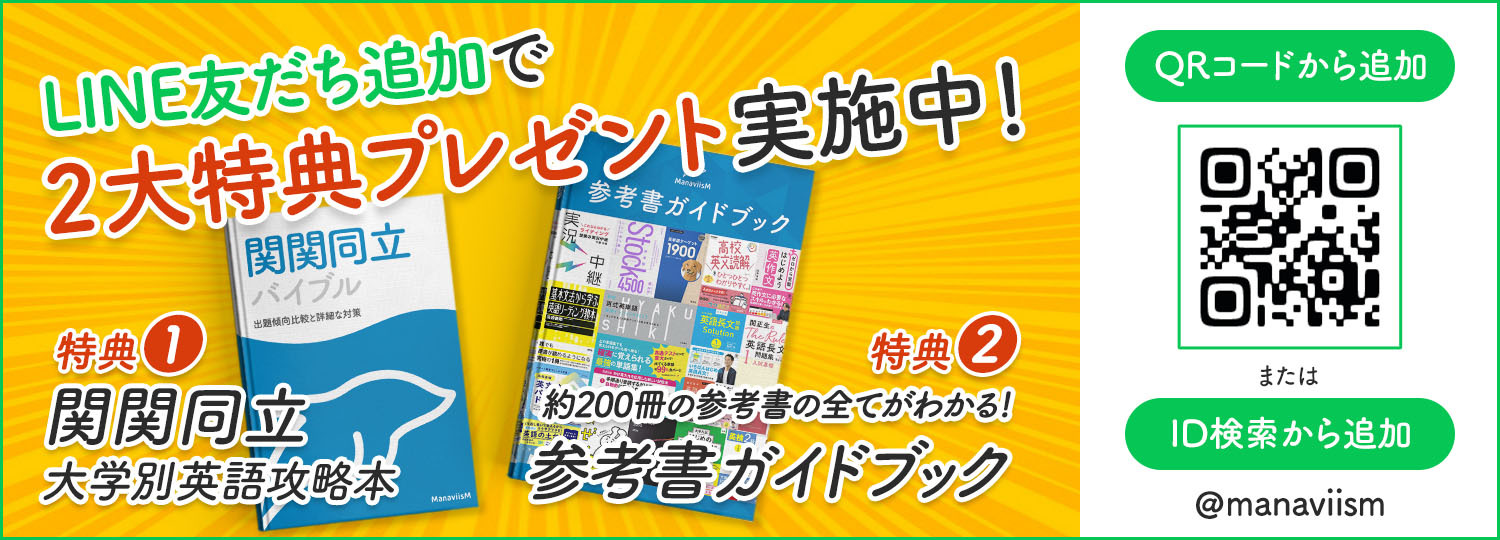大学受験において、第一志望の大学への合格率は60%台という現実があります。
3人に1人以上は第一志望校に入学できていません。
しかし、この数字を受けて親は「うちの子はちゃんと勉強している」「学校の成績も悪くない」と安心してしまいやすいです。
実は、大学受験における合否を左右するのは、受験生本人の努力だけではありません。
保護者の方が「正しい受験常識」を理解しているかが、子どもの合格に影響するのです。
特にはじめて大学受験を経験するご家庭では、高校受験の感覚で判断してしまい、結果的に子どもの可能性を狭めてしまうケースが少なくありません。
そこでこの記事では、保護者の無知が大学受験におよぼす影響と、知っておくべき最新の受験常識について詳しく解説します。
マナビズムでは、保護者の方にも受験の現状をお伝えし、ご家庭一丸となってお子様の合格をサポートしています。
YouTube動画でもご覧いただけます!
今回の動画では、大学受験に関する保護者向けの5つの常識を解説しています。
主な内容は以下のとおりです。
- 高校の成績は一般入試ではほぼ関係ない。
- 共通テストと私立大学の入試では出題傾向が異なり、模試の結果だけで判断できない
- 模試のE判定は一般的であり、逆転合格は珍しくない
- 大学入試は高校入試より難易度が高い結果、第一志望への合格は少数派
- 英検は準1級以上が有利に働き、2級ではアドバンテージになりにくい
以下では、この動画をわかりやすく記事にしました。
ぜひ、ご覧ください。
なぜ保護者の無知が合否に影響するの?

親が「昔の受験常識」や「表面的な情報(模試の判定・内申など)」で判断してしまうと、子どもにとって必要な環境・指導・教材・時間配分がズレるからです。
それは結局、「最短で合格する戦略」から外れ、志望校合格から遠ざかる原因になるのです。
具体的には、以下に挙げた3つの要因が大学受験の合否に影響します。
- 誤った「受験常識」を子に押しつけるから
- 本人が「今の勉強は意味があるのか」分からなくなるから
- 大学受験は”少数派しか受からない”構造だから
保護者の方にとって、「無知」という言葉は強い響きがあるかもしれません。
しかし、ここでお話しするのは決して悪い意味ではありません。
大学受験の仕組みは近年変化しており、保護者世代が経験した頃とはまったく異なる状況になっているのです。
誤った「受験常識」を子に押しつけるから
もっとも多いのが「高校の成績が大切」という誤った「受験常識」の押し付けです。
一般入試では内申点(評定平均)はほぼ関係ありません。
さらに、「共通テストと私大入試は似ている」という思い込みも要注意です。
しかし、実際には共通テストの形式や、定期テストの点数を重視してしまいます。
同じように「模試の判定が悪いから志望校を下げるべき」という判断も同様に危険です。
実際には、E判定から合格を勝ち取るための逆転合格は決して珍しくありません。
大学受験では全国の高3生および浪人生が競争相手になります。
この状況で、まったく傾向が違う試験を同じ対策で進めてしまうと、勉強の方向性がズレます。
お子さんの努力を親が捻じ曲げてしまえば、努力が空回りしてしまうのです。
関連記事:A判定でも落ちます!その模試判定は本当に正しい?【私大志望の受験生必見】
本人が「今の勉強は意味があるのか」分からなくなるから
大学受験への前向きな気持ちが失われ、間違った方向に時間をかけてしまう結果となります。
子どもは「何を基準に頑張るべきか」を見失いやすいものです。
保護者が指標や目標を間違えて伝えると、受験生本人が勉強の意味を感じられなくなってしまいます。
学校の定期テストで良い点を取っているのに、模試の結果はいつも悪い。
そうなれば、「なぜ頑張っているのに結果が出ないのか」という混乱が生じます。
大学受験は”少数派しか受からない”構造だから
高校受験は90%以上の中学生が受けるのと違って、高校生の大学進学率は60%です。
大学受験は高校受験と違い、「周りと同じでは受からない試験」です。
つまり、大学受験では「周りといかに差を付けられるか」が勝負になってきます。
保護者が「高校受験の延長」感覚のままだと、必要な危機感や投資(時間・費用・努力)が欠けます。
そうなれば、激戦となる競争に勝ち抜けません。
保護者様が知っておくべき受験の常識
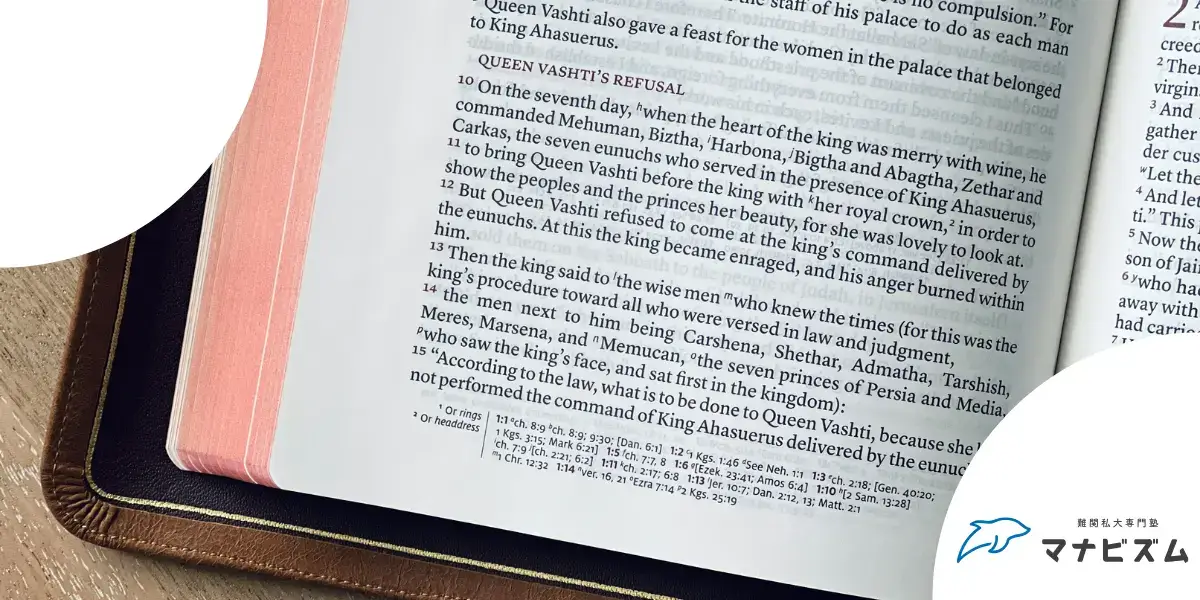
現在の大学受験において保護者の皆様が知っておくべき「本当の常識」は、以下のとおりです。
- 学校の成績は一般入試の合否にほぼ関係ない
- 評定が高くても合格率は上がらない
- 共通テストと私立大学入試は根本的に違う
- 模試のA〜E判定は見かけより遥かに厳しい
- 高校入試と大学入試はまったく異なる
- 英検は準1級以上でなければ意味がない
- 定期テスト・模試の成績を勉強の”指標”にしてはいけない
学校の成績は一般入試の合否にほぼ関係ない
まず、「学校の成績を真面目に取っていれば何とかなる」は完全な誤解です。
高校の定期テスト対策と大学入試で通用する基礎力は別物だからです。
学校の先生も「成績を頑張れ」と否定しませんが、入試に必要な力とは根本的に異なります。
特に第一子の大学受験では、親が高校入試の延長線上で考えやすいです。
確かに指定校推薦や総合型選抜では評定平均が重要です。
しかし、一般入試・公募推薦では学校の成績は「ほぼ関係ない」のが現実です。
すでに評定条件を満たせない場合は、潔く一般・公募型にシフトするほうが合理的な判断となります。
評定が高くても合格率は上がらない
学校の成績が悪くても、大学受験で勝てるようになる方法はいくらでもあります。
マナビズム塾生の平均評定は、3.1〜3.2程度です。
講師の認識としても「4以上取っている子が来たら『すごく頑張ってるな』という印象はある」というレベルです。
しかし、「評定4.1の子と2.9の子で合格率に明確な差があるか」については、一概にはいえません。
評定は指導しやすさに影響しても、入試本番の合格率に直結はしないのです。
勝負の土俵(推薦 vs 一般)を早めに明確にし、受験方式ごとの準備をすべきです。
共通テストと私立大学入試は根本的に違う
共通テストと私立大学入試は、問題の出題者の意図・求める能力がまったく異なります。
共通テスト英語は「処理能力」「情報抽出力」を問う一方で、私立大学では「単語力」「精読力」「論理的読解力」などが必要になります。
共通テスト形式の模試で高得点でも、私大入試の英語力を証明するものではありません。
共通テストと私大入試の差は、旧センター試験時代以上に拡大しています。
共通テスト形式の模試や判定をベースに進路を判断するのは、極めて危険です。
模試は参考程度に留めるべきであり、最重要指標は過去問でも本番と同じ点が取れるかどうかです。
模試のA〜E判定は見かけより遥かに厳しい
A判定は合格率80%以上で全体のごく一部であり、60%以上の受験生がE判定となります。
巷でいわれる「E判定からの逆転合格」は、むしろ王道ルートです。
参考までに、模試の判定比率は以下のとおりです。
| 判定 | 範囲 |
|---|---|
| A判定 | 上位20% |
| B | 〜40% |
| C | 〜60% |
| D | 〜80% |
| E | 残り20% |
EだからといってB判定の大学を第一志望にするのは、目標が低すぎます。
D・E判定から第一志望に逆転するのが”大学受験の常態”です。
判定に振り回されず、何をやるべきかを見極める力が重要です。
判定を見て焦るなら「今まで勉強してこなかった自分」に焦ってください。
高校入試と大学入試はまったく異なる
周囲がまだ勉強していないから自分もしなくていい、というのは完全な誤解です。
勉強法や教材、戦略まで”他人と同じ”では、まず受からないのが大学受験です。
よく比較対象となる高校受験は、90%以上が受験します。
そして、多数派が合格する試験(倍率が低く、努力が報われやすい)です。
一方で、高校生の大学進学率は60%程度。
この大学受験では、全国の高3生および浪人生が競争相手になります。
競争が激化しやすい仕組みによって、少数派しか合格しない試験(差をつけないと届かない)が当たり前です。
大学受験では、保護者も含めて意識を切り替えなければなりません。
第一志望の大学・学部に受かるのは全体の10%程度という現実を理解してください。
英検は準1級以上でなければ意味がない
数年前までは英検2級でも得点換算・英語免除などが可能でした(例:関大)。
しかし現在、2級の入試優遇価値はほぼ消失しています。
「2級で80%換算」などのお得な制度は終了し、準1級以上を持っていないと、加点・換算制度が使えないのです。
もちろん、いまでも一部(早稲田など)の学部では使えますが『限定的』です。
講師の認識としても「2級を持っていても入試では使えない」が共通理解となっています。
ただし、単語力・読解力などの下地があるため、指導しやすいというメリットはあります。
準1級の取得目安は「高3夏前」まで。
それ以降も取得を目指して時間を使うのは、一般入試対策に支障が出てしまいます。
定期テスト・模試の成績を勉強の”指標”にしてはいけない
本当に指標にすべきは、「過去問」、「志望校形式の模擬テスト」の得点です。
定期テストで80点以上取れる子が入試で勝てるとは限りません。
「場当たり的な暗記」や「その場しのぎの勉強」で乗り切っているからです。
そういった子は、長文読解や入試本番の応用力には対応できません。
模試の得点も、共通テスト形式では私大対策にはならないのです。
週単位で学習計画を立て、どこまで到達すべきかを逆算して取り組んでください。
本人が「なぜこの教材をやるのか」「なぜ今これが必要か」を理解して進める学習が必要です。
まとめ:まず保護者が知識をつけて子どもと向き合う
大学受験における親の無知は、どうしても間接的に合否に影響します。
受験制度の変化が激しく、正しい情報を得るのが困難な状況であるのも要因です。
過去を振り返るのではなく、この瞬間から正しい知識を身につけ、子どもと向き合ってください。
学校の成績や模試の判定に惑わされず、真に必要な対策の見極めが、志望校合格への最短ルートとなります。
マナビズムでは、保護者の方にも受験の現状をお伝えし、ご家庭一丸となってお子様の合格をサポートしています。
まずは正しい情報収集からはじめるためにも、お気軽にご相談ください!
大学受験の保護者の方からよくある質問(FAQ)
大学受験は子どもに任せるべき?
親の役割は、子どもが自分で考え、行動できるようになるまでの間の手助けです。主に、情報収集や環境整備、経済的な支援などは親ならではの役割です。ただし、勉強方法や志望校選択などの重要な決定は、最終的には子ども自身に委ねてください。
大学受験生の親がしてはいけないことは何ですか?
もっとも避けるべきは、間違った受験常識で子どもにプレッシャーをかけることです。「学校の成績が悪いから志望校を下げろ」「模試でE判定だから諦めろ」といった発言は禁物です。もちろん、親として子どもに期待するのは当然ですが、プレッシャーになりすぎないよう気をつけてください。
評定が低いのですが、もう良い大学は目指せませんか?
一般入試であれば、評定はほぼ関係ありません。今からでも十分に逆転可能です。マナビズムの塾生でも、評定平均3.1〜3.2程度の生徒が関関同立に多数合格しています。評定が低くても、正しい勉強法と戦略があれば難関私大への合格は十分可能です。
模試でE判定だったのですが、もう志望校は諦めるべきですか?
模試でE判定だったとしても、志望校へ本気で行きたいなら諦めなくて良いです。E判定を受けて絶望しても、逆転合格は決して珍しくありません。受験生がE判定から合格する、これが逆転合格です。
共通テスト形式の模試をもとに進路を決めてもいいですか?
共通テスト形式の模試をもとに進路を決めるのは、私大志望ならNGです。傾向がまったく異なるため当てになりません。共通テストは「処理能力」「情報抽出力」を重視する一方、私立大学入試では「単語力」「精読力」「論理的読解力」が求められます。私大志望であれば、志望校の過去問や私大形式の模試を基準に判断すべきです。
学校の定期テストは高得点ですが、安心して大丈夫ですか?
学校の定期テストの点数だけでは、合否を判断できません。本番で通用する力は別に必要で、定期テストで80点以上取れる子だとしても入試で勝てるとは限りません。入試本番での応用力には、専用の対策を考えてください。
———————————
□具体的に何から始めたらいいかわからない
□合格までの計画を立ててほしい
□1人で勉強を進められない
□勉強しているが成績が伸びない
上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。
———————————