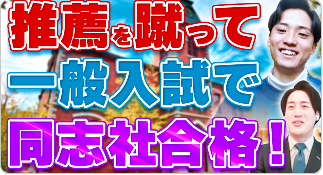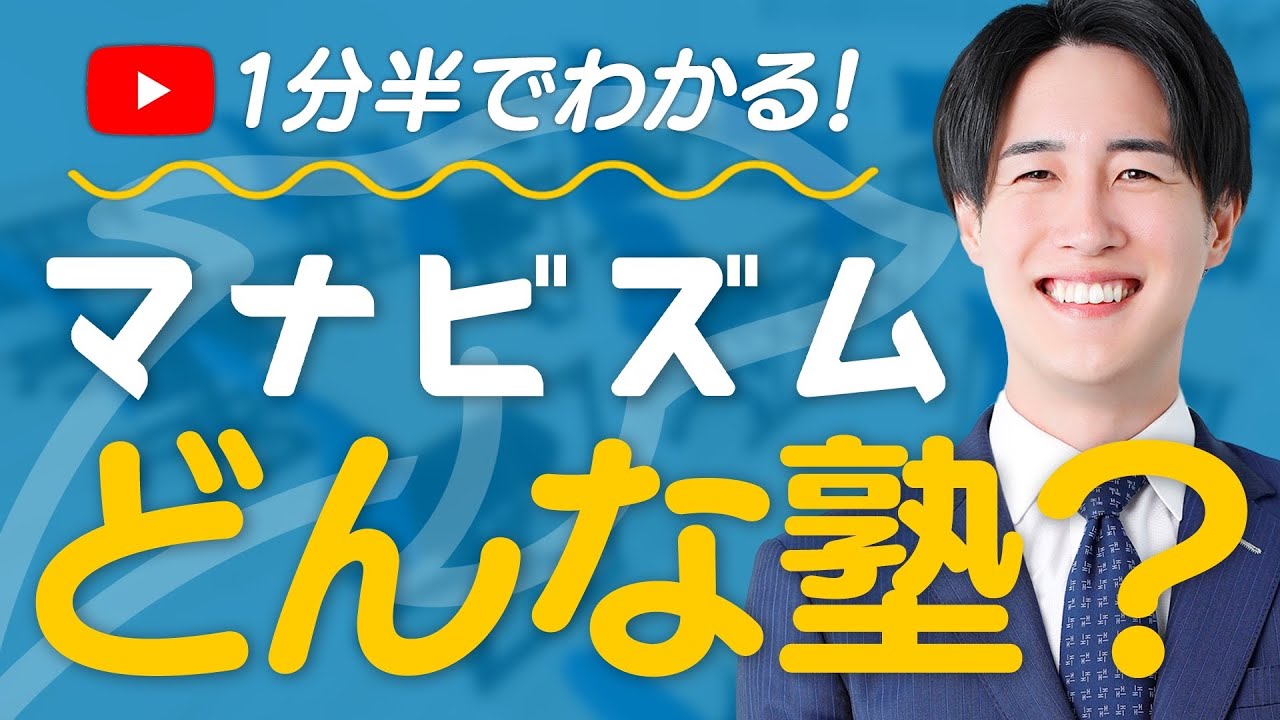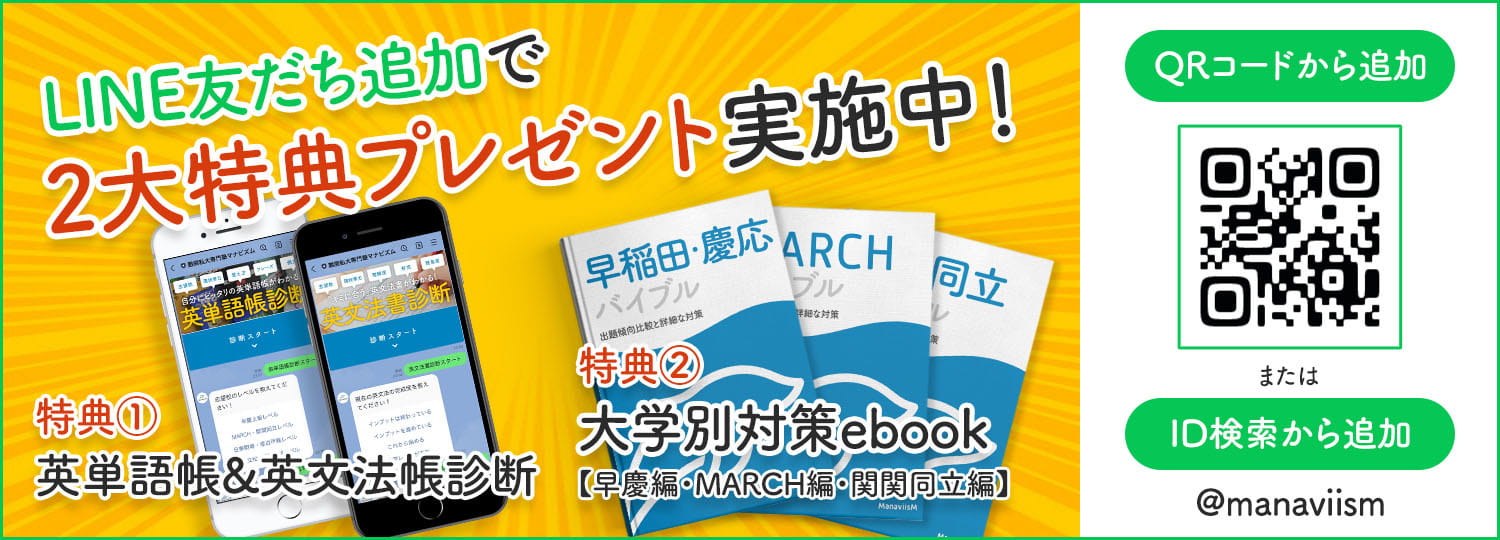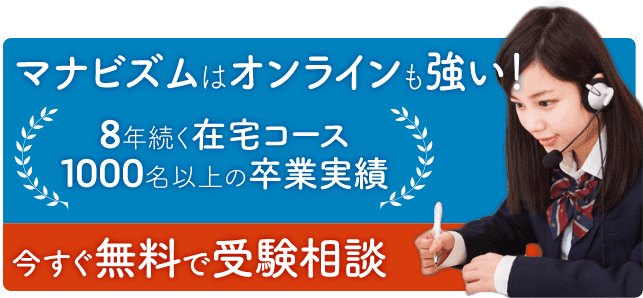難関私大
合格のための
全てをキミに。
マナビズムでは、
難関私大に特化した独自のサポートで、
他塾ならありえなかったであろう
逆転合格を実現します。
難関私大、もしマナビズムで受からないなら、
どこの塾や予備校に行っても無理です。

マナビズム独自のサービス
マナビズムでは多くの予備校や塾で生徒任せになってしまっている「自習学習」や「授業後のサポート」が徹底されています。自習学習で陥りがちな「何をすればいいのか分からない」や、授業の「受けっぱなし」「分かったつもり」を解消し逆転合格を可能にします。
校舎一覧
マナビズムは全国に16校舎あります。
どの校舎も駅から近くアクセスがよいので安心して通学いただけます。
自宅でも受講できるオンラインコースもあります。
- 開校情報 : 2023年11月1日に マナビズム大阪梅田校 がオープン!
- 大阪府
- 京都府
- 兵庫県
- 滋賀県
- 愛知県
- オンラインコース

マナビズム上本町校
大阪府大阪市中央区上汐2-4-6 上六センタービル302
06-6777-8922
大阪上本町駅:徒歩3分
谷町九丁目駅:6番出口直結

マナビズム高槻校
大阪府高槻市紺屋町3-1 グリーンプラザたかつき3号館318/324
072-690-7774
JR高槻駅:徒歩2分
阪急高槻市駅:徒歩9分
JR摂津富田駅:電車5分
JR島本駅:電車7分
阪急上牧駅:電車13分
JR長岡京駅:電車13分
JR京都駅:電車14分
阪急大山崎駅:電車21分
JR山科駅:電車21分
枚方市駅:京阪バス約30分

マナビズム豊中校
大阪府豊中市本町3-1-51 コロンべツェンティワンビル301
06-6335-7522
阪急宝塚線豊中駅:徒歩3分
阪急バス豊中駅:徒歩3分
阪急石橋阪大前駅:電車7分
阪急十三駅:電車10分
阪急梅田駅:電車14分
阪急淡路駅:電車21分
阪急宝塚駅:電車25分

マナビズム茨木校
大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル603
072-665-8555
JR茨木駅:徒歩3分
阪急バスJR茨木:徒歩3分
阪急バス下穂積:徒歩5分
阪急バス府民センター前:徒歩5分
阪急茨木駅:自転車で7分
モノレール宇野辺駅:徒歩10分

マナビズム北千里校
大阪府吹田市古江台4-2-60 千里ノルテビル203
06-6873-6080
阪急北千里駅:徒歩1分
阪急山田駅:電車3分
阪急南千里駅:電車5分
千里中央駅:電車15分

マナビズム堺東校
大阪府堺市堺区新町5-16 堺東アサヒビル3階
072-247-9483
南海高野線堺東駅から徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線 大小路駅から徒歩16分

マナビズム枚方校
大阪府枚方市岡東町14-40 トムソーヤビル4F
072-800-1849
京阪本線「枚方市駅」から徒歩1分

マナビズム天王寺校
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10−1あべのベルタ7階7003号室
06-6649-5667
谷町線天王寺駅:徒歩6分
JR天王寺駅:徒歩6分
御堂筋線天王寺駅:徒歩6分
近鉄阿部野橋駅:徒歩5分
阪堺線天王寺駅前駅:徒歩7分
谷町線阿倍野駅:徒歩1分
阪堺線阿倍野駅:徒歩1分

マナビズム大阪梅田校
大阪市北区芝田1丁目10番10号 芝田グランドビル701号室
06-6486-9954
阪急梅田駅:徒歩3分
JR大阪駅:徒歩6分
御堂筋線梅田駅:徒歩5分
阪神線大阪梅田駅:徒歩9分
谷町線東梅田駅:徒歩10分
四ツ橋線西梅田駅:徒歩13分

マナビズム西宮北口校
兵庫県西宮市甲風園1丁目9−4 第一山本ビル3階
0798-78-5781
阪急神戸線西宮北口駅:徒歩5分
阪急今津線西宮北口駅:徒歩5分
阪急今津駅:電車8分
阪急甲東園駅:電車9分
阪急塚口駅:電車10分
阪神本線西宮駅:電車12分
阪急岡本駅:電車15分
阪神甲子園駅:電車15分

マナビズム神戸三宮校
兵庫県神戸市中央区御幸通4丁目2-15三宮米本ビル1F
078-242-1133
JR「三ノ宮」 駅 徒歩7分
地下鉄「三宮」 駅 徒歩6分
阪神・阪急「神戸三宮」 駅 徒歩10分

マナビズム姫路校
兵庫県姫路市駅前町60
079-263-8078
山陽電車姫路駅:徒歩1分
JR姫路駅:徒歩1分